個人的には「誇張し過ぎた寓話(ぐうわ)」という括りなのだが、暗いところで読み書きをすると目が悪くなる・・というのは、真実ではないと主張したい。
目が悪くなるイコール視力が低下するという意味だが、暗い所で目をつかうことが視力低下に直結するとは思えない。なぜなら、明暗に反応するのは虹彩および網膜であり、近視を進行させる直接的な原因ではないからだ。
無論、暗いところで目をつかうことを推奨すべき・・とは思わない。照度の足りない環境でものを見ようとすれば、どうしても対象物と目の距離が近づく。そして長時間これが続くと、ピントを合わせる筋肉である毛様体筋が緊張状態となり、眼球そのものが前後に伸びる「軸性近視」へと進行する恐れがある。
とはいえ、このような環境的要因よりも遺伝的要因のほうが圧倒的に近視を招く確率が高く、幼少期にどれほど目を使わない生活を送っていたとしても、当たり前に強度近視の道を強いられる者もいるわけで——わたしのように。
などと思っていたところ、眼科医であり医学博士の平松先生が、面白い”例え話”を挙げてくれた(以下、マイナビニュースより抜粋)。
「考えてもみてください。例えば映画館は暗い環境ですが、『映画館で映画をよく観る人のほうが、目が悪くなりやすい』なんていう話は聞いたことがないでしょう。」
——そう、映画を見過ぎて目が悪くなった・・という話を聞かないように、暗いところでものを見たからといって、視力が低下するわけではないのだ。ではなぜ、このような寓話がまことしやかに受け継がれているのだろうか。
視力低下と関係があるのは「距離」です。「あまりにも近距離で本を読んだりしていると目が悪くなる」というのなら正解といえます。
「暗いところでものを見ると目が悪くなる」と言われるようになったのは、おそらく、暗いところではおのずと近距離でものを見ることになるからでしょう。しかし本当に問題なのは「暗いところで」ではなく、「近距離で」ものを見るの部分というわけです。(マイナビニュースより)
要するに、照度の低さが問題ではなく、近距離でものを見ることが視力低下につながるのである・・と言っても、やはり照明のあるところで読み書きをするに越したことはないので、ろうそく一本で夜を過ごしていた昔を再現する必要はないのだが。
*
かくいうわたしは、父が全盲のせいか「暗闇で過ごすこと」に慣れている・・いや、正確にいうと「単なるめんどくさがり」なだけなのだが、たとえば部屋が暗くても、必要に駆られない限りは電気をつけることなく過ごしているのだ。
その理由の一つとして、我が家はベランダ側が一面ガラスでできており、ガラス全体をブラインドが覆っているのだが、ブラインドの隙間から常に光が漏れていることが挙げられる。要するに、真っ黒闇という状況は存在せず、都会ならではの薄明かりが深夜も続くことで、室内を移動することやピアノを弾くことにおいては、さほど影響を及ぼさないのだ。
そして先日、実家を訪れた時のこと。リビングルームで父にスマホの使い方を教えていたわたしは、夕方となり室内が暗くなってきたことに気づいたが、「父は光が見えないし、わたしは薄暗くても問題ないからまぁいっか・・」と、照明をつけずに会話を続けていた。
そこへ、コーヒーを運んできた母が部屋のドアを開けるなり「ちょっと!電気もつけずになにしてるの。暗くて見えないじゃない!」とわめきちらしたのだ——別に、座って話してるだけなんだから、明るさなんてどうでもいいじゃないか。
しかしながら、客観的に見ると異様な光景であるのは間違いない。真っ暗な部屋にヒトがいる・・というのは普通に考えてありえないわけで、あの独房ですら薄明るいというのに(友人談)、あえて電気をつけずに会話をしているのはある意味ホラーである。
だが、わたしにとって明るいか暗いかはさほど大きな問題ではない。薄暗いなりに見えるものや景色、さらに視覚に頼らない感覚が敏感になることで、目で見るのと同じくらいその場を見ることが・・言い換えれば「把握すること」ができるからだ。
見えないものを無理に見る必要はない——なぜか昔からそう思ってきたわたし。これはやはり、父が全盲だからなのかもしれない。見えないものを「見ろ」というほど残酷かつ不可能なことはないわけで、だったらその分「感じる」ことで代替すればいいのではないか。
今ここにある状態、すなわち「与えられた環境」をありのままに受け入れることで、たとえそれが不完全・不十分だったとしても、それなりの面白さや美しさを感じることはできるはず。つまり、目の前にある現実を等身大かつ無理なく堪能することが、わたしの興味の矛先なのだ。
*
・・などとカッコイイ台詞を吐いた後でアレだが、ただ単に電気をつけるのが面倒だったという事実も、念のため補足しておこう。




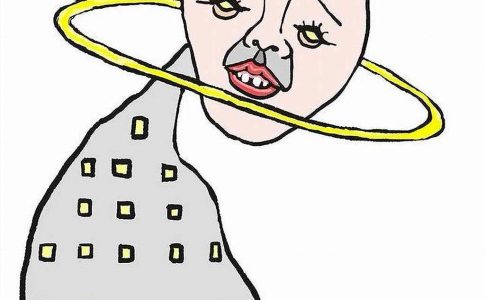

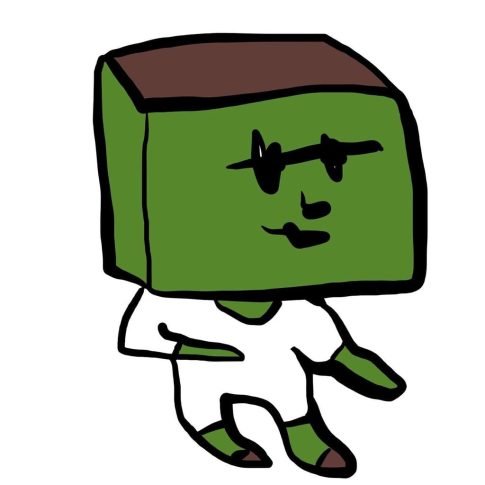
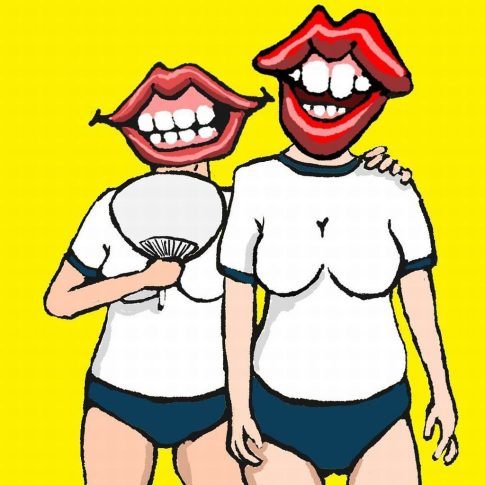

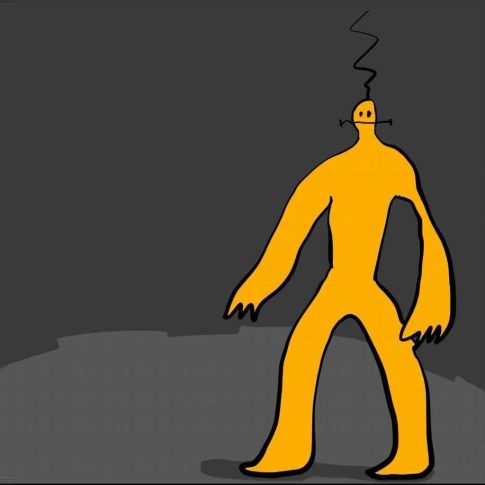
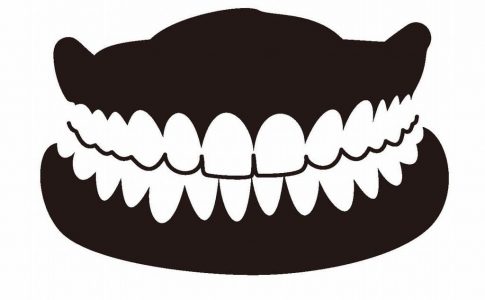










コメントを残す