「モチを食べに行かないか」
私をデートに誘うなら、このセリフで決めてもらいたい。
私はモチが好きだ。
モチの安全を確保するためには、たとえ赤福であろうが容赦なく救出作戦を敢行するほどに、モチが好きだ。
寒空の下、つきたてのモチが食べられると聞き、成田射撃場へとノコノコやってきたのはこの私。
会費1万円を払えば、つきたてのモチが食べ放題なのだ。
「それだけ払うならもっと近場でどうにかなりそうだな」
自宅で暖房にあたりながらゲームなどしている友人に冷静に諭される。
たしかにその通りだ。
「いやいや、モチを食べに来たんじゃなくて射撃の大会に来たんだよ!」
隣りにいた友人が現実的なことを言う。
そうだ、射撃の大会のついでにモチがあるのだ。
しかし、私のなかでの優先順位はモチ>>>射撃となっており、差し当たりモチが出来上がるのを今か今かと待ち構えている。
モチには不思議な魅力がある。
つきたてのモチは、すなわち生きている。
生きているがゆえ、放置するとすぐに硬くなる。
だが釘が打てるほどに硬くなってしまったモチはゴミ箱行きとなる。
つまり、殺されるということだ。
柔らかくむにょーんと伸びるモチは愛らしい。
そして美味しい。
味付けなどしなくても、プレーンなモチの味だけで十分うまい。
ところが私は、硬くなりかけたモチのほうが好みだ。
なぜなら、モチが必死に生きているという事実を、硬さという弾力を通じて確認できるからだ。
(あぁ、私が放置したせいでこのモチは死にかけている)
そう思うと、なんとも愛おしい気持ちになる。
かなり弾力のある、死にかけたモチを噛みしめつつ胃袋へと送り込む。
コレスナワチ救出ナリ。
今日の私はモチに対して積極的だ。
(今まで食べたことのない味付けをしてみよう)
そう思い立った私は、飲みかけのドリップコーヒーの中へモチを落下させた。
(見た目はおしるこだが、わるくない)
真っ白な柔肌にちゃぷちゃぷとコーヒーをかけて、パクッ。
(・・・まずい)
ダメだ、全然合わない。
コーヒーとモチは、まったく相性が良くないことが分かった。
射撃場で食べられるモチの味付けは、
きなこ、お雑煮、大根おろし、あんこ
この4種類。
あんこ以外で回し続けるも、さすがに甘い系がきなこしかないのはキツイ。
たまにプレーンを挟んでみるが、やはり甘みが恋しい。
これまで散々、敵視してきたあんこの鍋をのぞく。
不敵な笑みを浮かべる小豆らがこちらを見上げる。
(クソ、忌々しいヤツらだ)
一旦は引き下がったものの、やはりどうしても甘いモチが食べたくて仕方がない。
再び、あんこの鍋をのぞく。
(そうだ、あのうわずみだけすくい取ってみよう)
私はスプーンを使い、おしるこの表面上の表面である「うわずみ」を、薄っすらとすくいとった。
あんこの色はしているが、お湯で半分くらい薄まっているため、ぎりぎりセーフなのではなかろうか。
(うむ、これはあんこではない。あんこのようなお湯だ)
よく「カレー味のウ○コと、ウ○コ味のカレー」の議論が取り沙汰されるが、あれと似たようなものだ。
あんこのようなお湯は、お湯でありあんこではない。
似て非なるものだ。
そう言い聞かせると、そのうわずみをふわふわのモチへと垂らす。
3、4滴たらしたところで、モチを引き伸ばしうわずみを包み込む。
出来上がったのは真っ白いふわふわのモチボール。
そもそもあんこではないのだが、一見するとあんこと見間違う可能性のあるうわずみを、内側へ丸め込んだモチボール。
よって、見た目は完全なる白いモチ。
そして早速、ポイッと口へ放り込んだ。
(・・・・うまい)
不覚にも、うまいではないか。
過去にチョコレートやジャム、シュガーバター、ハチミツなどと組み合わせてモチを食べたが、その時点ではうまくても、また食べたいとは思わなかった。
一過性の満足は得られるが、持続的な満足にはつながらなかったのだ。
それがどうだ、このうわずみとの相性ときたら、抜群ではないか。
ーー惑わされるな
これはうわずみだが、元はといえば小豆から染み出た汁であり、あんこだ。
あの憎き敵の汁であることを忘れてはならない。
断じてうまいはずがない。
私はあんこが大嫌いなのだから。
あんこ、もとい、うわずみとモチとの率直な感想を友人に告げる。
「そりゃ昔から愛されてるレシピだからね」
ううむ。
Illustrated by 希鳳







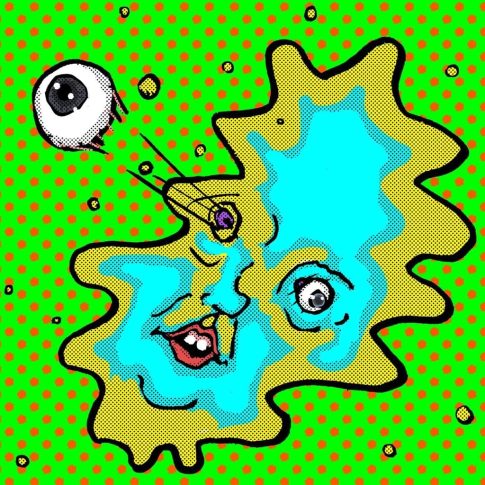


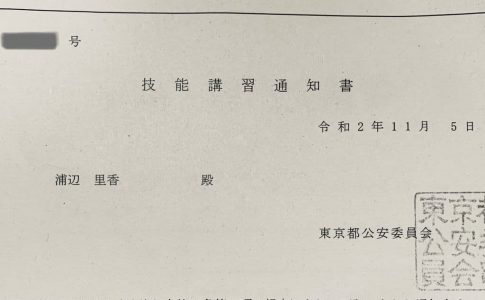










コメントを残す