——結局は、因果応報ってことなんだ。
まばらに埋まっている傘立てを見下ろしながら、この状況を予期していた自分を誇らしく思うのであった。
*
ビニール傘は、日本においては"国民の共有物"ということでいいのではないか・・と、高校生の頃から考えていたわたし。なんせ、あれほど見た目が酷似したアイテムが、所狭しと傘立てに突っ込まれていたのでは、さすがにどれが自分の物か即座に判別できないからだ。
「持ち手が黒いから、分かりやすいだろう」
そう思ってドラッグストアで購入したビニール傘も、いざ学校やジムの傘立ての前に立つと、その半分くらいが黒い持ち手だったりするわけで、もはや色では区別できないのである。
ならばと、持ち手の形が一般的なものとはちょっと違う傘——といっても所詮はビニール傘なので、所有者である本人にしか分からない程度のフォルムの変化ではあるが——を選んだところで、本人には分かる持ち手の違いでも他人には分からないのだろう。帰る頃には、その傘はもうそこには居ないのである。
そして今日、まさにこの状況に陥った。
自宅を出る際に、持ち手の形状が"鶴の首のように細長いもの"を選んだわたしは、「このフォルムは珍しい。ゆえに、誰かとかぶることはないだろう」と、内心ほくそ笑んでいた。傘まみれだったとしても、この持ち手ならば埋もれることなく目立つはず・・などと想像をしながら、どこかで手に入れた"鶴の首のビニール傘"を広げるのであった。
だが、実際に傘立ての前に立ってみると、あまりに多くのビニール傘が刺しこまれているせいで、まるで新手のアートのようになっていた。剣山に刺した花というか、無機質なネギ坊主というか、仕切りの数を明らかに超えた傘が、キャパオーバーのため放射線状に広がっているのだ。
(さすがにこれは厳しいか・・)
一つのマスに2本くらいの傘・・しかも、その9割はビニール傘という混雑ぶりに、「いかに"鶴の首の持ち手"といえども、存在感を誇示するのは困難」という諦めを感じつつ、それでも仕方なく傘を突っ込んだ。
グイグイとねじ込まなければ収まらないほど窮屈な空間に、無理やり収納された我がビニール傘を見つめながら、「もう二度と会うことはないだろう」と密かに別れを告げると、わたしはそそくさとその場を去ったのである。
*
ほとんどの関係者が帰宅したであろう頃、わたしは閑散とした傘立ての前に立ち尽くしていた。そこには、古びたビニール傘と折りたたみ傘がいくつか置かれてあった。
——そう、いつだって残されるのはボロいビニール傘ばかりなのだ。
ビニール傘を持参する者は、無意識に"ロンダリングの精神"が芽生えるのだろう。己が差してきた傘よりも、綺麗で新しいものにすり替える習性が宿るのである。わたしだってそうだ、「この新しい傘はわたしのものではない。だが、もしかするとこのくらい綺麗な傘だったのかもしれない。いや、間違いなくこれがわたしの傘だ!」という思考回路にはなりえない・・とは言い切れないわけで。
その証拠に、傘立てに残されたビニール傘たちの惨めで哀れなことよ。いったい誰が、こんな汚くて破れた傘を恥ずかしげもなく使うというのか。こんなもの、ロンダリング目的で差してきたに決まっている。
そこでわたしは、そんな粗末でゴミ同然のビニール傘に向かって、「今までご苦労さん」と、慈悲深い眼差しで労をねぎらうのであった。
——こうやって、ビニール傘たちは終わりなき旅を続けるのである。逆に言うと、ビニール傘を使うということは、常に"ロンダリング"を警戒しなければならないわけで、その覚悟のないものはビニール傘など使うべきではない。
加えて、ロンダリングの自信がない者もビニール傘の使用は避けたほうがいい。世の中には確実に、ビニール傘を洗浄(ロンダリング)する実行者がいるため、やられたくなければ所持しないほうが安全だからだ。
ちなみにわたしは、ロンダリングの被害に遭った哀れな敗者などではない。よって、ここにある残骸を持ち帰るくらいなら、本降りの雨の中を堂々と闊歩するほうがよっぽどマシだと考えた。
こうして「やられたらやり返せ」という、戦時中のような貪欲な感情を抱きつつ、慌ててコンビニへと駆け込むのであった。
果たしてわたしはビニール傘を買うのか、はたまた・・・。



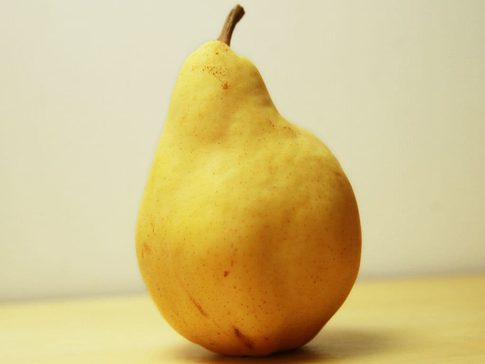
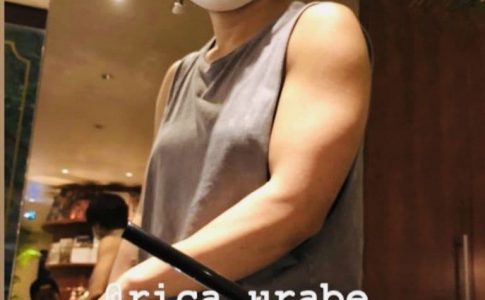


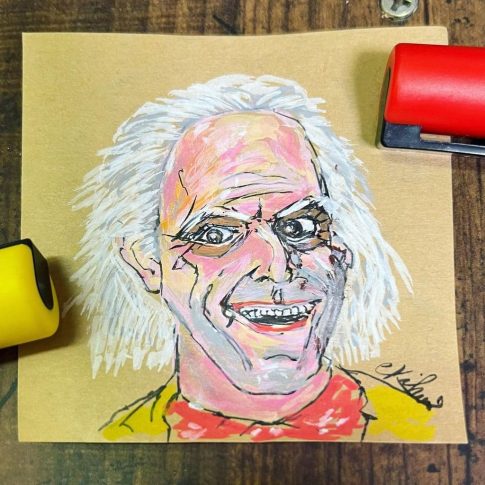


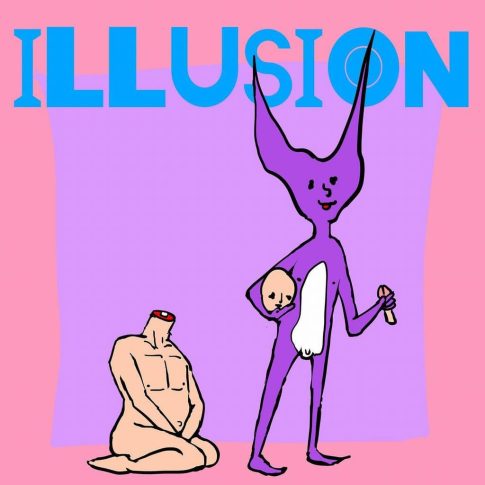










コメントを残す