メンタルの話・・というと、イコール根性論になりがちな傾向にあるのは否めない。実際に、スポーツの世界で「メンタルが弱い」と言われれば、精神的に脆いイメージを彷彿とさせるわけで、昭和の世代ならば「根性が足りないんだよ!」と一喝して終わりだろう。
たしかに、根性が足りない・・という言葉で片付けられる場合もあるが、その「根性」がどの部分を指しているのかは、人によってまるで違う。しかも、根性という単語が意味する本質が、本当に不足しているのかどうかはまた別の話。そして、言われた本人は漠然と「やる気が足りないんだ」と解釈し、ただがむしゃらに取り組むようになる。
その結果、なんだかんだで経験値が上がり、これまで出来なかったことがいつの間にか出来るようになっていた・・なんてことも、よくある話かもしれない。
いずれにせよ、メンタルがどうのこうのという場合、言葉が持つ概念が広すぎるゆえに、本質を的確に貫けない可能性が高い。だが、最終的に障壁を乗り越えた際に感じるのは、「メンタルの問題だったんだな」という結論であり、やはりメンタル・・いや、とどのつまりは根性論なのだと、昭和風情な堂々巡りを繰り返すのである。
しかしながら、信頼できる相手もしくは物事の本質を見抜ける相手から「根性が足りない」と言われたならば、それは紛れもない事実だろう。
言葉というのは限りがあるため、”根性”という粗野でレトロな二文字に集約されるしかないこの世の事情・・というものがある。その上で、相手を信じて根性を見せるしかない場合があるのだ。
これはピアノの話だが、先生から「こう弾こう・・と思わなければ、決してその音は出ません」と、毎回のように指導されるわたし。だが、鍵盤を押せば確実にその音が出るわけで、気持ち云々の問題ではないのも事実。
それでも、音を聴く耳のある先生が「その音ではない」というのならば、それはやはり真実なのだ。そしてわたしは、先生が求める「いい音」を出すためにレッスンに通っているのだから、その言葉に従って「こういう音を出そう」という気持ちを見せなければ・・いや、そういう想いを音に込めなければならない。
その結果、「そう!その音ですね」と、なんとか及第点をもらえるのだ——とはいえ、こんな不確実で不安定なことがあるだろうか。「気持ち」などという、目に見えない、かつ、サイズを測ることもでいない要素を、どうやって音に反映させるというのだ。先生にとっては「それだ」という音も、自分自身では判断できないわけで、だとしたら気持ちを乗せようが乗せまいが、変わりはないのでは——。
このように疑心暗鬼になりながらも、「いい音」を求めて練習を続けるうちに、いつしか「いい音」の出現率は上がる。そしていつの間にか、自分でも「いい音」が分かるようになる・・というより「ダメな音」が分かるようになるのだ。
その結果、全体的にいい音で弾けるようになっている・・という、不思議な成功体験をするのである。
このことについて、実際に「いい音」が出せるようになった時点で振り返ってみると、「結局は気持ちの問題、つまりメンタルの話だったんだな」と結論づけるしかないことに気付く。そして”とにかく気持ちを入れながら、いい音を求めて練習を続ける”という根性を見せた結果、それまで出来なかったことが出来るようになっていた・・となるわけだ。
加えて、この変化は「やるかやらないか」の話でもある。どのくらい気持ちを込めればいい音になるのか・・なんていう定性的な感覚は、自分自身でも実感できないのだから測りようがない。だからこそ、怖くて歩を進めることができないのだ。
ひと筋の光もささない暗闇の中を、その先にゴールがあると信じて進め——などと言われても、なかなかその勇気は出ないだろう。それでも、信頼できる者からそう言われたならば、信じて進むしかないのである。
これはすなわち、進むか進まないかの選択であり、それを決断する根源となるのは気持ち・・つまりメンタルの問題なのだ。
*
ピアノに限らず、どんな物事にもメンタルは付き物。そして、触れることも測ることもできない不可侵領域は、己のさじ加減でいくらでも変化するという特性を持っている。
だからこそ、根性をみせるのだ。
まだ見ぬ自分に会いたいならば、自らが築き上げたメンタルブロックを解除するしかない。そのためには、昭和のメンタルで突き進むしかないのである。
頭で理解してから進む・・というロジカルな方法もいいが、理解できずとも相手の言葉を信じて目を閉じたまま進む・・という、ある種の根性論でしか手に入らないものがあることを知っておくといい。それだけでも人生の可能性が広がるからだ。
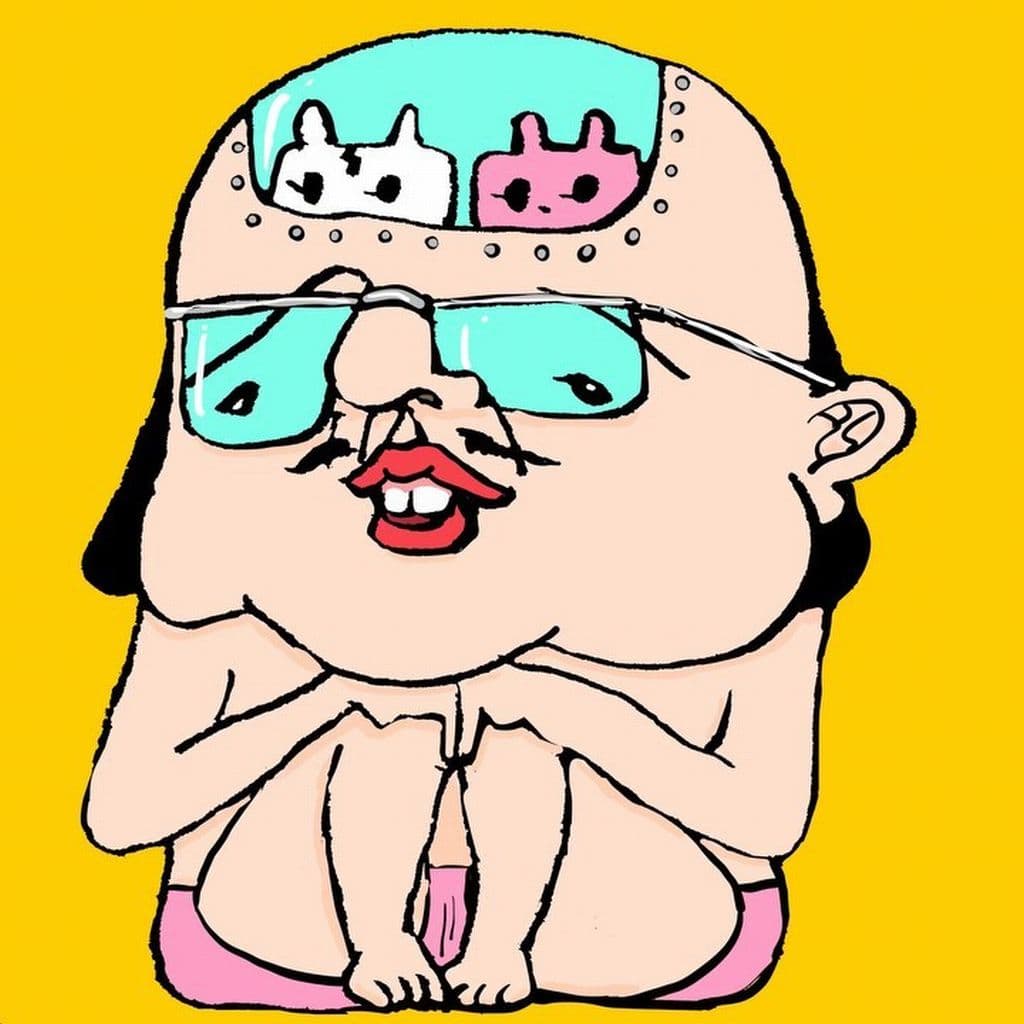





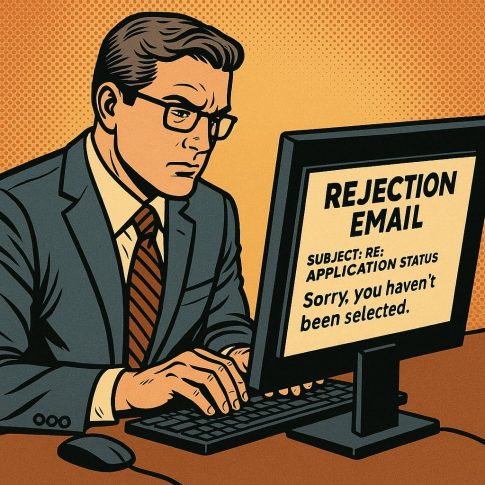














コメントを残す