圧倒的な忘却力を持つわたしだが、なぜか毎年忘れずにこなし続けている作業・・というか手続きがある。それは"転居届を出す"ということだ。
現在の住まいに引っ越してから早くも十年が経過するが、その間、毎年欠かさず転居届の手続きを行ってきたわたし。これは自分自身でもびっくりするほど、定期的かつ継続的、自発的に行っている唯一の作業である。
通常ならば、引っ越しをした翌年までは転居届の効力が発揮されるが、さすがにその間に届かなかった郵便物がそれ以降に届く・・というのは考えにくい。その最たるものが年賀状だろう。
そもそも昔から年賀状を出す習慣のないわたしは、律儀に届いてしまうそれらを申し訳ない気持ちで受け取ってきた。もらったからには返さなければならない——そんな暗黙のルールに縛られて、かつては届いた分だけ年賀状を書いていたが、いつの間にかその作業すら疎かになってしまったが。
それでも未だに何通かの年賀状が届くわけで、こうなると申し訳なさよりも「形式を重んじる、不屈の精神に完敗」といったところ。そして、この"一度も返事を出したことのない年賀状"が厄介なのだ。なぜなら、転居前に知り合った人たちから届くのだが、一度も返事を出したことがないので、わたしが四丁目から一丁目に引っ越したことを誰も知らないのである。
おまけにこの十年間、毎年転送手続きを怠らなかったことから、先方は「四丁目でちゃんと届いてる」と信じているわけだ。
まぁ、年賀状はどうでもいいとして、なぜわたしが転居届だけは忘れずに行っているのかというと、わたしが代表を務める会社の登記が旧住所でされているからなのだ。
あまり大きな声ではいえないが、現在の住まいでは法人登記が禁止されているため、会社の所在地を変更するには別の場所を借りるしかない。だが、誰も訪ねてこない会社であるにもかかわらず、わざわざ事務所を借りるというのも憚られる。さらに、わたしの部屋のオーナーの気が変われば、法人登記の許可が出るかもしれない・・などと楽観的な希望を抱くわたしは、「最終通告までは、転送でやり過ごそう」と決めたのである。
なんせ会社には、税務や社会保険に関する書類がわりと頻繁に届くため、それらを然るべき者の元へと確実に転送する必要がある。よって、会社の代表としての責務をまっとうするべく、一月一日を起算日とする一年間の転送サービスを繰り返し利用してきた・・という経緯なのだ。
それにしても、最初の一年ならば転居届で凌げばいいが、十年を過ぎるともはやこれが普通に思えてくるから不思議。「いつかやろう、今度こそやろう・・」と思いながらも、十年もの間やり過ごせたのだから、もうこれでいいや——という気持ちがないとは言い切れない。いや、そうとしか思えないわけで。
だからこそ、代表者の責務として転居届を毎年出してきたのだ。といっても、e転居なのでスマホから簡単に手続きできるのだが。
*
そんな無責任な状況に終止符が打たれる時がきた。役員の一人が「自宅を法人所在地にしてもいい」と申し出てくれたのだ。
そもそも、なぜわたしが会社の代表になったのかというと、分かりやすくいえば「じゃんけんに負けたから」である。合同会社のメンバーは全員士業者で、設立当初に代表者を決めるにあたり、ちょっとしたいざこざ(?)があった。
弁護士「オレは職業柄、人から恨まれることが多い。だから自宅を公にはできない」
税理士「近々、地方へ引っ越すから自分じゃないほうがいい」
行政書士兼国会議員「大阪の住所じゃあかんやろ」
社労士(わたし)「女性の一人暮らしで、自宅を明かすのは危険!」
それぞれがこのような主張をする中、「なるほど、それはその通りだ」とならなかった唯一の意見が、わたしのものだった。
これに関しては、未だに「なんでだよ!」というわだかまりはあるが、まぁたしかに港区白金の住所は映える。少なくとも大阪市東成区よりはいいだろう——。というわけで、謎の理由で担ぎ上げられたわたしが代表者となったのである。
所詮、わたしごときがさばける書類などたかが知れているわけで、そのほとんどを税理士や弁護士へ転送するのが代表者の仕事となっていた。この時点で「だったら税理士事務所へ転送かけとけばいいんじゃ・・」と薄々感じてはいたのだが、それでも唯一の任務としてせっせと書類を転送し続けてきたのだ、十五年もの長きにわたり。
——それが今、この重責から解放される時がきた。
自宅を登記しても転送、自宅を引っ越しても転送——。そんな"転送人生"からの脱却が決まったわたしは、同時に、唯一無二の重要任務を失うこととなった。雑務が消えるのはありがたいことだが、そうなるとわたしの役割りというのは何なんだろう——。
とりあえずは"お飾りの代表"として、もうしばらく君臨しようと思うのである。









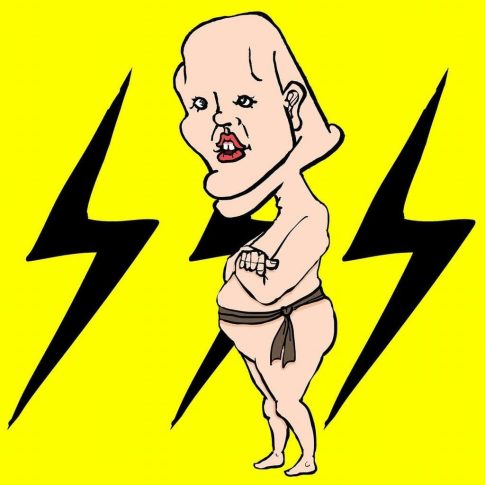











コメントを残す