南フランス、いわゆるコート・ダ・ジュールのとある都市で開催された「自転車によるマラソン大会」に参加したわたしは、プロには劣れどアマチュアの中では上位に位置していた。
フランスといえば、世界三大スポーツイベントの一つである「ツール・ド・フランス」が開催されるなど、自転車のロードレースにかけては世界屈指の歴史とプライドを持っている。なんせ、ロードレースやマラソン大会を実施するには、普段は一般道(または高速道路)として使用している道をコースにするため、大会期間中は地域住民にとっての日常生活に支障が出るわけだ。にもかかわらず継続して実施されるということは、住民らの理解と協力があるからこその賜物なわけで、競技への愛着や誇りを感じるのである。
加えて、その国の・・いや、その地方に住む人々の人間性も関係しているように思う。要するに、道路が使えなくなることを「迷惑なことだ」と思うのではなく、「我々も一緒に楽しもう」という気持ちで受け入れるからこそ、ロードレースの存続が維持できるわけで。
——青空が眩しい南仏の空の下、忙しくペダルを踏みながらも颯爽と駆け抜けるわたしは、ギアをカチャカチャと切り替えながら坂道をのぼっていった。そう、この大会は使用する自転車に特徴・・というか制限があるのだ。いわゆるロードレーサーやマウンテンバイクの使用は禁止されており、スピードや操縦性に欠けるママチャリしか選ぶことができないのだ。
まぁ、このイベント自体が町おこしに似たモチベーションで開催されており、途中途中でプロヴァンス料理をつまんだり、パスティスやリカールといった地元で人気のリキュールを嗜んだりしながら、100キロの道のりを走破するわけだ。そのため、殺伐とした競技モードというよりは、順位を競いつつも安全と楽しみを重視したスタンスで成り立っているのである。
そんな中、わたしはとあるブラッスリー(フランスの居酒屋)の裏に止めてあった、機能的なママチャリを拝借してレースに挑んでいた。店内で飲み食いしている客のものだが、大会期間中は無断で借りてもいい・・という特殊なルールがあることから、それに則ってわたしも勝手に借りたのである。
そしてこの自転車、密かにギアの切り替えができる仕組みになっており、上り坂ならば軽くして、下りになったら一気に重くするなど、他の参加者よりも有利にレースを進められるという圧倒的な優越感に浸っていた。
ところが、レース後半に差し掛かった頃、頼みの綱であるギアチェンジが突如できなくなったのだ。レバーは動かせるもののギアとの連携が取れておらず、通常の回転でしかペダルが踏めないため、上り坂では立ち漕ぎが必須となってしまった。
(・・クソッ、これじゃギアのアドバンテージが生かせないじゃないか!)
見上げる先には急こう配の坂道が続いている。マップによるとこの先には灯台があり、さらに進んだところに大きな公園があってそこがゴールとなっている。つまり、なにがなんでもこの坂道を登りきらなければゴールできないのである。
みるみるうちに後続の選手らに抜かされていくわたしは、やむを得ずママチャリを降りた。そして全力で走り出したのだ——。
この大会のいいところは、自転車の種類に制限はあれど、必ずしも自転車に乗らなければならない・・という決まりはないところだ。つまり、ママチャリを漕いでもいいし電動自転車を使ってもいいし(とはいえ、すぐに充電がなくなるから誰も使わないのだが)、はたまた自力で走ってもいい。そんな自由なルールだからこそ、この地方で長く愛され大勢の参加者で賑わうイベントとして支持されているのだ。
元来走ることが大嫌いなわたしだが、今はそんなことを言ってる場合ではない。そこで、ギアが壊れたママチャリをその場に乗り捨てると、全力で坂道を駆け上がることにしたのである。
長い坂道の途中で、ちょっとしたスナックとリキュールを振る舞うブラッスリーを発見したわたしは、「どうせ順位を下げるなら、ちょっと寄り道でもしていくか」という気持ちに傾いた。おまけに、数名の参加者が店内に吸い込まれていく姿を見てしまっては、わたしもそれに続くしかないだろう・・というわけで、店のドアを静かに押し開けてみたところ——なんと、灯台までの直通エレベーターを発見したのである!
もちろん、自転車ではそのエレベーターに乗れないため、現時点ではわたしにのみエレベーターの搭乗権が与えられたことになる。というか、自転車に乗っている者からすれば、そのエレベーターの存在にすら気がついていない様子——あるぞ、これは一発逆転の可能性がある!!
カラフルなラタトゥイユやクリーミーなキッシュなど、グラトニーな食欲を猛烈に刺激するビジュアルと匂いに釣られながらも、わたしは心を鬼にしてエレベーターへと飛び乗った。そしてR(屋上)ボタンを連打——。
ドアが開くと、そこは灯台の入り口へと繋がるフロアだった。なんと、ものの数十秒で灯台へとたどり着いてしまったのだ。とりあえずダッシュでエレベーターを降りると、マップに沿って通りへと出たわたしは、その先にゴールとなる公園を発見した。そしてここからは下り坂なので、もつれる足をさばきながら転がり込むようにゴールテープを切ったのである。
(やったー!!科学のチカラを借りて優勝することができたぞ!!)
滝汗を流しながらも喜ぶわたしの元へ、大会スタッフがやって来てこう尋ねた。
「それで、使用した自転車はどれですか?」
そこでわたしはこう答えた。
「途中で壊れたので、その場へ置いてきました」
するとスタッフは、
「自転車を使用した場合、たとえ壊れたとしても一緒にゴールしなければならないルールなので、回収してきてください」
と、冷ややかな表情で言い放ったのだ。
(今さら戻ることなど、できるはずもない。しかも、あのチャリを携えて峠を越えてここまでたどり着くのに、どれほどの時間と労力を要すると思ってるんだ。かといって、自転車を使わずにこのタイムでゴールすることなど不可能・・ということは、やはりチャリを回収しなければゴールとして認められないのか——)
先ほどまで流れていた爽やかな汗とは別の類の汗を感じながら、わたしはギアが壊れたママチャリの持ち主を恨んでいた。
(なんでギアの修理をしておかなかったんだよ!おまえのせいでゴールが台無しになったじゃないか!)
そして、見知らぬ持ち主を強く恨んでいたところ、目が覚めたのである。
——あぁ、夢だったのか。




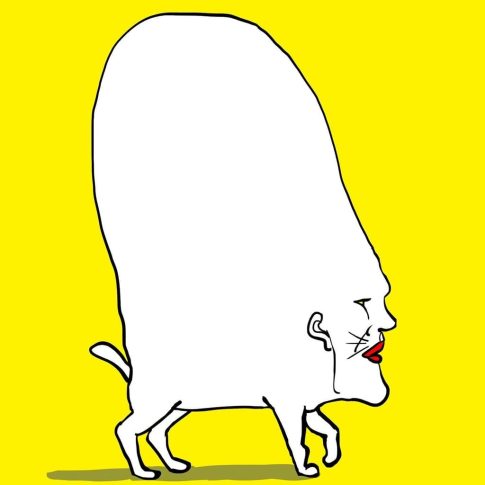
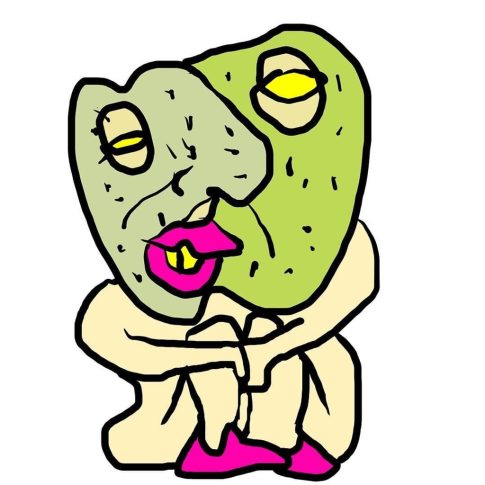















コメントを残す