とある映画を観る前に、予行演習として友人推奨の"ヒューマンドラマ"を鑑賞することにしたわたし。その作品は、2000年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞しているミュージカル映画で、音楽良しストーリー良しの素晴らしい作品なのだ・・と、期待に胸を躍らせていたのである。
ところが、映画のタイトルを口にすると、なぜか誰もが表情を曇らせるのだ。感動的なヒューマンドラマのはずなのに、なぜそんな顔をするんだ——。
その作品とは、ダンサー・イン・ザ・ダーク。ミュージカルの要素があるため、主人公はアイスランドの人気歌手であるビョークを用いており、この配役がドンピシャの大当たり。おまけに、カメラワークも手持ち撮影が中心のため、微妙なブレやにじみ出る日常が、まるでノンフィクションを彷彿とさせる臨場感を演出しているのだ。
(それにしても・・言うほど悲惨な話ではない気がするが)
序盤の展開は、たしかに哀れな境遇の主人公ではあるが、友人らが雁首揃えて表情を曇らせるほどのものではない。それともなにか?彼女たちは映画慣れしていないとでもいうのか——などと友人らの反応に疑問を抱くわたしは、想定内の過酷な人生を歩む主人公を、ホットカフェラテ片手に生温かい目で見守っていた。
とはいえ、先天性の眼疾患によりあと一年で失明する主人公には、どこか他人事とは思えない共感を抱いた。彼女の勤務先であるプレス工場で実施された視力検査では、自身の視力では合格できない主人公を手助けするべく、唯一の友人がカンニングに協力することでなんとか乗り切る・・という場面がある。
(あぁ、これはわたしにも似たような経験がある。わたしの場合は友人の協力ではなく、片目を覆う黒いスプーン・・遮眼子<しゃがんし>を横へずらして、両目で文字を読むことで視力検査をクリアしたわけだが)
そして失明するまでの残された期間で、同じ眼疾患を持つ息子の手術代を貯めるべく夜勤を始めるも、案の定、ミスを犯してクビになるのだ。まぁ、こういう展開になるであろう予感はしていたが——。
そしていよいよストーリーも終盤へと差し掛かった頃、なにかと不遇な主人公は殺人罪により絞首刑を言い渡された。
たしかに彼女は「隣に住む男」を殺した。だがその男は、身を粉にして貯めた息子の手術代を盗んだり、ありもしない虚偽の不貞をでっち上げたりと、さすがに気が狂うであろう罠にはめられた・・という事実がその裏にはあったのだ。さらに、ほぼ失明状態の彼女は事態が把握できず、男が所持する拳銃が暴発したことで彼自身は致命傷を負ったわけだが、撃発の音と苦しみ悶える男の様子から半狂乱となり、パニックからとどめを刺してしまったのだ。
そんな、いくつもの罠や勘違いそしてパニックも相まって、主人公は真実を口にすることなく絞首刑を受け入れた。いや・・さすがに受け入れてはいないが、盗まれた治療費を奪い返し主治医へ届けたことで、息子を失明の危機から救うことができた。
だが、もしも治療費を自身の弁護士費用に充てたならば、彼女は死刑を免れただろう。なんせ、情状酌量の余地は十分あるわけで、最初の裁判では彼女がチェコからの移民であることによる差別や、工場内での視力検査の結果から「視力をほぼ失っていたのは嘘である」という判断をされたことが不利に働き、冷酷かつ極悪非道な殺人犯に仕立て上げられただけなのだから。
しかし彼女は、息子の手術のタイムリミットが近いことを憂慮し、自らの"不本意な死"を受け入れたのだ。
そしていよいよラストとなる、絞首刑が実行されるシーンがやってきた。もはや「想定の範囲内の不遇かつ過酷な人生を歩む主人公の話」という感覚は皆無で、むしろ吐き気をもよおすほどの苛立ちと無力感、そして確実に近づいてくる"死"への絶望から、ほぼ思考停止となっていた。
喉の奥がむかむかするような、脳内で無機質なナニかが渦巻くような感覚——それは、止めることのできない絞首刑への歩みを、ただただ見守ることしかできない視聴者たる無力な自分への軽蔑・・なのだろう。
絞首台に立たされると首へロープを巻かれた彼女は、無事に目の手術を終えた息子のメガネを握りしめ、大好きなミュージカルの歌をうたい始めた。死への恐怖を払拭するべく、全身全霊で熱唱する最中に・・・突如、足元の床が開き絞首刑が実行された。
落下と同時に響く首の骨が折れる鈍い音、それを見て静まり返る"見届け人"たち。ぶら下がる彼女の遺体を隠すかのように、すぐさまカーテンが閉じられた。まるでミュージカルの舞台が幕を閉じるかのように——。
*
・・あぁ、これは確かに顔が曇る作品である。しかも、タラレバが存在しない唯一無二のストーリーかもしれない。いずれにせよ、なんともいえないモヤモヤした気分を抱えながら、わたしはひとり帰路に就くのであった。








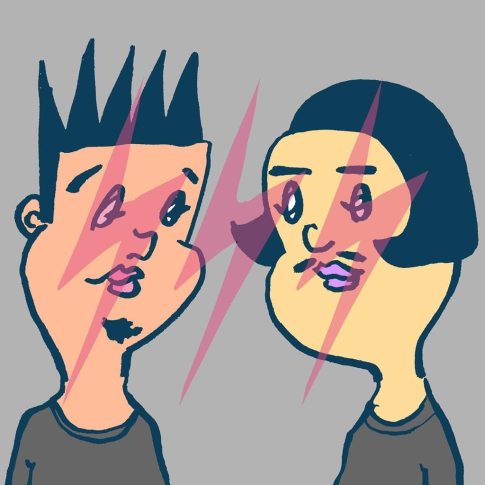












コメントを残す