わが国には「国民皆保険制度」という立派な制度が存在するため、日本に住民登録をする者は、国籍問わず何らかの医療保険制度に加入しなければならない。
有名なところでは、都道府県および市区町村が保険者となる「国民健康保険」が挙げられる。国保は、企業に勤めたり公務員として働いたりする人を除く、自営業や学生さらには無職の住民が加入する制度。これはいわば地域によって加入できる健康保険であり、「港区に住んでいるが、足立区の国保に加入したい!」というわがままは通用しない。
そして、国保とは別に「国民健康保険組合」なるものが存在する。こちらは同種の事業・業種によって組織された公法人で、「医師国保」、「建設国保」、「弁護士国保」「美容国保」「食品販売国保」などなど、158の国保組合が設立されているのだ(令和6年4月現在)。
——というわけで本日、タレントや俳優、スポーツ選手、カメラマン、イラストレーターなど、文化芸能関連の個人事業主のための「大阪文化芸能国民健康保険組合」へ加入を検討しているクライアントに代わり、国保組合を深掘りしてみた。
組合の名前に「大阪」とついているので、大阪在住でなければ加入できないのかと思いきや、まさかの広範囲にわたって認可地域が存在することに驚いた。
(・・・ん?)
関東方面は、東京、神奈川、埼玉、千葉の一都三県が認可されているが、よくよく見ると神奈川県は「横浜市、鎌倉市、相模原市」の3市のみ、埼玉県は「蕨市、新座市」の2市、千葉県など「浦安市」一ヵ所のみではないか。
さすがに東京都は「全域」となっているが、さいたま市や所沢市、千葉市、船橋市といったメジャーな地域がすっぽりと抜けてる。要するに、認可地域外に住む住民は、職業の加入条件が該当しても大阪文芸国保への加入は叶わないのである。
この不思議な認可地域の設定について、当該組合に尋ねてみたところ、
「昔の話なので正確なことは分かりませんが、組合員の方が認可地域外へ転居された際に、新たな認可地域として都道府県知事の認可を受けて追加したのだと思います」
とのこと。ちなみに現在、認可地域を増やす予定はないそうだ。
さらに、保険料の納付に関して「ゆうちょ銀行の自動払込のみ」しか受け付けていないため、大阪文芸国保に加入するにはゆうちょ銀行の口座開設が必須となる。納付書での振り込みもできないため、とにかくゆうちょ銀行が必要なのだ。
その一方で、意外な盲点というか"保険料を節約するための選択肢"が存在することに気がついた。といっても、海外転入者や課税標準額が非課税または低所得者にとって効果的な節税・・というだけだが。
国保組合に納付する保険料には「等級」が設定されている。その中で、最低等級の組合員保険料は8,000円、後期高齢者支援金分保険料3,000円(加えて、40歳以上は介護保険料3,500円も発生)の、合計11,000円(40歳以上は14,500円)の納付が必要となる。
ちなみに、1,000万円を超える課税標準額の場合、組合員保険料はたったの28,000円なので、高所得者であればあるほど国保組合に加入することで、健康保険料を抑えることができるのだ。
ところが、市区町村の国保であれば非課税の場合は7割の保険料軽減が可能。そのため、月々の保険料が2,000円程度で済む・・という事実が発覚した。
海外を活動拠点としていたアーティストやスポーツ選手が帰国した場合、前年度の税申告を日本で行っていない可能性が高い。そうなると税務上は「非課税」となる。
仮に、海外ではビリオンプレーヤーだったとしても、納税先は外国であるため、当たり前だが日本では非課税扱いとなる。よって、帰国初年度は国保組合よりも市区町村国保を選択するほうが、かなり保険料を抑えることができるのだ。
当然、翌年度については帰国後の収入や契約内容によって、国保組合を選ぶのか、あるいは健康保険に加入しなければならないのか、検討を重ねる必要がある。そのため、"帰国した年のみ可能な節税対策"といえるわけだが。
(それにしても、海外転入者の国保が月々2,000円程度とは・・・や、安いな)
とはいえ、国保組合は「保険料の安さがウリ」である。個人事業主で加入条件に該当する職業であれば、国保組合を選択するのがファーストチョイスとなるのは当然。
その一方で、認可地域外に転居すれば自動的に資格喪失となるため、東京都内であればほぼ問題ないが、地方在住者にとってはうかつに引っ越しができない"縛り"を課せられるわけだ。
さらに個人的には、電子申請が利用できない不便さが受け入れがたい。国保組合の中には電子申請が可能な組合もあるのかもしれないが、少なくともわたしが関与する企業はすべて紙での申請しか手段がない。そのため、国民健康保険は郵送、厚生年金は電子申請という、なんとも手間のかかる作業を強いられるのである。
——まぁそれでも、いろんな選択肢が存在するのはいいことだ。なんせ国保組合は、ある意味「職業に対するプライド」の象徴でもある。誰もが加入できないからこそ、仕事に対する愛情や誇りが保険証に凝縮されるわけだ。
(・・・ほんとか?)
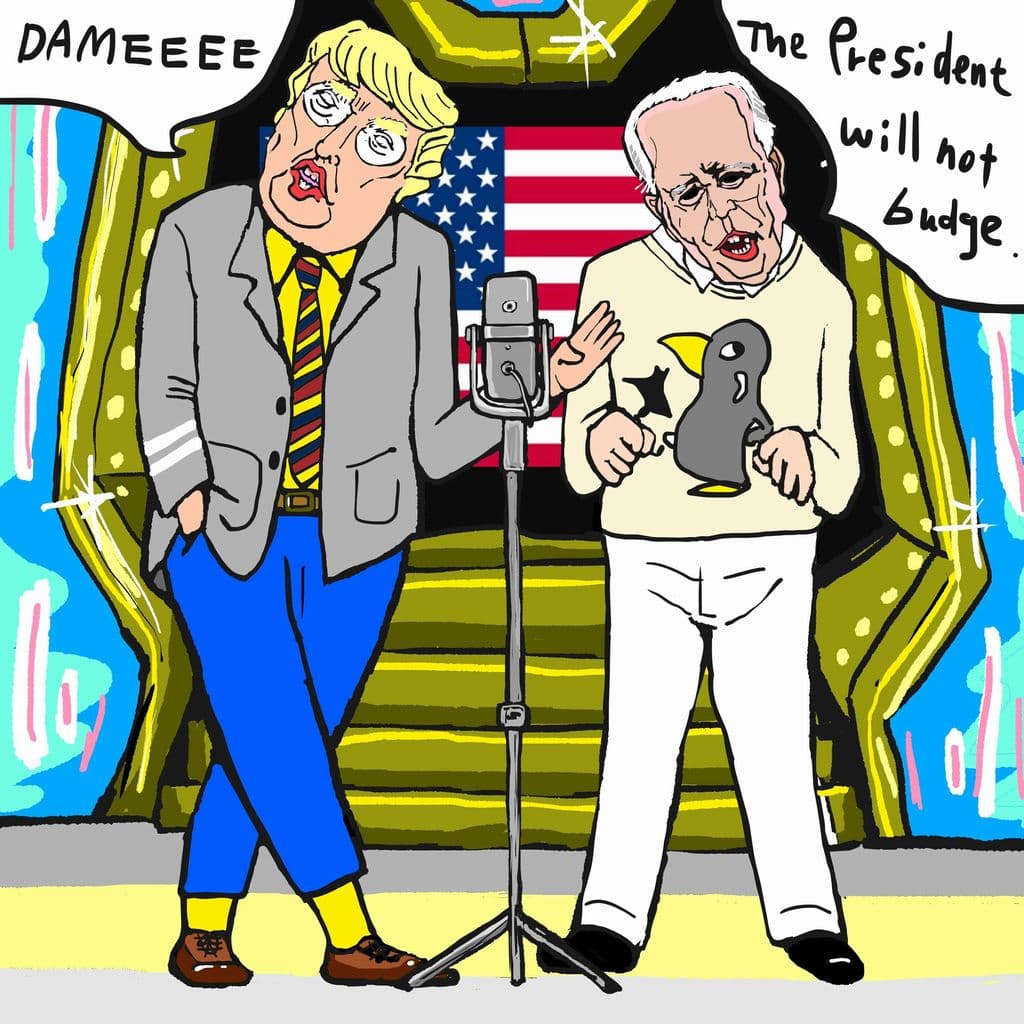







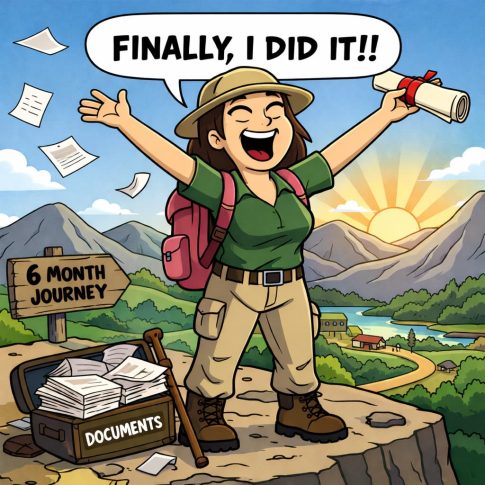












コメントを残す