「お、攻めてるねぇ」
道着チェック担当の男性が、やや驚きながらそう呟いた。——否、わたしは攻めてなどいない。
お気に入りの一張羅であるKINGZの道衣を、購入したそのままの状態で着用しているだけで、先をすぼませているとか、全体的に細く加工したとか、そんな面倒なことは一切していない。
それなのになぜか、今まではスルリと入っていた青いチェッカーが、今日は全然入りそうにないのである。
(このままだと、試合に出られないぞ・・・)
*
ブラジリアン柔術は、試合直前に道着と体重のチェックを行う習慣がある。
そのため、ボクシングや総合格闘技のように、前日の時点で体重を整えるわけにはいかず、試合開始の10分前にクリアしなければならないため、過度な減量は厳禁となる。
よって、ある程度余裕をもって事前に体重を調整しておく必要があり、直前ギリギリに水抜きで整えるようなことは、あまりおすすめできないのである。
そして道着(衣)に関しても、定められた規定をクリアしているかどうかのチェックが行われる。
主に道着の丈や幅、ほつれ、パッチの場所について、担当者によって厳格に確認がなされるのだ。
中でも道着の上着の袖の幅について、手首側から専用のチェッカー(既定の幅でできた樹脂製のものさし)を差し込み、奥まで通ったら引き抜く・・という作業が行われる。
そのチェックの最中に、冒頭のやり取りがあったわけだ。
今まで、何度もこの道着でチェックを通過してきた。それなのになぜ、今日に限ってチェッカーが袖から入ろうとしないのか——。
確かに会場は蒸し暑かった。そのせいで、わたしの腕が湿っているのだろうか。いや、それにしては袖口の空間よりもチェッカーのほうが大きいことの説明がつかない。
いつもは余裕ですり抜けるはずのチェッカーが、今日に限ってつっかえて入らない。そして道着はいつもと同じ、ということは——太くなったのはわたしの前腕、もしくは手首ということか???
男性が二人がかりで、わたしの腕をどうにかしようと悪戦苦闘している。あぁ、まさに「わたしのために争わないで」状態ではないか——。
悪い気分ではないが、それにしてもなぜ手首が太くなったのだろう。
「本当にごめんねぇ、痛いかもしれないけど・・」
なんとかわたしの道着をクリアさせようと、男性が謝りながら強めにチェッカーを差し込んできた。
実際には全然痛くないのだが、なんせ前腕の筋肉に引っかかったチェッカーはビクともしないわけで、これ以上押し込んだら皮膚が擦り剝けてしまうのではないか・・と心配してくれたのだ。
もういっそのこと、皮膚がズル剥けてもいいから差し込んでくれ・・と思うほど、うんともすんともいわない状況にイライラしてきたころ、力強く押し込んだチェッカーがズボッと脇まで届いたのだ。
「おお、やった!入りましたよ!」
差し込んだ男性だけでなく、その周辺で事の顛末を見守っていた人々が、ホッと安堵の表情を見せた。
(フン、入るに決まっている。いつも余裕で入っているんだから!)
さぁ、これで気が済んだだろう、さっさと抜いておくれ・・と思った矢先、実はここからが地獄だった。なんと、今度はまったく抜けなくなったのだ。
入ったのだから抜けるはず——それは当たり前のことだが、入れるときの摩擦でわたしの腕がパンプアップされたらしく、さっきよりも袖の内側が窮屈になっているのだ。
こんな不可抗力、どうしょうもない。無論、わざとやっているわけではないし、わたしはされるがまま突っ立っているだけなのだから。
(脇まで届いたチェッカーを、胸から抜いたらダメなのだろうか・・)
そんな代替案を考えるわたしを尻目に、明らかに焦りの表情を見せる担当の男性は、必死にチェッカーを引き抜こうとしている。
そしてわたしは、されるがままにガクンガクンと体を揺さぶられながら、ただただチェッカーがわたしの腕に密着している感覚をかみしめていた。
(それにしても、なんで腕が太くなったんだろう。なにもしてないのに・・)
思い当たる節もなく、なぜこのような異常事態に陥ったのか、自分自身のこととはいえまったく分からない。そして分かったところで、どうしたらいいのか分からない。
とにかく、わたしの腕がどうなっても構わないから、そのチェッカーをなんとかして引き抜いてくれ——。
もはや祈るしかなかった。そして自然と、周囲で見守る人間の顔からもニヤニヤが消え、神妙な面持ちに変わってきた頃、
——ズボッ!!
「おぉ、やった!抜けましたよ!!」
男性はこの日一番の笑顔を見せた。これで晴れて、わたしの道着はチェックを通過したのである。
わたし自身は「当たり前だ!」とずっと思っていたが、周りは冷や冷やしたり面白がったりと、完全なる他人事を楽しんでいた。
そんな珍しい光景を撮影する者もいるなど、それなりに見せ場を作れたことに満足したわたしは、試合が終わるとそそくさと会場を後にしたのであった。








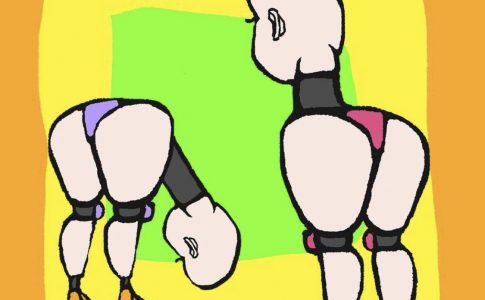












コメントを残す