さすがに顔には出さなかったが、内心わたしは震えた。
アタマの悪いただのデブだと思っていた相方が、まさか一度の説明で柔術のテクニックを再現してしまうとは、出会って10余年でもっとも驚かされた瞬間だった。
——わたしですら、6年かかったのに。
*
あまりに醜く太り果てた相方を見て、「恥ずかしいから、わたしの近くを歩かないでくれ」と懇願したのは数年前のこと。それでも、元来だらしなく自分に甘い相方は、左膝の前十字靭帯が完全断裂していることを言い訳に、あらゆる運動を避けてきた。
「クレー射撃をしているじゃないか!」
・・いやいや、あれは部活で区切るならば文化部だ。体力や筋力でいうと、吹奏楽部といい勝負だろう。むしろ、マーチングバンドと比べたら負けが濃厚となるくらいに、クレー射撃はスポーツというより文化部の要素でできているのだ。
そして、正常値を振り切った高血圧など、明らかに病気へと近づく相方に向かって、
「死にたくなかったら柔術やりなよ」
と、白帯と道着を買い与えたのが先月のこと。人間は、準備を整えられてしまうと断りにくくなる性質がある。よって、すぐさま柔術を始められる状態を作り上げ、強制的に扉を開かせたのだ。
とはいえ、南東北・・おっと失礼、北関東在住者が都内の柔術道場に通うのは簡単なことではない。そのため、まずは区の体育館にて柔術の「じ」の字に触れることからスタートさせた。
柔術経験者ならば誰でもできるであろう「エビ」「肩抜き後転」「ショルダーブリッジ」「テクニカルスタンダップ(柔術立ち)」を覚えさせ、「黙想!」と言われたら目を閉じてジッとするだとか、「おねがいします!」はグータッチだとか、そういった超基本的な動きとマナーを教え込んだ。
そして、体育館での事前練習を二回ほど行ったところで、いよいよ本物の道場への"出稽古"を敢行することとなった。場所はトライフォースのメッカ・池袋本部。
本日のテクニックは「ヘッドロックエスケープ」というもので、果たして奴はついていけるのだろうか——。
ど素人の白帯を引き連れたわたしは、茶帯としてキチンとリードしてあげなければならない。仮にわたしができなければ、当然ながらど素人も困ってしまうわけで、それではせっかくの出稽古が無駄に終わってしまう。
まずは、わたしがしっかりしなければ・・・
そんなプレッシャーとストレスに押しつぶされそうになりながらも、手本を見せるつもりで一連の流れをやってみせた。そしていよいよ相方のターン。
(・・・あれ?一通りできてるぞ)
あれこれ注意したりアドバイスしたりするつもりで、躓(つまづ)くであろう箇所を予想していたわたしは、肩透かしをくらった気分だった。
——おかしいな、普通はここで分からなくなるはずなんだが。
とはいえ、受け手であるわたしの「動きがよかった説」も挙げられる。
テクニック練習というのは、受け手のアクション・リアクションが重要となるため、わたしが上手いことリードしてあげた結果、ど素人でもすんなりできてしまった可能性は大いにあるわけで。
そうこうするうちに、二つ目のテクニックに移った。今度は、先ほどのムーブで完遂できなかった場合の対処であり、一つ目を覚えていないと何が何だか分からなくなってしまう、複雑なムーブである。
(・・・おや?なぜかできているじゃないか)
不思議なことに相方は、ノロノロとではあるが動きを止めることなく、最後までムーブを完遂してしまったのだ。茶帯の大先輩である、わたしからのアドバイスを受けることなく——。
*
これらの事実に対して、わたしは疑問符が拭えなかった。言い方は悪いが、相方はデブでおバカな中年である。高血圧は病人レベルで、醜く肥えた身体は見るに堪えないおぞましさ。
そんな"肥満体の地蔵もどき"が、インストラクションを聞いただけで動きを再現できるものなのだろうか。たしかに、でっぷりと飛び出した腹がつっかえて、ゴロンと後ろへ転がったりもしたが、それでも「やるべきこと」「なぜその動きなのか」を理解していたのだ。
その証拠に、
「あの部分では、かかとをお腹にピッタリくっつけることで、相手の動きを抑えているんだよね?」
「力は入れずに、足を振るタイミングで腕を抜けばいいんだよね?」
などと、一丁前の質問を投げかけてくるのだから。
そして改めて思った・・少なくともわたしは、6年目くらいにヘッドロックエスケープの動きを理解できたわけで、白帯時代などヘッドロックエスケープを習ったことすら記憶にない——この差はいったい、なんなんだ?
*
「向き・不向き」というものは、本当に分からないものだ。そもそもやってみなければ分からないし、やったところですぐには現れない可能性もあるわけで、そのタイミングがたまたま合致したときに適性が認められるもの。
とはいえ相方は、わたしよりもはるかにセンスがあり、柔術への適性があると直感で悟った。だからといって試合に勝てるわけではないかもしれないが、それでも「柔術」を続けるに値するポテンシャルを持っていることを、羨ましく思うのであった。
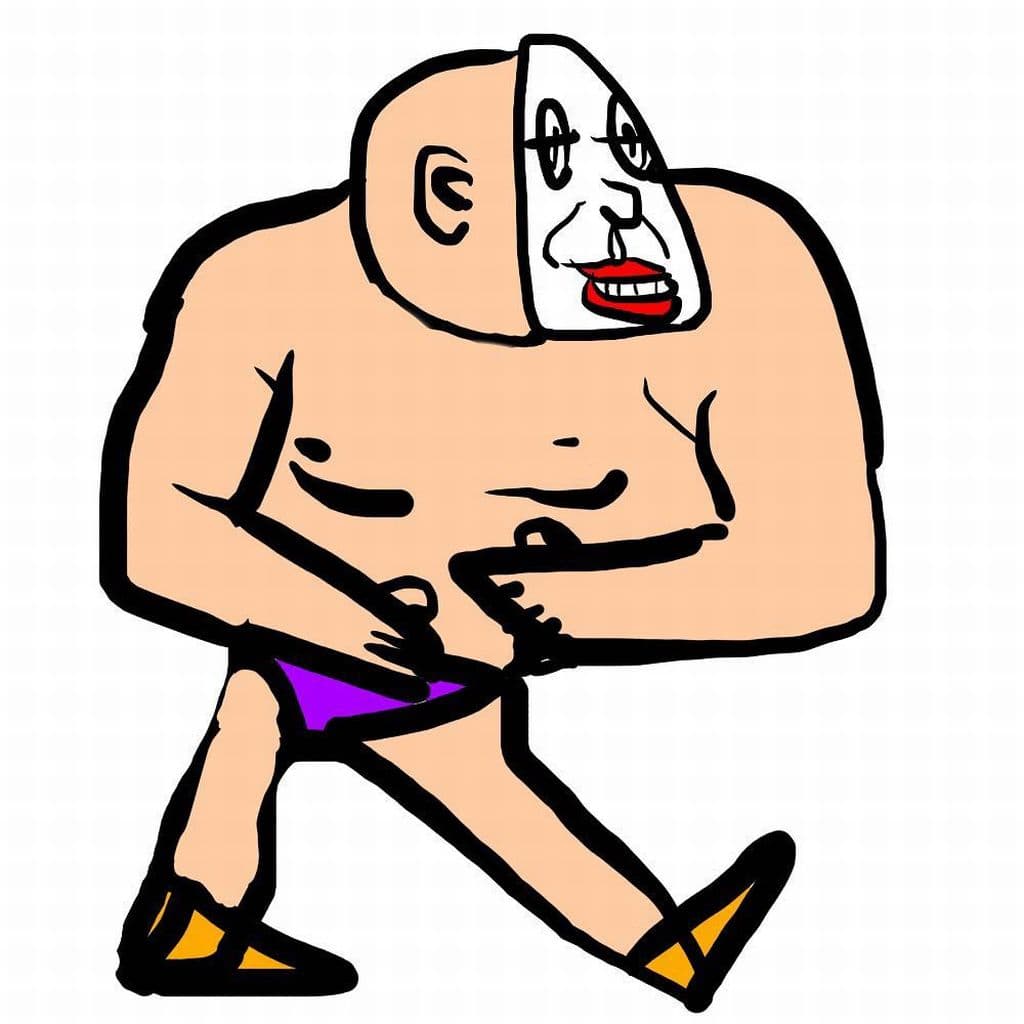


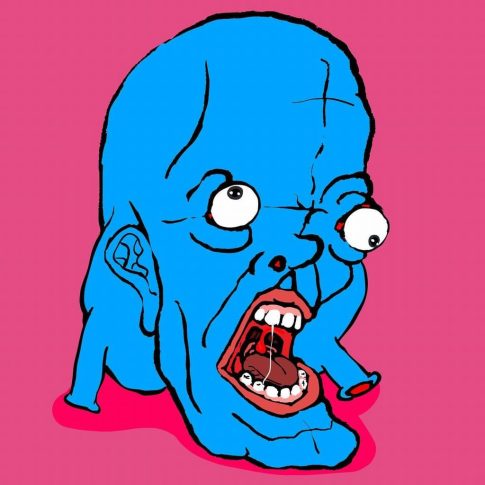



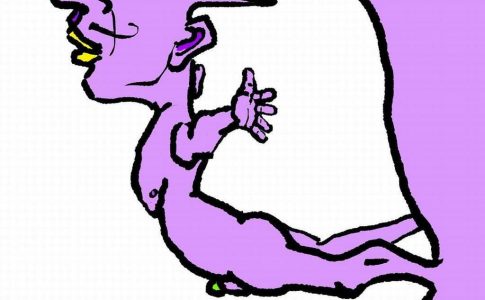


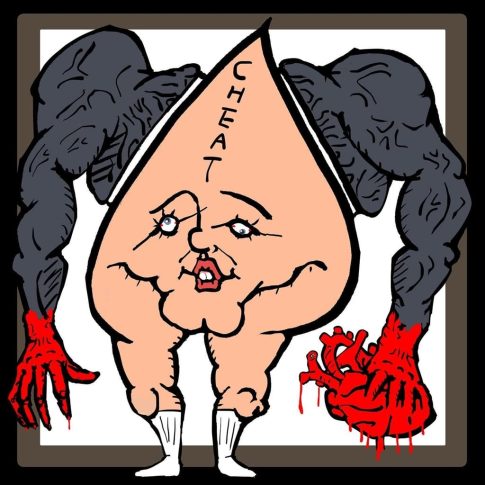










コメントを残す