ブラジリアン柔術という競技を始めてから、わたしはたくさんの試合を見てきた。もちろん、自分自身がエントリーした試合も含めてだが、それでもただ一つ、わたしには忘れられない試合があるのだ。
その試合のマットに立っていたのは、わたしではなく友人だった。
——あれから何年が過ぎたのだろうか。そしてこれからもきっと、あの試合を上回る感慨深い試合に出会うことはないだろう。
*
わたしがまだ青帯の頃だっただろうか。自分の試合が終わりホッと一息ついていたところ、いよいよ仲間の試合が始まるということで、わたしは師匠とともにマットの前にスタンバイした。
これから試合に挑むのは、同じジムの仲間であり抜群の柔術センスを誇る、ニクモトという男だった。細身でイマドキっぽい雰囲気のニクモトは、白帯や青帯男子にありがちなパワー重視の手荒なスパーリングなどするはずもない。そのため、彼が練習に現れると男女問わず引っ張りだこの大人気だった。
ご多分に漏れず、わたしもニクモトと一緒に練習できることがなによりも楽しみで、その長い手足から繰り出されるトライアングル(三角締め)やデラヒーバ(相手の片足に、自分の片足で絡みつく技)にやられながらも、「いつかニクモトに追いついてみせるぞ!」と、憧れのまなざしで彼を見上げていたものだ。
そしていよいよニクモトの試合が始まった。いつもの調子で攻めれば、ニクモトが負けるはずはない。ビビらず焦らず、しっかりと試合を組み立ててくれ——。
寡黙な師匠の隣りで、わたしは大声で檄を飛ばした。肝心の試合展開は一進一退、二人の間に差は感じられないほど、噛みあった攻防が続いている。
よく見ると、ニクモトの相手は青帯だがストライプが4本巻かれている。つまり、紫帯へ「リーチ」ということだ。
ブラジリアン柔術は黒帯を頂点に、茶、紫、青、白と5段階に帯色が分かれており、さらに「ストライプ」と呼ばれる白い線(実際にはテーピングを巻いている)の本数で、およその昇帯までの時期(実力)が分かるのだ。
青帯に昇進したばかりのニクモトがストライプ0本であるのに対し、対戦相手はマックスとなる4本が巻かれている。この状況は、一般的には大きな実力差があるといえるのだが、われらがニクモトはそんな下馬評を覆すほどの、見事な試合運びを展開させているわけだ。
「ニクモト、残り2分!」
わたしは声を張り上げて残り時間を伝えた。ちょうどその頃、くんずほぐれつの激闘を繰り広げるニクモトは、ちょっとした転機を迎えていた。
(あそこから立ち上がれば、ニクモトに2点が入る。そうしたら、勝利がグッと近づくぞ!)
流行る気持ちを抑えながら、わたしはマット上のニクモトへ熱視線を送った。年は若いが、地に足のついた考えと行動力を持つニクモト。髪の毛から滴る汗も爽やかに、必死に立ち上がろうとする彼の姿は、応援する者の心をガッチリとつかんだ。
普段はメガネをかけている彼は、試合の際には当然ながら外している。そのため、目を細めながら残り時間や点数表示を確認するしぐさが見られる。
さっきから何度も、点数が同点であることや残り時間が1分半ほどであることを叫んでいるが、どうやら彼には伝わっていないらしい。仕方ない、もっとデカい声で叫ぶか——。
そう思って大きく息を吸い込んだ瞬間、わたしはマット上のニクモトと目が合った。
無論、視力が悪い彼にはわたしの姿は見えていないだろうが、それでもこちらを向いてハッキリと大きな声で、ニクモトはこう叫んだのだ。
「今、どっちが勝ってますか?!」
会場内を静寂が包む。わたしの隣りに立つ師匠は、手で顔を覆いながら呆然としている。ニクモトの後ろに立つレフリーも、一瞬なにが起きたのか理解できない様子で硬直していた。
そう、ブラジリアン柔術の試合中、選手は声を出してはならないのだ。
力んだはずみに声が漏れてしまう程度は仕方がないが、明らかにハッキリと、しかも滑舌よく点数を尋ねてしまったニクモトは、最悪の場合「負け」となるのだ。
とてつもなく長い時間が過ぎたように感じたが、実際にはほんの数秒だろうか。我に返ったレフリーが手を挙げて、ニクモトにマイナスポイントを与えた。
それこそ、なにがどうなったのか把握できないニクモトは、目をしばたたかせながらキョロキョロしている。すると、寡黙な師匠が珍しく大きな声でこう叫んだのだ。
「い、今ので負けてる!」
本人もショックだっただろうが、わたしも師匠も相当なショックを受けた。かなりいい試合をしていただけに、ここでマイナスをもらったのは痛い。さらに、ニクモトの失態を機に勢いを取り戻した相手は、残りわずかな時間を全力で暴れまくった。
その結果、ニクモトが逆転することはなかった。
*
試合後、今回の勝利によって対戦相手は紫帯へと昇進した。
心の整理がつかないまま、なんとも微妙な心境で「おめでとうございます」と告げるニクモトに対して、相手の選手もこれまた微妙な表情でお礼を返す。
(ニクモトが叫ばなければ、相手の選手は青帯のままだったのだろうか・・・)
激戦を制した!と言えるかどうか微妙な試合だが、そんな余計な心配をするわたしに向かって、真剣な表情でニクモトがこう言い放った。
「魂込めた試合だったけど、あれがオレのやりたかった柔術ではないから!!」
あぁ、そうだろう。そうであってほしいし、そうでなければならない。
それでも、わたしにとってベストバウトであることは間違いないし、何年経ってもあの時の驚きと感動が色あせることはない。
試合に集中していたからこそ、彼は思わず叫んでしまったのだ。明日は我が身かもしれず、誰も彼を笑うことなどできない——。
そう自分に言い聞かせながらも、何年経っても腹を抱えて大笑いする、わたしがいるのであった。
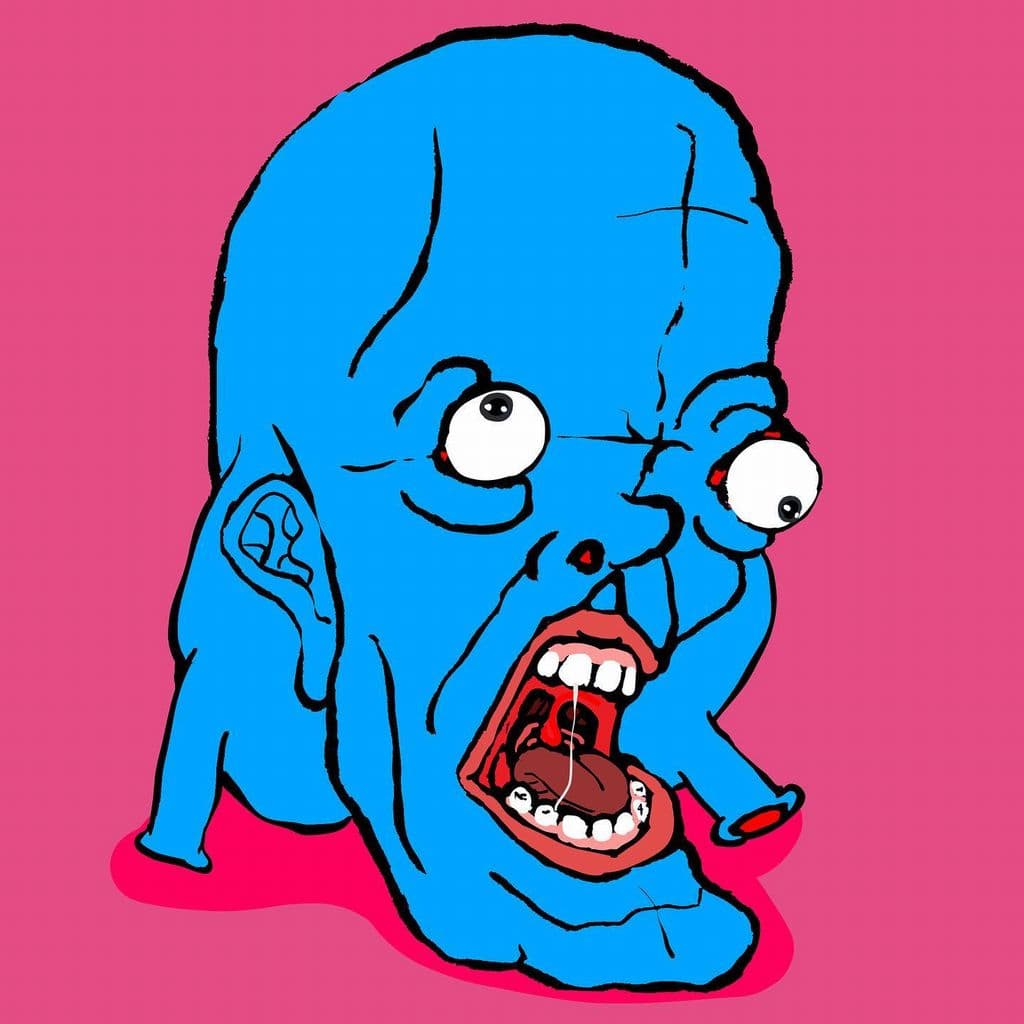








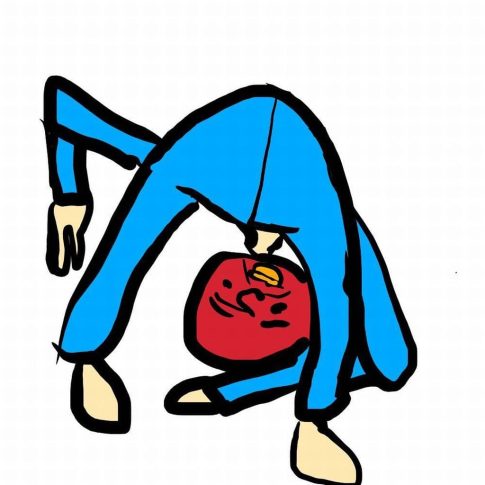











コメントを残す