麻酔から覚めつつある乙は、虚ろな目で唇をだらんと垂らしながらわたしを見ていた。正確には、わたしのほうに顔を向けてはいるが、わたしが誰だか分かっていない様子である。
(こんな風にされて、乙は怒っているかもな・・)
覚醒しきっていない乙にどれほどの意思があるのかは分からないが、その大きな瞳は「もうこんな苦痛を味わわせないでくれ」と訴えているようだった。間近に見る黒目には細い血管が生えている、そんな齢12歳の老犬は、それでもなお人間のエゴで生かされようよしていた。
どうせなら、わたしのことが分からなければいいのに——。
*
これはわたしの持論だが、「長生きしたい」と思うのは人間だけである。動物たちが、どんな手を尽くしてでも長生きしたい・・などと思っているとは思えないからだ。
ただただ必死に今日を生きて、命が尽きる時は抗うことなく静かに目を閉じる——そんな風に感じるわけで、とくに野生の動物は治療すら受けられずに、なすすべもなくこの世を去っていくのだから。
しかし人間にとって、治せる怪我や病気ならば治療をするのが当たり前で、防げる疾病はワクチンや予防接種を打つのが当然の権利となっている。
今となってはペットは立派な家族であり、「犬のくせに」「猫の分際で」などという言葉を口にする飼い主はいないだろう。なんせ、昭和の堅物である父ですら「乙、どうした?ん?」などと、孫に声をかけるじいじのように溺愛しているのだから。
その昔、わたしが小学生の頃に飼っていた雑種の"マリー"は、当然の如く自宅の庭に繋がれていた。雨の日も風の日も小さな犬小屋の中で静かに丸まっているマリーが、もしも今の時代に生きていたならば、それこそ「動物虐待だ!」と糾弾されるはず。だが当時はそれが普通であり、「犬を室内で飼う」など父には到底理解できなかった。
乙を実家へ連れて行ったときも、「犬を家の中で飼うなんて、とんでもないことだ」と大いにご立腹だった。それが今となっては、二人並んで昼寝をするなど、大の仲良しになってしまったのだから微笑ましい。
そんな不思議な魅力を持つ愛玩動物だからこそ、人間は最期まで責任を持って世話をしなければならないし、人間同様に愛情を注ぎ大切に守ってあげなければならないのだ。彼らが言葉をしゃべらない分、鼻水を垂らしたりウンチが柔らかかったりしたら、血相を変えて動物病院へ連れていくわけで。
無論、わたしも「治せるものは治してあげたい」と考えているが、それでも全身麻酔の状態とはいえあれこれ痛い思いをさせるのが、本当に"大切な家族たるペットのため"なのかどうか、ニンゲンの物差し以外で測ることができればいいのに・・と思ったりもする。
一日でも長く生きしてほしいと願うのは、果たしてペット本人なのか、それとも飼い主である人間なのか——。
乙は、今この時点でできる治療をすべて施してもらった。外科的処置はさることながら、わたし自身が理解し納得できる最善の治療を受けることができた・・というのが正しい言い方か。
だが乙にとったら「こんなにも痛くて苦しいことを、お願いした覚えはない!」と思っているかもしれない。つまりは、飼い主であるわたしのエゴなのだ。
鼻腔内にびっしりとこびりついた腫瘍を、あの手この手で見事に除去してもらったところまではよかった。だが、鼻孔から通した柔らかいカテーテルが、何かにぶつかりグニャっと曲がるような感覚があった・・と、手術を行った獣医師が教えてくれた。
ならば硬いカテーテルならばどうなのか?という質問に、「鼻腔の天井は薄く、その先には脳があるんです」とのこと。つまり、一歩間違えばカテーテルが脳に突き刺さる可能性があるわけだ。
ましてやフレンチブルドッグの乙は、短頭種という鼻ペチャの犬種であるがゆえにマズルが短い。そのため、鼻の長い犬に比べると"鼻道に何かを入れる"という行為は難しいことなのだ。
今回の治療に全力を尽くしてくれた獣医師は、手術後にこう告げてくれた。
「遠くから来ていただいたのに、ご期待に応えられるような結果にならず、本当に申し訳ありませんでした。なんとか呼吸をさせてあげたかったのですが・・・」
実際に鼻腔を覗いてみなければ分からないことも多いが、それ以上に腫瘍の増殖が速かった。さらに鼻孔寄りにもこびりついていたことから、予想以上に困難を強いられたのだ。
わたしからすれば、感謝こそすれど恨むことも怒ることもあり得ない。むしろ最高の治療を施してもらったわけで、彼の直観や洞察力、そして豊富な経験値による所見と内視鏡手術には、感謝を超えて感動を覚えるほどである。
ちなみに、これが人間ならばいくらでもやりようがある。犬の鼻線腫(癌)について形成外科のドクターに話したところ、「そんなの簡単ですよ、鼻を切り開いてでもチューブを入れればいいんだから」と言っていた・・・もちろん「人間ならば」の話だが。
この話は伝えていないにもかかわらず、獣医師はこうも胸の内を語ってくれた。
「動物医療も人間医療のようになれたら・・と、私もつくづく思います。しかし現状、サイズ感や解剖学的なこと、そして医療器具のキャパなどのさまざまな弊害により、"人間医療に近づくのは難しい"というのが現実です。だからこそ、もっと精進しなくてはと毎日思っています」
・・獣医師には獣医師なりのジレンマがある。人間ならば簡単に対処できることでも、動物にとってそれは決して簡単なことではないからだ。
そしてその時、わたしは知った。
「人間ならばどうにかできる症状でも、動物では手の打ちようがない場合もある。これらも含めて"病気"であり"寿命"なんだ」
ということを——。
*
酸素室の中から必死にこちらを見つめる乙は、自分が何をされているのか分かってはいない。仮に分かったとしても、果たしてそれを喜ぶのだろうか。
鼻呼吸ができなければ、犬は寝ることができない。つまり乙は、この一か月ほとんど眠ることなく生き続けているのだ。気がつけば常に舟を漕いでおり、目を真っ赤に充血させながらバタンと倒れては起きて・・を繰り返す乙を見ていると、あまりの辛さから"一時間でもいいから眠らせてあげたい"と思ってしまった。
子豚のようにまるまるとした体格がチャームポイントだった乙は、今では骨と皮と血管だけのみすぼらしい姿になっている。体重の激減が睡眠不足によるものなのか、あるいは別の理由なのかは不明だが、なぜか食欲だけは旺盛のままなのだ。・・この奇妙な違和感もまた、謎である。
今回、二度目の生検を行ったので改めて病理の結果待ちではあるが、今度は「鼻腺癌」と出るのかもしれないし、再び「鼻線腫」なのかもしれない。それ次第で新たな治療方法が現れるかもしれないが、乙に嫌な思いをさせてまで強行するべきものなのか判断に迷う。
わたしとしては、一日でも長く乙とわたしの人生が続くことを願うが、乙はきっとそうではないだろう。その小さく短い鼻から大きく息を吸い込んで、ぐっすり眠りたいに決まっている。そのまま目を開くことなくこの世を去ったとしても、息をして眠ることができたならば、乙にとってはそのほうが幸せに決まっている。
治療に携わった人間は、誰もが全力を尽くしてくれた。つまり、人間側に悔いはない。
だが乙は、乙は果たしてどう思っているのだろうか——。永遠に知ることのない答えを探しながら、「これも含めてペットを飼うことなのだ」と、飼い主のほうが学ばされるのかもしれない。




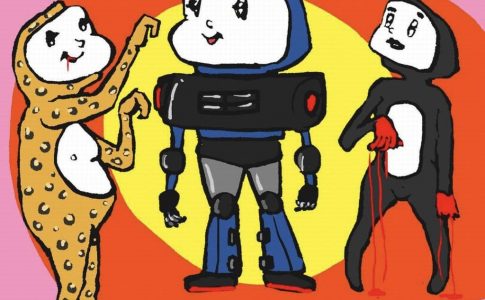


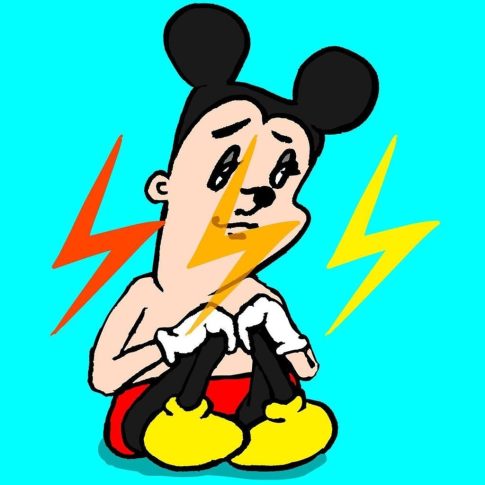













コメントを残す