よく「地方再生」という言葉を聞くが、それは地方へカネをばら撒くことで実現する未来ではない。むしろ、地方に住むひとたちがやりたいことをやったり、挑戦したいことに取り組んだりすることで、その結果として地方が活気づくことを指すのではなかろうか。
「過疎化した田舎を盛り上げること」を目的とするのは、実際のところかなりの無理がある。意図的に作られたレールは、地元住民からするとどこか異質であり、確実に不信感を抱くこととなるからだ。
むしろ、「地域のため」などというスケールの大きな目標よりも、「自分がやりたいこと」くらいの身近なモチベーションのほうが、不自然さがない上に楽しみながら続けることができる。
なんせ、嫌々やらされる仕事というのは、自他ともに気持ちの良いものではない。ところが、自分のやりたいことであれば、少なくとも自分自身は満足できるわけで。
つまり"本人が楽しめること"こそが、地域再生への第一歩となるのではなかろうか。
*
友人の母は75歳にして、地元である栃木県那珂川町でカフェをオープンした。その名も「Filippo Madre(フィリッポ マードレ)」。
一言で「カフェ」といっても、その実態はかなり贅沢な"レストラン"といっても過言ではない。なんせ、練馬の有名ピッツェリア「Gitalia da FILIPPO(ジターリア・ダ・フィリッポ)」のピッツァ生地を使い、同じく、FILIPPOから発信された100%国産小麦「匠のパスタ」のスパゲッティがあり、おまけにFILIPPO名物「幻のバスクチーズケーキ」までもがメニューにあるのだから!
都内在住でも、練馬(石神井公園)まで出向かなければ対峙できないご馳走たちと、ここ那珂川町で出会うことができるのだから、これは単なるカフェというには秘密がありすぎる。
——そう。何を隠そう、マードレを切り盛りするのは、フィリッポのオーナー・岩澤正和の母なのだ。
「どうせ家にいたってテレビ見てゴロゴロするだけだから、それならこうして店に立っているほうがいいかな・・って」
はにかみながら、正和の母・真喜子さんは話してくれた。
じつは真喜子さん、かつては同地域で「シャトー」というレストランを営んでいた。わたしも一度だけ訪れたことがあるが、昔ながらのハンバーグやボリューム満点のステーキセットに舌鼓を打ったことを、最近の出来事のように思い出す。
およそ20年に渡り地域で愛された店を閉めてから、真喜子さんはゆっくりとリタイア人生を謳歌した・・かどうかは分からないが、やはり料理人としての血が騒ぐのだろう。加えて、息子からの
「(母ちゃんが)好きなことをしながら、いつまでも元気でいられるように、無理のない範囲でカフェをやってみたら?」
という提案に乗ったのだ。
息子の心強い後押しとともに、娘である真澄さんも厨房に立つことで、真喜子さんはカフェオープンに向けて盤石の体制を整えることができた。
そして2023年12月19日、いよいよFilippo Madreがこの世に産声を上げたのである。
*
(ん?厚焼き卵MAKIKOって、なんだ・・・)
メニューを見ながら、一つだけ想像のできない料理を発見した。MAKIKOは十中八九、真喜子さんのことだろう。ということは、彼女は厚焼き玉子が得意なのだろうか——。
いや、待てよ。もしかするとMAKIKOという名のニワトリを飼っているのかもしれない。そのニワトリ、すなわちMAKIKOの卵を使った厚焼き玉子、という意味なのか——。
考えたところで答えは出ない。わたしはさっそく挙手をすると、真喜子さんへこの小さな疑問をぶつけてみた。
「あぁ、それねぇ・・息子が勝手につけてくれたの」
なんと、イチオシの鶏卵を使った料理を考えていたところ、正和が勝手に「MAKIKO」というネーミングにしてしまったのだそう。
「どうせ誰も頼まないでしょ・・と思ってたら、いきなり頼まれて驚いたわぁ」
物珍しそうな顔で、"厚焼き卵MAKIKO"を注文したわたしを見つめる真喜子さん。——わたしはまんまと、息子・正和の策略にハマったのである。
(そもそも、こんな洒落たネーミングの玉子焼きがあったら、頼まずにはいられないだろう・・)
こうして、マードレ開店一発目の"MAKIKO"は、このわたしがめでたくいただいたのであった。
(いうまでもないが、卵の味も玉子焼きの味も美味かった。コクのある甘みとまろやかな舌触りは、添えられた醤油など使用することなく、あっという間に食べ終えてしまうほど美味だった)
*
大きなイチゴと生クリームたっぷりのドルチェピッツァに、匠のパスタのボロネーゼ、柔らかなバスクチーズケーキとハンドドリップ熟練コーヒー、そして、那珂川クリームソーダイチゴ添えを胃袋へ送り込んだわたしは、ふと思った。
(地元の人間が、自分たちのやりたいことを形にすること。そしてそれを心から楽しむこと。それこそが、真の意味で地域の活性化につながるんじゃないか?)
なぜなら、わたしがカフェに滞在している間に、何人もの地元住民が店を訪れた。開店祝いの花を持ってくる者もいれば、仲間を連れ立ってやってくる者もいた。そして、誰もが笑顔でこの店のオープンを喜んでいたのだ。
——地元で愛される店っていうのは、こういうことなんじゃなかろうか。
さらに、こんな出来事も聞かせてくれた。
「シャトーに通ってくれていたお客さんが、ここへ来てくれてね。帰り際に涙をポロポロ流しながら、『また会えてよかった』って言ってくれたのよ」
この話を聞いたとき、わたしは込み上げる涙を堪えた。20年近く、この地域を代表するレストランとして、腹ペコな住民の胃袋を満たしてきた名店・シャトー。それがいつしかこの世から消えてしまい、言葉にできない寂しさを覚えるファンが、実のところ多かったのだろう。
——あれから5年。突如現れた小さなカフェを覗くと、そこにはあの"シャトーのおかみさん"が立っていたのだから。
*
栃木県道52号線沿い、馬頭広重美術館近く。目の覚めるような青い看板が眩しい「フィリッポ・マードレ」へ、ぜひ一度、足を運んでみてほしい。




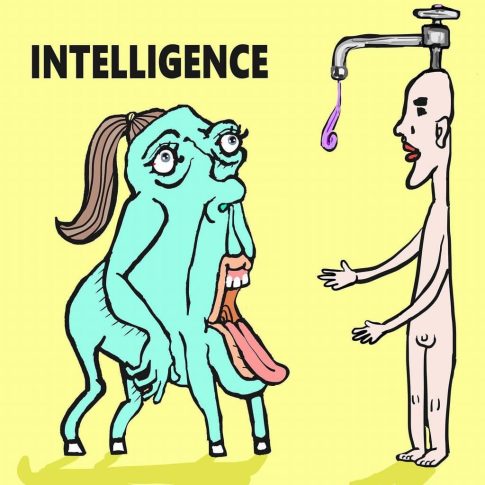





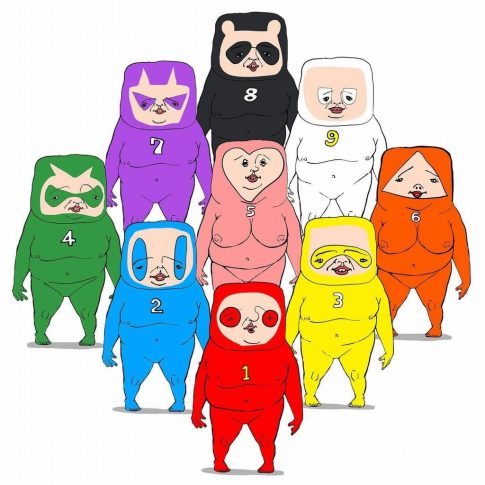










コメントを残す