背中には超大型のリュックを背負い、両手は10キロほどの大荷物でふさがれたわたしは、地面を一歩一歩踏みしめるようにゆっくりと歩いていた。
普段からトレーニング的な行為に馴染みのないわたしは、「きっと、こういう苦しいことを指すのだろう」と勝手に決め込んだ。なぜなら、今回はどうしても運ばなければならない荷物のためにこの苦行に耐えているが、そうじゃなければすぐさまギブアップだからだ。
ずしんと背骨にのしかかる大量の荷物は、体重に換算すればおよそ20キロも増えたことになる。太るってこういうことなのか・・・すべての重量を支える足の裏が悲鳴をあげており、体重が増えることの恐ろしさをひしひしと感じた。
ちなみに、右手のバッグには大量の汁物が入っている。しかも液体をジップロックに小分けにしてあるため、雑にあつかうとバッグもろとも大惨事となる。そのため、どうせ早歩きもできないのだから、汁物になるべく振動を与えないように、そろりそろりと歩を進めているわけだ。
・・そういえば、競走馬を運ぶトラックの運転手は、水を満たしたコップをドリンクホルダーに設置して、その水をこぼさずに運転する練習をすると聞いたことがある。この練習が今でも行われているのかはわからないし、あくまでも「たとえ」として語り継がれているだけかもしれない。だが、馬運車の運転手は急ブレーキを踏んではいけないのは事実。
レース前の大切な競走馬を、安全に運ぶことが馬運車に課せられた任務のため、間違っても競走馬に怪我をさせてはならない。そのため運転速度も法令順守となり、信号の特徴や道の構造によっては、一般車よりもかなりゆっくり走ることになるのだ。
かつて高速道路で馬運車を見かけたときのこと。調子に乗った下品なセダン車が、こともあろうか馬運車を煽りまくっている場面に出くわした。馬は繊細で敏感な動物ゆえに、後ろからガンガン煽られていることに気が付いているかもしれない。
こんなことで、レース前のナーバスな状態にストレスを与えるようなことがあってはならない――。
正義感の強いわたしは、下劣で危険な煽り運転を続ける車の後ろに張りついて、逆に煽り返してやった。誤解しないでももらいたいが、なにも好きでこんなことをしているわけではない、馬運車を煽ることを止めてほしい一心から、心を鬼にして無言のメッセージを送ったのだ。
そもそも輸送している対象物が何かを考えれば、いかに安全に運ぶ必要があるのか、小学生でもわかるだろう。ましてや馬体重500キロの体に対して、明らかに細い脚で体重を支えているわけで、運転が雑になったり無駄にブレーキを踏んだりすれば、馬の脚への負担は免れない。
そんな最悪の事態だけは回避しなければならないため、この下品で無知なセダン車の暴挙を、わたしが食い止めるしかないのだ。
こうして、激昂したセダン車はすぐさまわたしの後ろへピタリとくっついた。よし、これでいい――。
わたしは馬運車と一定の距離を保ちながら、競走馬と運転手、そして厩務員の安全を確保した。後ろからハイビームで煽り散らかすセダン車など、完全に無視である。わたしがここにいる限り、マツリダゴッホと国枝栄厩舎は絶対的に安全なのだから。
そんなことを思い出しながら、わたしは右手の汁物を揺らさないように、静かに足を動かした。
・・いや待てよ、これは馬運車に限った話ではない。イニシャルDという走り屋の漫画でも、とうふ店の息子が豆腐を運ぶ際に、コップに水を入れた状態で猛スピードで峠を攻めていたではないか。
いかに滑らかにドリフトできるか――。その英才教育の一つとして、コップの水をこぼさずに攻めるという方法を、主人公の父親は強制的に導入していたのだ。
わたしは前かがみになりながら、リュックの重さを背中全体で受け止めつつ、両手をだらんと下げて汁物への無駄な振動を排除した。
これは、ラーメンや蕎麦を運ぶバイクに設置された「出前機」の要領だ。腕や手首を固定することで発生する無駄な振動を、ぶら下げるように脱力することで吸収するのだ。いわゆる、人間エアサスペンションの原理である。
そんなことを考えるうちに、ようやく駅の灯りが見えてきた。――あぁ、助かった。わたしの腕も背中も、じつは限界を迎えていたのだ。








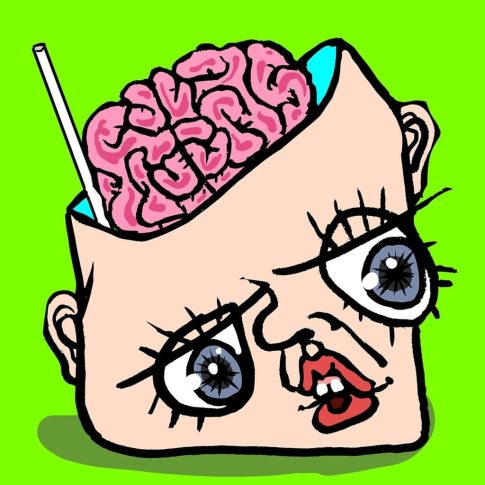

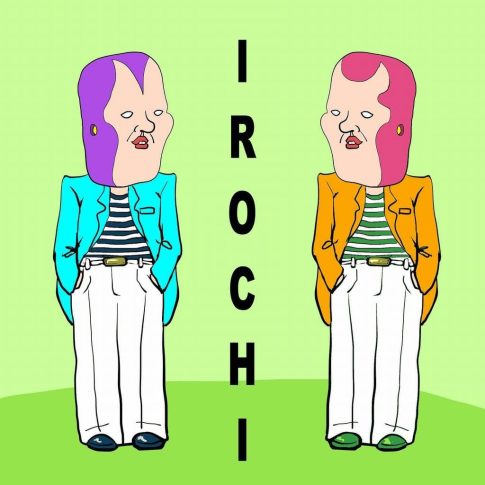










コメントを残す