――その日の夜。
那須に宿泊することとなったわたしは、「冬の東北の洗礼」を受けた。
一般的なホテルや旅館ならば、当然ながら寒さはしのげる。しのげるどころの話ではない、室内は半袖半ズボンで十分なほどに暖かい。
窓はペアガラスで外気から遮断され、小雪がちらつく外の寒さなど微塵も感じない。
備え付けのテレビからは賑やかな笑い声がこぼれ、他愛もない小さな幸せを感じるのであった。
・・・となるのが大方の予想だろう。
だがわたしは、とある事情からコンテナの中で朝を迎えることとなった。とはいえ「コンテナ」に問題はない。断熱材による内装が施されており、凍え死ぬようなことはないからだ。
さらに感動したのは、広々とした共有スペースに置かれた暖房器具だった。
それは、冬場の工場や体育館で活躍する「灯油式の業務用赤外線ヒーター」で、そこから放出される熱風は、ナイロン製のジャケットを溶かすほど強力だからである。
それにしても、人間とは単純な生き物だ。
氷点下に近い寒さの中で、ゴウゴウと音を立てながら燃え盛るヒーターの前に立った瞬間、「生きててよかった!」と、心の底から感謝するのだから造作ない。
普段は偉そうに威張り散らす輩であっても、あまりの気温の低さに命の危険を感じた途端、なりふり構わず暖を求める姿は滑稽といえる。
そのくらい人間は、カネと寒さにめっぽう弱く、暖かさと権力にひれ伏す習性を持っているのであった。
とにかく、「家庭での使用禁止」というシールがデカデカと貼られた業務用ヒーターの前で、わたしは風呂に入る準備をした。
風呂といっても、即席のシャワールームが設置されているだけだ。しかも敷地の端っこにあたるその場所は、吐く息が白くなるほど「ほぼ外」という環境であり、ヒーターの恩恵をまったく受けていない。
さらに、ただでさえ寒がりのわたしは、相当な覚悟を決めてからでなければ全裸にはなれない。
このようになんだかんだ言いながらも、自然との厳しい戦いに備え十分に体を温めたわたしは、シャワールームへとダッシュしたのであった。
「ボイラーが止まると思うから、そうなったらしばらくは水で我慢してね」
脱衣所で友人からこんな忠告を受けたが、「じゃあシャワーを浴びるのは止めよう」とはならないわけで、聞いても聞かなくても同じくらい絶望的な気持ちでシャワーのレバーを捻った。
(よし、温かいお湯が出た!)
幸いにも40度のお湯が出てきた。水勢も水量も不十分ではあるが、そこに不満を漏らしたところでなにも変わらない。
とにかく今は、わずかでも体を温めてくれるこのお湯に感謝を捧げよう。少しでも長い時間、わたしの体を温めてくれ――。
とはいえ、こちらも万が一に備えて対策を練っている。
たとえばシャワーが水になってしまったとき、それでも洗える部位はどこかを考えた。手先足先、そして顔と頭ならば水でもどうにかなる。もっと言うと、顔などその辺の水道で洗えるため後回しが効く。
ということは、お湯が出ている間に洗わなければならない部分を、優先的に攻めるべきなのだ。
大急ぎで全身にボディーソープを塗りたくると、体の中央から優先的に泡を流し始めた。首、肩、胸と調子よく流すうちに、いよいよお湯の温度が下がってきた。
はじめのうちは「気のせいだ」と言い聞かせ、明らかにぬるいお湯で膝上までを流したところで、タイムアップ。とうとう冷水が襲ってきた。
これはもう「気のせい」では誤魔化せないくらい、絶対的な水の温度である。那須の大自然からくみ上げられた新鮮な冷水で、わたしは膝下の石鹸を洗い流した。
(つ、冷たい・・・)
当たり前である。外気2度の寒空の下で、水のシャワーを浴びているのだから冷たいに決まっている。サウナで汗をかいたあとに浸かる水風呂とは、ワケが違うのだ。
腕には鳥肌がハッキリと確認できる。冷え切ったつま先は、青白く変色している。
それでも、髪の毛についたシャンプーをどうにかしなければ、シャワールームから出ることができない。
百歩譲って、その辺の水道で髪の毛をすすぐことも可能。だがそれならば、ここでちょっと腹をくくれば済む話である。
頭部を冷水で流せば、「頭を冷やす」という言葉通り、何かいいことがあるかもしれない。
さらには「頭寒足熱」というくらい、健康のためにも良いはず。
(そうだ、これは修行なのだ)
わたしは覚悟を決めた。ただでさえ寒がりの温室育ちかもしれないが、生きるか死ぬかの局面で怯むほど、落ちぶれてはいない。
今こそ野生動物を思い出せ。彼らには、人工的な暖房器具の用意などない。それでも寒い冬を乗り越えて、暖かな春を迎えているではないか。
彼らにできて、わたしにできないはずがない。足りないのは勇気だ。やってできないことなどないし、もしも低体温症で命を落としたとしても、悔いはない。
今できる最善を尽くしての「死」なのだから――。
土色の手でシャワーヘッドを握りしめると、スーッと息を吸い込んでから頭を下げた。そしてすかさず、後頭部へと水をぶっかけた。
もはや「冷たい」とか「寒い」などという感覚はない。滝行で煩悩を祓うかのごとく、一心不乱にシャンプーを洗い流した。少ない水量ではあるが、焦ることなく歯を食いしばり、丁寧にしっかりと水を浴びせ続けた。
なぜか穏やかな気持ちになるわたし。邪念は消え、純真無垢な自分がそこにいる。
そしていま、生きる喜びを感じている。
全身を鳥肌で覆われながらも、シャンプーという化学物質を洗浄することで、生き物としてまっさらな状態を手に入れることができたのだ。
――あぁ、何という幸せだろう!
とうとう、頭がおかしくなったのである。
(了)




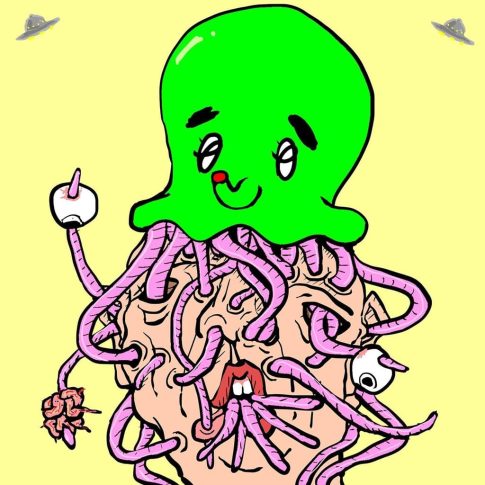




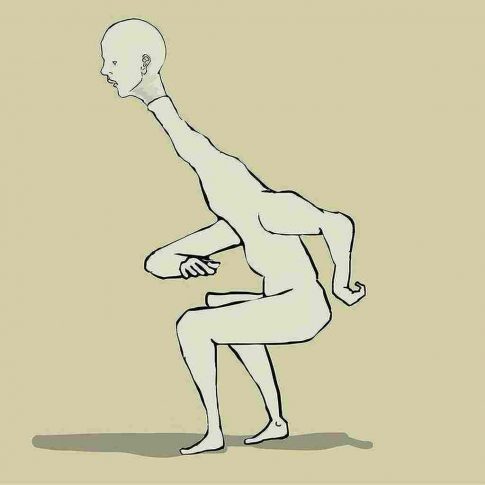











コメントを残す