高級料理店を訪れると、自然と背筋が伸びるもの。立ち居振る舞いも自ずと上品になり、知人の奢りにもかかわらず、自身が金持ちになったかのような錯覚に陥る。
おっと。「自然と背筋が伸びる」と言ったが、実際は腰痛のせいで前かがみの老婆であり、会食に同席した友人知人のみならず、店員からも哀れな目で見守られた。
(チキショウ。床がすーっと動けばいいのに)
そんなことを思いながら、長い廊下をノッシノッシと進むのであった。――なんだってこんな見世物みたいな役回りなんだ、チキショウ。
本日の会食は、品川にある「なだ万高輪プライム」で行われた。高級ホテルで有名な「ザ・プリンスさくらタワー東京」の3階に、ひっそり、かつ、荘厳な雰囲気の店舗を構えている。
「なだ万」といえば、高級日本料理店であることくらいの知識はあったが、その生い立ちなどはまったく知らなかった。
創業は1830年(天保元年)、192年の歴史を誇る老舗中の老舗である、なだ万。天保元年などという元号は、日本史の授業以来久々に聞いたが、その頃からの灯を絶やさず受け継いでいる姿に感動を覚える。
ちなみに「なだ万」という屋号は、創始者である「灘屋萬助」の名前に由来しているのだそう。長谷川賢がハセケン、深田恭子がフカキョンと呼ばれるようなものか。
そんな老舗料理店にお呼ばれした私は、新調したビーチサンダル(リカバリーサンダル)を履いて、上体を45度前傾させながら、目的地である個室へと向かった。
店員たちはもはや声も掛けてこない。私から漲る「話しかけるな」オーラに圧倒されたのだろう。
*
次々と運ばれてくる、手の込んだ緻密な料理に舌鼓を打つ。だがなぜか誰よりも早く平らげてしまう私は、そっと箸を置くと知人の話に耳を傾け相槌を打つことが多かった。
そうこうするうちに、また新しい料理が運ばれてくる。そして問題はここで起きた。
(あれ?この箸、どっちで食べ物つかんだっけ?)
高級料理店で出された箸は、祝箸(いわいばし)と呼ばれる両口箸だった。両端が細くなっており、中間部分がふっくらしている、アレだ。
縁起物とされるこの箸は「神人共食(しんじんきょうしょく)」の意味を持つ。一方の端を神が使い、もう一方を人間が使うことで、神の恩恵を授かることができるとされているのだ。
そんな両口箸を箸置きに置いた私は、果たしてどちら側で食べ物に触れたのか、分からなくなった。
高級料理というのは、えてして質素でこじんまりとしたものが多い。脂ぎっていたり、ゴテゴテの味付けだったりすることは、まずナイ。
そのため、そっと食材をつまんで口へと運ぶだけの仕事しかしていない箸は、その表面に汚れなど確認できない。なんなら私が箸ごときれいに舐めているため、話に花が咲こうものなら、次の料理が並ぶ頃にはきれいさっぱり乾いている。
(箸置きの左側に出ている部分が、箸の先っぽだろうか)
通常、箸置きの左側には箸の先端がくる。右利きが多い日本において、食べ物と箸の接触部分がテーブルやランチョンマットに触れないように、箸置きを使うからだ。
しかし左利きの私にとって、通常通りに設置された箸置きは逆となる。だが、わざわざ位置を変えるのも面倒だったため、そのままの状態で箸を置いたのだ。
そのため、本当に箸置きの左側に出ている部分が箸先かどうか、自信がないのだ。
(無意識に置けば、箸置きの左側は箸の頭となる)
何度かエアーで箸を置く動作を繰り返してみた。無意識の場合、左手でそのまま箸置きへ乗せるため、必然的に箸先が右を向いた状態となる。
だが箸先の意識が少しでもあれば、左手首をひねるようにして、箸先を箸置き側にして納めている。
仕方なく、両方の先端をくまなく観察し、どちらかに湿り気や着色がないかを確認する。しかし、両側とも新品同様の綺麗さである。
(うーん。今回は左側が箸の頭ということにして、次回から気をつけて置こう)
そう決めた私は、さっそく次の料理へと箸をのばした。
*
・・・そう。大方の予想通り、私は毎回このトリックに引っかかり続けたのだ。
まだ誰も蓋を開けていないお椀を、私が先陣を切って完食し、ふたたび蓋を戻して足並みを揃えるくらい、誰よりも早く食べ尽くしていた私。
そのおかげで、食事中の会話の中心は私だった。そして話に花が咲けば咲くほど、私は箸の天地を忘れることとなった。
こうして新たな料理が運ばれてくるたびに、「あれ?」と思いながら悩み自問自答し、その結果、毎回逆サイドを使ったのである。
最後のほうで鰻ご飯を食べた際、米のカピカピが箸先に付着しているのを発見したが、時すでに遅し。最後のデザートは、
「ライチの葛切り はちみつレモンのソース」
という上品な一品で、葛切り専用の箸が添えられていたからだ。
高級料理というのは、なにかと難しいものである。



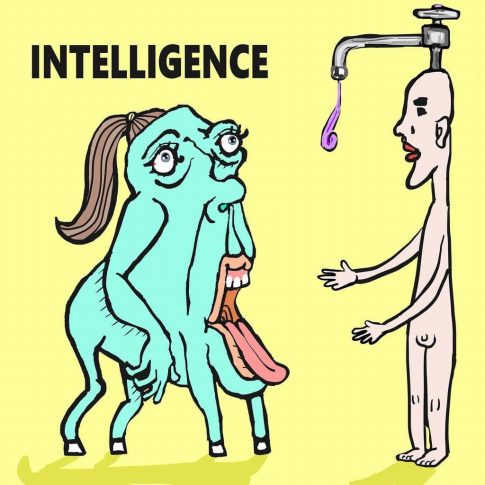


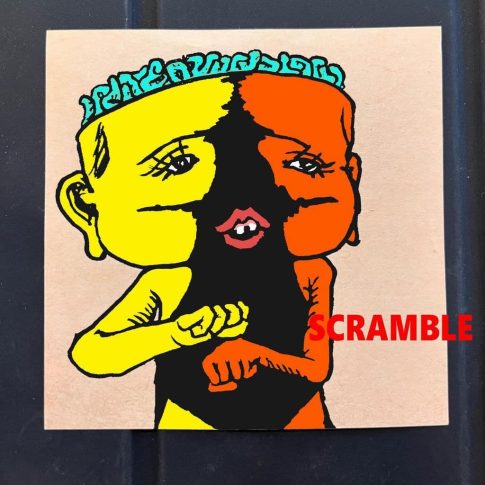














コメントを残す