「職業」を聞かれるのが嫌いだ。
理由は、そのイメージで話が進むから。
何かにカテゴライズされることがとにかくキライだ。
そんな私のメインの仕事は、社労士。
サブの仕事は、会社(アスリートのキャリアサポート)の社長。
そして、仕事というかお小遣いをもらってるのが、ライター。
私の中で仕事はドライなもの。
人と戯れることなく淡々とこなすもの。
イメージとしては、「終わらせるために進めるもの」という感じ。
その点、ライター業は異質。
とてもウェットで生きている感がある。
だからと言って、好きとか得意なわけではない。
ただ、私自身に影響を与えるのはこの仕事だ。
**
ある日、「職業社労士」の筆者は、ハローワークを訪れた。
筆者の自宅から割と近いこの場所は、言ってみれば「庭」みたいなもの。
その日の筆者(社労士)のファッションは、以下のとおり。
(上から順に)
・金髪
・クロムハーツのネックレス(ゴツイやつ)
・タンクトップ(DIESEL)
(腕ムキムキ)
・ダメージ加工のデニム(G-STAR)
・サンダル(ビルケンシュトック)
完璧な路上ファッションだ。
これぞまさに戦闘態勢。
そしてその日は、助成金のちょっとした確認をしたかっただけなので、手ぶらで訪れた。
いまどき財布など不要だ。
ケータイ一つで電車もバスもタクシーも乗れる。コンビニもイケる。
つまりケータイ一つで、本当に手ぶらで、ハローワークを訪れた。
助成金と外国人関係の窓口のある階で、順番待ちのチケットを引いて待っていた。
しかし、待てど暮らせど順番が来ない。時期が時期(コロナ)だけに、助成金窓口は大繁盛。「4時間半待ち」と、フザケタ貼り紙がされていた。
(仕方ない、一つ聞きたいだけだから、知り合いの職員でも探すか)
筆者は社労士である。
社労士たるもの、ハローワークに知り合いの職員くらいいるものだ。
今こそ、社労士としての威厳を誇示しようではないか。
キョロキョロしながら、カウンター内の職員らの顔を見渡した。
すると、
「お客さん、ここから先は入らないで」
ガードマンにつまみ出された。
(チッ)
往生際の悪い筆者は、つまみ出されながらも職員の顔を見回した。
すると、最後に一人の女性職員と目が合った。
知らない顔だが、彼女は筆者のほうへ向かってくる。
(ナイス!援軍確保!)
部屋の外までつまみ出されたとき、その女性職員が追いついた。
彼女は笑顔でこう言った。
「ごめんなさいね、わかりにくい案内表示で。
お客さまは多分、1つ下の階ですね。
ご案内しますね」
(え?そうなの?
社労士専用窓口とかあったんだ・・・)
親切な彼女は、下の階へつながる階段まで案内してくれた。
「この階段を下りて、右に曲がると窓口がありますよ」
「そうなんだ、ありがとう」
筆者は優越感に浸りながら、何時間も待たされ、疲労と絶望でいっぱいの、哀れな小市民を脇目に、颯爽と階段を下った。
(えっと、下りたら右・・・と)
ものすごい数の人間がいる。
年齢も、老若男女と呼ぶに相応しいラインナップ。
そして、目の前に広がる、壮大な窓口。
窓口の案内表示には、デカデカと
「失業の認定」
・・・そうか。
筆者は「失業者」だと思われたのだ。
まさか、ハローワークの職員ですら「先生!」と呼ぶ立派な社労士だとも知らず、外見で判断したところ、コイツは立派な失業者に違いない、ということか。
「本日認定日ですか?」
忙しいのにまた新たな失業者来たよ、と言わんばかりの乾いた笑顔で、職員が声をかけてきた。
筆者は、無視をした。
もしこれが、スーツやワンピースで、革のバッグにヒール、メガネをかけて金のバッジでも付けていれば、間違いなく、
「先生!先生は上の階でございます!」
と言われるんだろう。
それが、よりによって失業者。
小さくため息をつき、なんとなく周りを見渡してみた。
みんな、死んだ魚の目をしてる(失礼な)。
耳にペンを差してるオッサンもいる(競輪場か)。
無活気が集まりすぎて、逆に活気づいてる、変な集団だ。
そしてふと思った。
上の階よりこっちの階ほうが、なんていうか、自然だ。
自然体でいられる。
*
筆者は、「先生」などと呼ばれる社労士にはなりたくない。
失業者と間違われるほうが、性に合ってる。
思い返せば、過去にも幾度となく似たような経験をしている。
「ここは社労士の窓口だから、あっちへ行きなさい(いや、私社労士だし)」
「社労士の浦辺先生ー、浦辺先生ー(目の前にいますが)」
「(ZOOMで)あとは、社労士さんだけですね(いや、既にいる)」
「書類の書き方、わかるかな?見本あげようか?(何十回も書いてるわい)
**
以上、とりあえず仕事においては見た目は大事だぞ、という実体験から来る教訓でした。



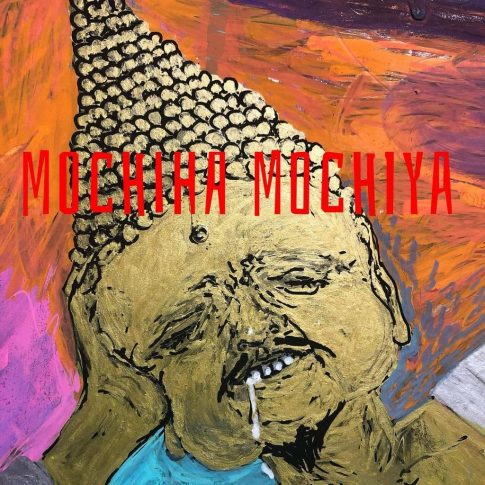


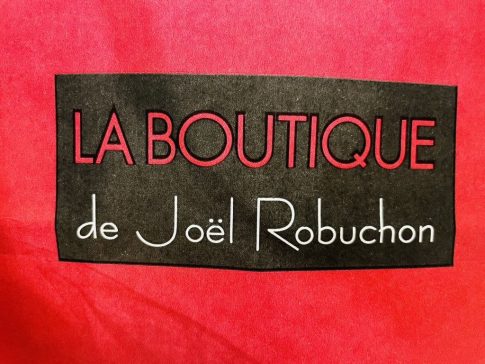














コメントを残す