昨日、友人から”ゾウの餌”と揶揄されるようなディナーを堪能したわたしは、ふと思ったことがある。「いつだったか、祭りで食べたじゃがバターは美味かったな」・・と。
今でこそ縁日や祭りのようなイベントの数は減り、的屋による屋台を見る機会も少なくなった。的屋といえば、たこ焼きやお好み焼き、かき氷、チョコバナナといった食べ物から、金魚すくいやスーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、わなげといったチャレンジ系の遊びまで、子どものみならず大人も楽しめる空間を演出してくれる露天商のこと。無論、支払う金額の対価として商品の値段が釣り合っていないことなど承知の上。あくまで、イベントを盛り上げるための”演出”として、的屋が出す屋台に価値があるわけで。
だが時代の流れだろうか。最近のイベントにおける屋台というのは、赤い看板に「たこ焼き」などと黒字で書かれた”昔懐かしの屋台セット”ではなく、いわゆるキッチンカーによる出店が増えた。
昔懐かしの屋台セットでも、ガスボンベと簡易キッチンを設置することで調理はできるが、キッチンカーならば屋台がそのまま移動するので設営の手間が省ける。おまけに、車載用冷蔵庫のような小型冷蔵庫も内蔵できるため、食材の鮮度を落とすことなく移動と調理が可能なのだ。
加えて、シンクや水道といった水回りも付帯しており、石鹸とアルコール消毒の設置まで義務付けられているため、昔懐かしの屋台よりも衛生面ではかなり安全性が高いといえる。
とはいえ、祭りや縁日といった伝統的なイベントに足を運んだ際に、あの赤い屋台セットを見るとホッとするのは日本人ならではの感覚だろうか。不衛生でぼったくられているとわかっていても、ついつい財布から現金を取り出してしまうのが、昔懐かしの屋台が持つチカラなのだろう。
そんな屋台で「じゃがバター」を買ったことがある。ホクホクのジャガイモに、客が好きなだけ塩とバター(多分マーガリン)を塗りたくってもいい・・という魅力的なサービスがウリで、バター好きのわたしは”ここぞ”とばかりにバター(多分マーガリン)をジャガイモ以上のサイズですくいとったものだ。
ちなみにじゃがバターは、ジャガイモが持つ自然の甘さとバターが織りなす滑らかなハーモニーがポイントではあるが、それよりも重要なのが「塩」の存在である。ジャガイモとバターだけでは味にパンチが足りないため、大量に食べるのは難しい。ところが、そこへ塩を少々振りかけることでジャガイモが引き締まりバターの存在感が際立った結果、いくらでも口へ運べるようになる。
この事実を思い出したわたしは、自宅のキッチンへと向かった。たしかウチには塩があったはず——。料理で使うわけではないが、誰かからもらった塩の存在を思い出したわたしは、引っ越し以来初となる「シンク下の空間」を物色し始めた。もう何年・・いや、十年から十五年は経過しているであろう塩の存在を、わたしは今日まで覚えていたのだ。
(・・あった!!)
すると見事に、瓶に入った塩を発見した。すでに開封済みで半分くらいが固まってはいるが、それでも強くシェイクすると塩がパラパラになったのでまだ使えるはず。そこでわたしは、改めて12個のジャガイモを購入すると、レンジで15分加熱して昨夜と同じ状態まで仕上げた。
(ここまでくると、もはや料理上手と言っても問題ないな)
そしていよいよ塩を使う瞬間を迎えた。だが、そもそも塩というものをどのくらい振ったらいいのかが分からない。まれに飲食店で塩を使う機会はあるが、たとえば天ぷらに塩を振るとかゆでたまごに塩をつけるとか、その程度の小さな範囲での塩使いのため、12個のジャガイモにどのくらいの塩をかけたらいいのかが分からないのだ。
とりあえずは適当に何回か振りかけてみるも、ジャガイモの表面に付着した塩はそのうち透明になって消えていった——もう少しかけたほうがいいかな。
下のほうのジャガイモにも満遍なく塩が行き渡るように、耐熱ボウルを上下左右に揺さぶりながら、さらに塩を振りかけては馴染ませる——全体的に回っただろうか。念のためもう少し振っておくか。
こうして完成した塩味ジャガイモ12個、いざ実食!!
(・・・しょっぱい!!)
見た目では全く分からないが、とんでもない塩味をまとったジャガイモはとてもじゃないが食べられなかった。やむをえず水道水で洗いながら塩を落とつつ、それでも無味の状態よりは美味いジャガイモをかじるわたし。
そしてこう思った——やはり料理というのは、高度な技術と経験が必要な難易度の高い行為なのである——と。
*
余談だが、シンク下から発掘した塩は、「海の精やきしお」という名の伊豆大島産の天然塩。原材料名「海水」という潔い記載が、商品の質とプライドを物語っている。
ちなみに、ラベルにロットナンバーの印字があったので、製造元のホームページから生産に関する詳細を検索してみることにした。そこでは海水採取日、天日濃縮日、釜揚げ日、焼成日、包装日といったロットごとの詳細が確認できるのだ。
「検索結果ありませんでした」
(・・・・・)
まぁ、塩に賞味期限はないとのことなので、「いつ作られたのか」などどうでもいい情報である。味も美味いしちゃんとしょっぱいし、なんら問題はないわけで。
それでも、この「検索不可の塩」がいつ頃の海水から作られたものなのか、興味津々であることは間違いないのである。
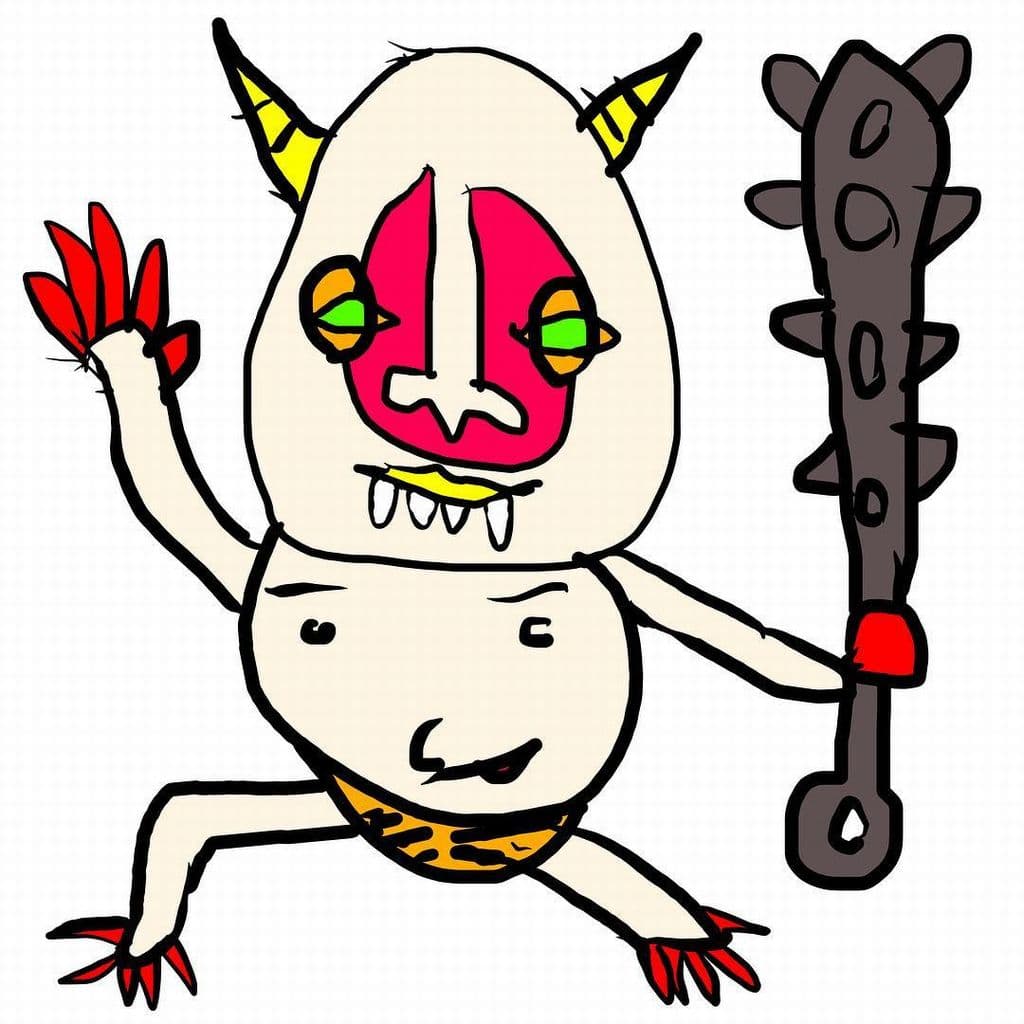

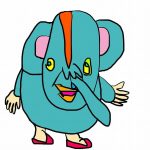
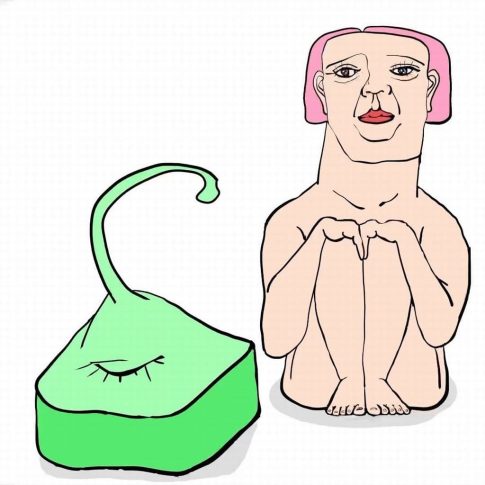

















コメントを残す