人間が野生から離れて長い年月が経つ。それゆえ、野生で生きていた頃の記憶もなければ、遺伝子的にも当時の情報などほぼ残っていないだろう。
よく「嗅覚はもっとも原始的な感覚である」などというが、それでも所詮、夕飯の匂いをかいで子どもの頃を思い出す程度。
このように、野生から退いてずいぶん経つ人間は、もはや危機察知能力など備わっていないに等しい。
そんな現状に危機感を抱くわたしは、街中を歩くときは常に全方向へ注意を向けている。
目に見える範囲だけでなく、たとえばあのマンホール。突如蓋が弾け飛び、中からヒトが出てくるかもしれない。それどころか、マンホールが超高温に加熱されており、踏んだとたんにサンダルが溶けて足まで大火傷を負うかもしれない。
むしろ蓋を踏んだら堕ちるかもしれないわけで、マンホールだからと安心してはならないのだ。
おっと、今度は目の前から酔っ払いがやってくる。
いや、待てよ。あれは酔っぱらっているかのように演じているが、実は暗殺者の可能性がないともいえない。上手に千鳥足を演じ、よれよれの服装をしているが、それだけで「単なる酔っ払い」だと侮るなかれ。
よく見れば、右手に電子タバコのようなものを挟んでいる。あれが本当に電子タバコかどうかは見た目だけではわからない。もしかすると、ワンプッシュで鋭利な刃物が現れる武器かもしれないし、ハンディータイプのスタンガンかもしれない。
そして我々の認識として「酔っ払いはフラフラしている」「酔っ払いはおかしな目つきをしている」「酔っ払いは急に変な方向へ踏み出したりする」という行動特性がある。
つまり、多少変な動きをしたとて怪しくないのが酔っ払い。そんなステルス性を、酔っ払いという人種は手に入れているのだ。
わたしは全身全霊でその男をロックオンした。
さすがにわたしを狙って殺傷事件を起こそうとは思っていないだろう。だが油断は禁物。無差別殺人を目論んでいるかもしれないし、人間を傷つけて狼狽する姿が見たいのかもしれない。
とにかく犯人の考えなど知りようもないのだから、こちらは十分警戒し、もしもの事態に備える以外に方法はないのである。
柔術を習っているからといって、刃物相手に身を守れるほど鋼鉄な皮膚は持ち合わせていない。道着でも着ていれば話は別だが、真夏のこの時期に裸同然の格好で歩くわたしの衣服が、刃物の侵入を防ぐとは到底考えられない。
となれば、敵からのファーストアタックを堂々と受け入れる覚悟が必要。
痛みもあるし出血もするだろう。だがそこで犯人の腕を掴めれば、その先の攻撃を防ぐことができる。ましてやこちらもそれなりの覚悟ができているわけで、注射を打たれる際にグッと身構えるのと同じ要領で待ち構えればいい。
あんな小さな、電子タバコほどの刃物であればなおのこと、痛みなど大したことはない。仮にあれがスタンガンだとしても、ここは繁華街ゆえにキャッチを含めた大勢の人間がうじゃうじゃ蠢いている。
よって、わたしに初手で攻撃を加えようとも、致命傷まで負わせることは難しいはず。
(よし、覚悟は決まった)
このまま奴とすれ違えば、あの電子タバコはわたしの右腹部から大腿部あたりに接触する。
そして、すれ違いざまに斬られる分には傷も浅いわけで、もしも直前で勢いをつけて突っ込んできたら、前蹴りで距離を取ろう。
股間めがけて思いっきり、かかとをぶち込んでやろう!
気分が高揚してきた。心拍数も軽く上昇している。そして何より、成功する画しかイメージが湧かないのだ。
さぁ来い!どこからでもかかって来い!
*
酔っ払いのフリをした殺人犯と思しき中年は、右手に挟んだ電子タバコもそのままに、フラフラとわたしの横を通り過ぎて行った。
きっとわたしの殺気に気づいたのだろう。この女はダメだ、そう感じたのだろう。
男が通り去ってからも、背後からの奇襲攻撃に備えて身構えていたわたし。だが、情けなく丸まった背中を見送っただけで、事件が起きることはなかった。
何も起きなくてよかったのだ。それでも若干の消化不良を感じているわたし。振り上げたこぶしの行き場に困るとは、正にこのことか。
そんな思いを胸に、鼻息も荒いまま繁華街へと歩を進めた。
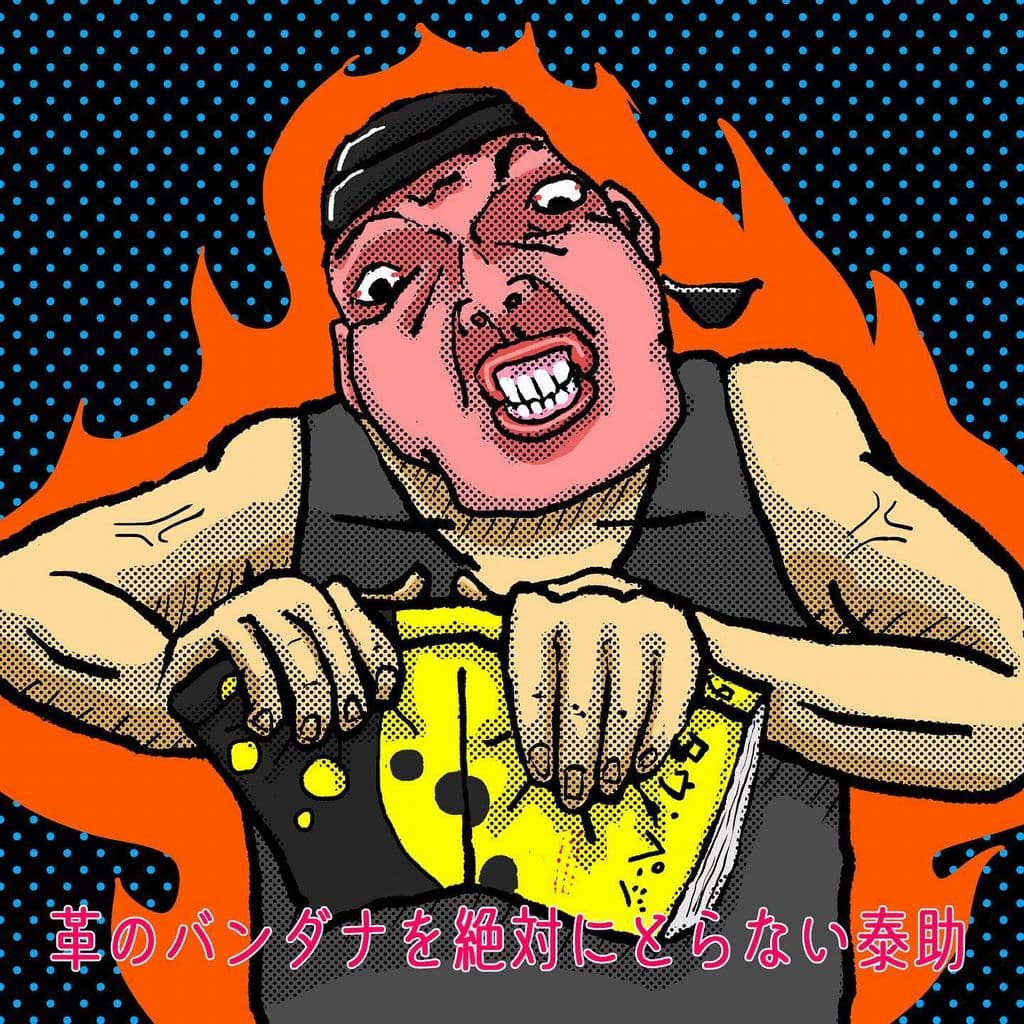









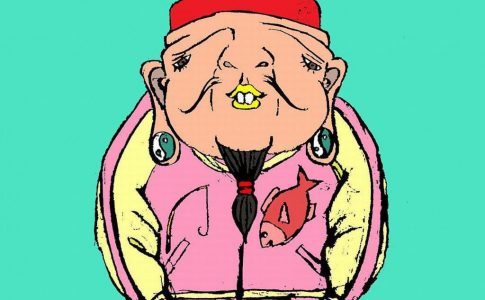










コメントを残す