わたしは「花より団子」を地で行く人間であるため、薔薇の花束をもらうよりおむすびをもらうほうが嬉しいわけだ。
ゆえに、わたしに求婚を考えている殿方は、豪華な花束よりも選りすぐりの食い物引っさげて跪(ひざまず)くことを推奨する。
そんなわたしが、珍しく花束をもらう機会に恵まれた。
(イケメンからもらう花束というのも、悪くはないな・・)
そんなことを思いながらも、受け取った花束の処理に頭を悩ませた。なんせわが家には、花瓶というものは存在しない。それどころか、花瓶の代わりになるコップがほぼ存在しないのだ。
いつ誰にもらったのかは覚えていないが、Baccarat(バカラ)のワイングラスならばある。だが、あんなペリカンのような細い脚に花を入れたら、手を離した途端にグラスは倒れて粉々になるだろう。
かといって、毎日使っている容量473ミリリットルのマグカップは、これになみなみとコーヒーを注いで飲むことでわたしの一日が始まるわけで、花を挿してしまったら一日が始まらない。——ほかに何かないかな。
水を入れることができて、しかも自立させられる容器といえば、やはりペットボトルだろう。しかも偶然、いい感じのペットボトルが転がっているではないか。
(いやいや、これじゃ失礼すぎる)
というわけで、大学時代の思い出といえば雀荘でのアルバイトしかないわたしの学び舎である、ナンバーワン(雀荘の名前)の解散記念湯飲みを使うことにした。
湯飲みなど使うことがないのでしまっておいた・・というのが本音だが、それでも、わたしの青春がつまった大切な記念品なわけで、どうせならここ一番で下ろそうと思っていた。そしてまさに今が、ここ一番だろう。
・・というわけで、花の鮮度を保つための薬を湯飲みに注ぐと、溢れるほどの水道水を入れてやった。そこへ、もらった花束を投入——おぉ、立派な生け花じゃないか。
こうして、わが家史上初の「生花」との同居を始めて数日が経った。
湯のみに挿した花束は、長さがあるため単独では立っていられない。そのため、壁にもたれかかる必要があることから、居場所はキッチンを与えられた。
わが家のキッチンといえば、それはもうピカピカの美しさが自慢の"未使用キッチン"である。油汚れ一つない、まるで鏡のように澄み切ったステンレスに囲まれて、湯飲みに挿した生花たちが凛として佇んでいる。
(これぞ侘び寂びってやつだ)
とはいえ先にも述べた通り、食い物にしか目がないわたしは、花を見ても心奪われるほど感動することはない。
もちろん、誰かにプレゼントするならば美しい花や珍しい種類を選ぶが、自分自身のために花を買う習慣がないため、「あぁ、花だな」と思う程度で終わってしまうのである。
そして今日も、いつも通りチラッと花の様子を視認しつつ玄関へと向かおうとしたところ、わたしは思わず足を止めた。いや、止めざるをえなかった。
(・・な、なんだ、このいい匂いは)
わが家には、何種類かの天然アロマオイルが常備されている。その日の気分によってそれらを使い分けており、当然、新鮮ないい匂いが漂っているのである。
おまけに、その辺の量販店で購入できるようなオイルではなく、専門店で量り売りしている、いわゆる高級品なのだ。よって、このオイルを超えるほどのいい匂いなど、そうそう出会えるものではない。
それなのになんなんだ、このいい匂いを上回るいい匂いは——。
生花の前まで戻ったわたしは、改めて花の匂いを嗅いだ。それは言葉では言い表しがたい、天然モノにしか放つことのできない立体感のある香りだった。
これは、好みの匂いとかそういうレベルではなく、天然か人工かの違いである。しかもそこには、人工的には作り出すことのできない、天然が持つ圧倒的な香りの幅があった。
目をつぶって嗅いでも、決して間違うことのない香り——それこそが、天然か人工かの差だろう。そしてわが家の生花から、ホンモノの証である天然の香りが放たれていたのである。
(・・花をもらうのも、悪くはないな)
*
花びらがしょんぼりしている理由が、水がなくなったからだとも知らずに、わたしは満足げに家を後にしたのであった。




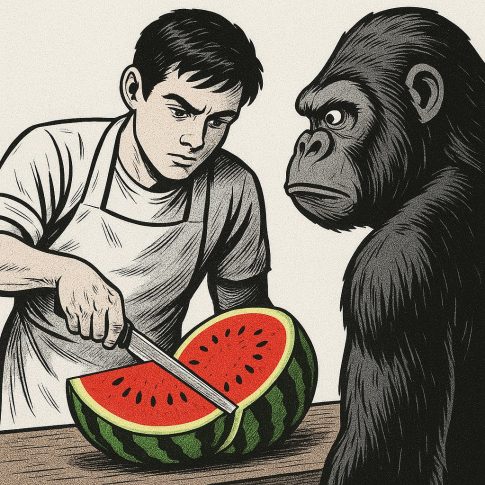
















コメントを残す