(言葉が存在しない・・というより、文化的な概念なのかな)
とある会話を聞いていて思ったことがある。何かに挑戦する者に対して、われわれ日本人が使う言葉として有名なのは「がんばれ!」だが、この一言に込められた想いの温度差はものすごく広い。
場の流れでなんとなく応援しなければならない・・というところで使う「がんばってね」も、血の滲むような努力を間近で見てきた者が使う「がんばってね」も、口にすれば同じ単語ではあるが、意味合いが異なるといっても過言ではないくらいの温度差がある。
このような場面に遭遇した際にいつも思うことだが、「もっと別の言葉で伝えられたらいいのに・・」と、便利で独特な言語である日本語が持つ、簡潔ゆえに語彙力が乏しくなる現象に”もどかしさ”を感じるのであった。
たとえば英語で「がんばって」を言い表そうとすると、真っ先に思い浮かぶのは「Good luck!」だろう。直訳すれば「幸運を祈る!」だが、日本人からすると「ちょっと投げやりで、こちらの気持ちが伝わりきらない」と感じる表現かもしれない。おまけに、「祈る」という言葉は”神を信じる文化圏”ならではの感覚でもあり、馴染みが薄い可能性もある。
さらに「Do your best!」もよく使われる表現である。「あなたのベストを尽くして!」という意味だが、こちらのほうが日本語でいう「がんばって」に近いかもしれない。とはいえ、勝負事であれば本人の実力のみならず「運」も影響してくることから、前出の「Good luck!」のほうが万能といえばその通りか——。
ほかにも「Keep it up!」や「Keep going!」のように、すでに努力を重ねた者に対して「その調子で続けて!」という意味合いでkeepを使うこともあるし、「Don’t give up!」「Hang in there!」などと、あきらめかけた挑戦者に対して「なんとか踏ん張れ!」と応援する場合もある。
また、「Take it easy!」ならば「無理せずに気楽に!」になるし、「Go for it!」と言えば「やってみよう!」と背中を押すイメージが加わる、というように、日本語では「がんばれ」という一言で済んでしまう・・いや、それしか相応しい言葉が存在しないわけだが、英語ならばシチュエーションに合わせていくつかの選択肢があるため、応援する側もされる側も言葉に込められた意味や想いを正確に受け取ることができるのだ。
だからこそ、「がんばれ」に込められた魔力は、時には挑戦者に過度なプレッシャーを与え精神的に追い込んでしまうのである。これもまた、ハイコンテクスト文化の特徴といえる「表情や雰囲気、共有の価値観といった言葉以外の要素」に、頼りすぎた末の結果なのかもしれない。
そういえば「いただきます」という言葉も、英語には存在しない。だからこそ、日頃から「いただきます」と一言を発して食べ物に手をつける習慣がある日本人にとって、何も言わずにいきなり食べ始めるのは、少なからず違和感を覚えるもの。
とはいえ、さすがに「神に感謝を伝えてから」というような、宗教的な慣習のある家庭で食事をする機会もほとんどないので、とりあえずテーブルに並べられた料理を褒めたり喜んだりしながら食べ始めるわけだが。
しかしながら、「いただきます」についても仏教由来説がある。だが、どちらかというと”食材を育ててくれた農家”や”料理を作ってくれた人”への感謝、さらには”自然の恵み”や”命をいただくこと”への感謝を込めて、「いただきます」という言葉を使っているので、宗教的な感覚は現代の日本人には皆無だろう。
というわけで、ハイコンテクスト文化においては「空気を読む」という行為が言葉に付随するため、人間関係が希薄になりがちな現代においては、ただ単に「言葉足らず」という残念な結果に陥りがちなのだ。
そしてなによりも、「がんばれ」と言われた当人は自分の物差しで「がんばれ」の熱量を測るわけで、他人と比べてがんばったかどうかなど知る由もないし比べようもない。であれば、「行ってらっしゃい!」くらいのほうがフィットするのではなかろうか——。
そういえば、試合前に「ご武運を!」というメッセージをもらうことがあるが、これもまた「素敵な言葉だな」と思ったりする。やるだけのことはやったんだから、あとは運に任せるのみ・・という、一見投げやりに聞こえるが当事者らが登場しない応援の仕方は、陰湿な残痕を刻まないスマートな応援といえるからだ。
・・などとあれこれ述べてきたが、われわれの常套句である「がんばれ」は便利である反面、使い方が難しい言葉であるということを、ふと思ったのであった。
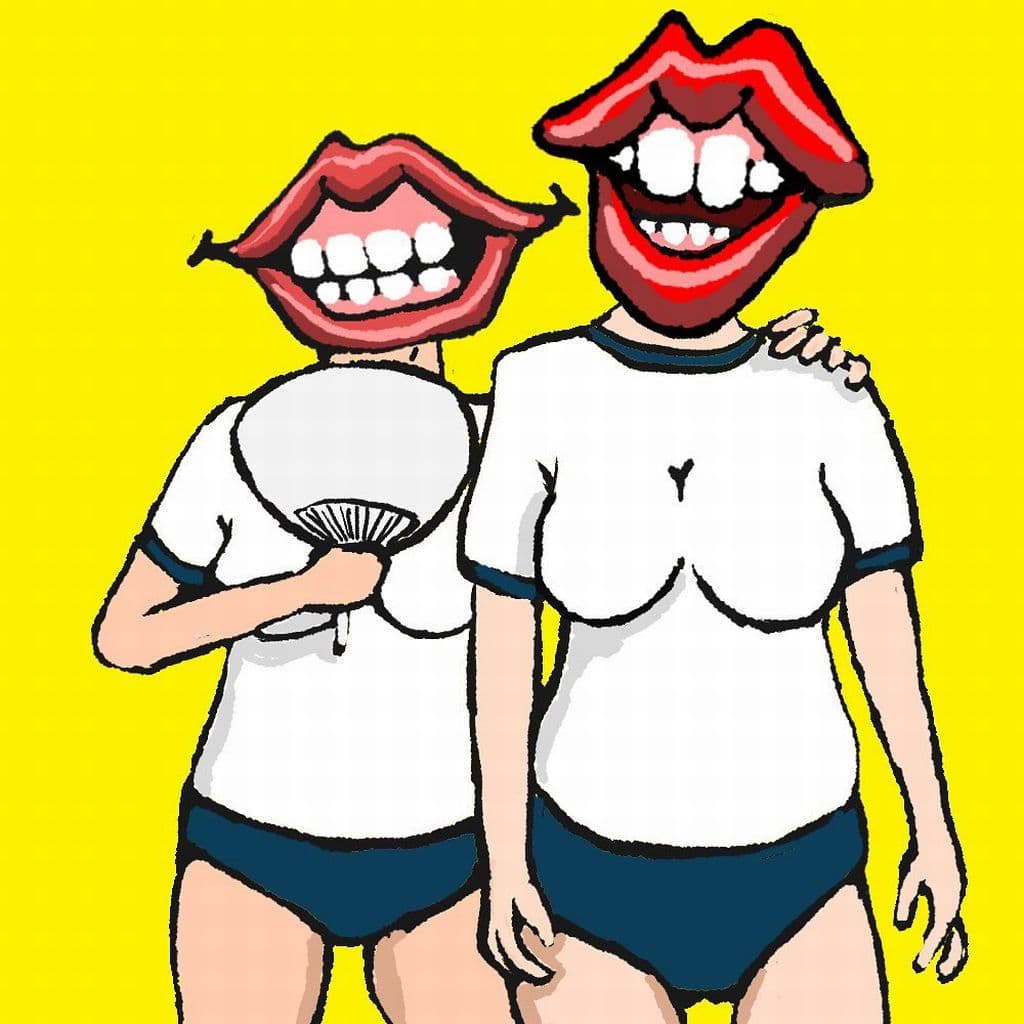







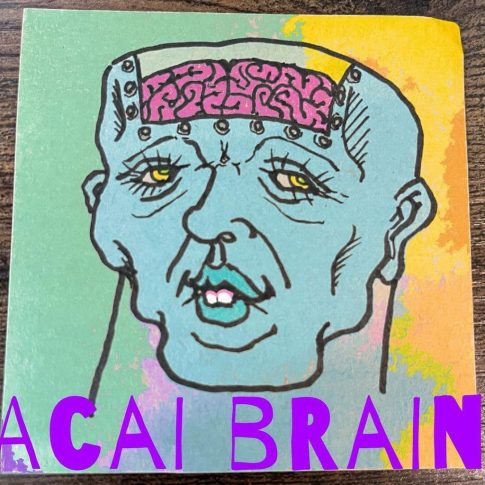












コメントを残す