(今すぐここを出なければ遅刻する・・・)
時というのは無情にも過ぎていくわけで、こちらの都合などお構いなし。せめて、心の準備ができるまでの僅かな間、一秒という単位をもう少し長く刻んでもらいたいと願うのだが、そんな虫のいい話が通用するはずもない。
なかでも、誰もが経験するであろう"恐怖のウインター・モーニング"という、クソ忙しい朝なのにどうしても布団から出られない現象は、時の残酷さを如実に示すいい例である。
そんなわけで、冬というのは時が無情であることを体感させられる"ナチュラル拷問シーズン"であるのは周知の事実。しかしながら、11月の後半はまだ極寒とまではいかず、朝晩の冷え込みはおよそ冬だが、日中の穏やかな日差しは冬の一歩手前といったところ。
そして、本日の最高気温である17度の時点で家を出たわたしは、夜の恐怖を忘れて適当なジャケットを羽織っていた。なんせ都会は軒伝いでどこへでも行けるし、電車やタクシーを利用すれば外気に触れることなく移動できるし、そこまでガチンコの防寒着は必要ない・・と甘く見積もっていたからだ。
まぁ、そんな安易で愚かな考えは、数時間後には木端微塵に砕かれたわけだが——。
(いやいや、寒すぎるだろう・・・)
時刻は午後6時過ぎ。外が寒いのは当たり前だが、カフェ店内で震えなければならないのは納得がいかない。言うまでもなく、ジャケットは着たままである。
ちなみに、店内にもかかわらず寒い理由は、わたしの席が店舗入口の真横だったからだ。そりゃ当然、外気に触れる機会が多いのだから寒いに決まっている。おまけに、次から次へと客が出入りするため、入り口の自動ドアはほぼ開きっぱなしの状態で、店内といってももはや屋外のような寒さが出来上がっていた。
そこそこ厚手のトレーナーにジャケットを羽織ったわたしは、"まるで季節外れな格好"とまではいかないし、むしろもっと薄着の者も散見するわけで、そこまで非難されるいわれはない。だが一つ、重要なことを忘れていた・・それは、わたしが"極度の寒がり"ということだった。
(寒がりだと分かっているのに、なぜダウンや冬用ジャケットを選ばなかったんだ・・)
——いつだってそう。後悔するのは冷え切ってガクブル震え始めてから。こうなることは予め想像できたはずなのに、何度同じ目に遭ってもなぜか懲りずに薄着で家を出るわたしは、真性のバカなのだろう。
そして今、すぐにカフェを出なければ次の予定に遅刻する・・というところまできているにもかかわらず、外の寒さにビビり散らかしているわたしは、未だに腰を上げることができずにいた。
いつかは店を出なければならないのだから、だったら今すぐ立ち上がるべきだ・・と頭では理解しているが、体がそれを強く拒否しているのだ。そりゃそうだ、外は店内よりも確実に寒い上に、隠れたり暖をとったりすることも不可能となる。となれば、以前までは「場所の移動」という行為が、今日は「拷問」と化すわけで。
そんな不毛な自問自答を繰り返すうちに、とうとう遅刻が確定する時刻となってしまった。——あぁ、時は考える余地すら与えないだなんて、なんと惨たらしい概念なんだ。せめて、心の準備が整うまでの数分・・いや数十分くらい、時を止めてはくれまいか。
(いや、ダメだ!こんなことを繰り返していたら、マジで大遅刻する)
心を鬼にしつつ理性を総動員させたわたしは、泣きそうな気持を抑えて席を立った。そして一目散に走り始めたのである。
わたしは走ることが嫌いなため、滅多なことではダッシュはしない。もしも「電車に間に合わない」となったら"あきらめる"を選択するほど、走るのが嫌いなわけで。
だが今日は違う。無論、遅刻を恐れているわけではない。では、なぜ全力疾走したのかというと——そう、寒いからだ。これ以上の防寒対策が不可能ならば、自家発電で熱を発生させる以外に方法はないため、嫌だのなんだの言っている場合ではないのだ。
身体の芯から冷え切ったわたしは、頭も心も「無」の状態で走った。もはや刺すような冷気すら感じないほどに、皮膚上にある温度受容体は麻痺していた。それでも、走ることで体を温める以外に生命を維持する手段はないのだから、これは命懸けの行為なのだ。
走れ、URABE——。
*
とはいえ、一分も走ればなんとなく体は温まるので、そうなったらすぐにスピードダウンして歩くわけだが。



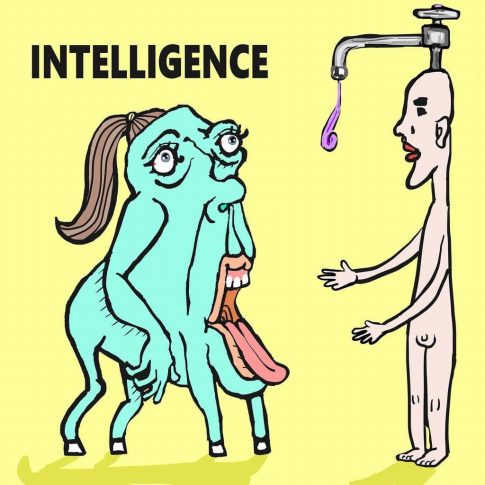



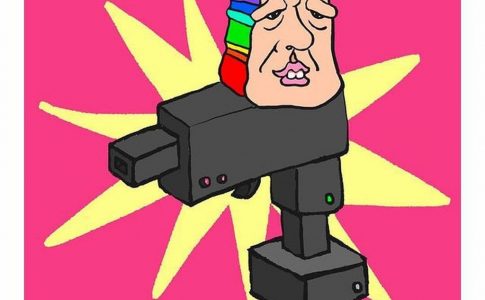













コメントを残す