わたしは、帰宅するとすぐに手に提げていた紙袋から、大きなタッパーを取り出しフタを開けた。——中身はビーフシチュー。しかも友人お手製の美味そうなやつだ。
手作り料理というのは、そのワード自体が明らかに食欲増進のスパイスとなっている。どこぞのブランド店やら行列のできる有名店やら、そんなところの料理に興味はない。わたしはただ、百円ショップのタッパーに詰められた、作り立てでもなければ温かくもない手料理にこそ、最高の美味さと圧倒的な贅沢を感じるのである。
「ちゃんと温めて食べてね」
と、言われたかどうかは覚えていないが、たいていの場合、作り手はベストな状態で味わってもらいたいことから、電子レンジなどで加熱してもらいたいと願うもの。
対する受け手側も、作り手の心意気を汲み取り、ベストな状態を再現してから味わうのがマナーである。いくら面倒くさがりで料理嫌いなわたしであっても、そのルールは守ろうと決めている。それこそが作り手への感謝であり礼儀であるからだ。
とはいうものの、一先ず味を確認してから友人へ礼を述べるのが筋だろう。そもそもわたしは、出来立てホヤホヤよりも冷めた弁当のほうが好きなのだ。その"最高に美味い状態ではない状態"にこそ、手料理の醍醐味が光るからだ。
そこでわたしは、そっとフタを開けると真っ先に目についた肉の塊をすく上げた。ゴロっと大きな牛肉は、煮たか焼いたか、はたまた叩いたか揉んだかは分からないが、何らかの下処理が施されてある。元から美味い肉という可能性もあるが、肉自体の味というよりはシチューに馴染む風味を醸し出しているからだ。
・・そういえば友人が、
「カットしてある肉だから、煮崩れしてホロホロにならないか心配」
などと、わたしには不要のエクスキューズを入れていたが、そんな心配はどこ吹く風。しっかりとした噛み応えと脂身のトロトロ加減は、それだけでも絶妙なハーモニーを奏でる上等な料理だった。
さて、肉の次は野菜だ。とりあえずニンジンをすくうと、カプッと噛みついた。・・おぉ、ニンジンの甘みと歯ごたえが、お口直しにちょうどいい。
作り手いわく「本当は明日食べてもらいたかった」とのこと。シチューというのは作り立てよりも、一晩寝かせたほうが味が染みて旨味が増すのだそう。とはいえ、野菜の青臭さというのも捨てたもんじゃない。世間に染まる前の若人が持つ、勢いとプライドのような眩しさが生野菜にはあるからだ。
そして、ニンジンの次には玉ねぎが待ち伏せていた。玉ねぎは加熱によりその姿を消す習性があるが、今回はしっかりと顔を拝むことができた。
・・こうして、ニンジンと玉ネギにより、口内にはびこる動物性たんぱく質を拭い去ったわたしは、肉の塊と同等の、いや、それよりも大きな"とある塊"をすくいあげた。
その名はジャガイモ。友人は、わたしがイモ好きであることを知っていたため、わざわざ大きなジャガイモを入れてくれたのだ。しかも煮崩れを防ぐべく、メークインを選んだとのこと。
わたしからすれば、肉もジャガイモも形を失おうが溶けて消えようが、シチューと一体化するのだから文句はない。だが作り手からすると、相手が口にするその瞬間まで、最低限の形状維持を望むのだろう。・・これだから、手料理ってやつは贅沢なんだ。
ゴロンと存在感のあるジャガイモだが、芯まで火が通っていて柔らかい。無論、ジャガイモの味もするが、シチューのルーと絡むことで一段と上品な味わいを生み出している。
硬さ加減といい形状といい咀嚼感といい、完全無欠のジャガイモといっても過言ではないほど、文句のつけどころのないメークインを食べ終えると、わたしは再び肉へと戻った。
・・二巡目の肉というのは、最初の一口とはまったく異なる意味を持つ。最初の肉はいわば小手調べだが、野菜をはさんでからの肉は、まさに真骨頂といえる。
もはや「初めての感動」という特効薬は使えないわけで、ここからが味の真剣勝負となるからだ。
(これはやはり、温めてから第二ラウンドに突入するべきか・・)
わたしは迷った。だが、その迷いに対する決断を下す前に、わたしの手は無意識に肉へと伸びていた。
あれほどレンジで温めろと忠告されたにもかかわらず、あれほど作り手への誠意を示すためにも"加熱してから食す"と誓ったにもかかわらず、ここへきて本能が暴走したのだ。
(ダメだ、温めてから食べなければ・・・!!!)
遠のく意識の片隅で、わたしは理性を奮い起こした。だがちっぽけな理性ごときが、狂い咲く本能を上回ることはできなかった。
・・そう。気付いた時にビーフシチューは、一滴たりとも残っていなかったのである。
*
「え、温めなかったの?!・・・迂闊だった」
スマホの向こうで、頭を抱える友人の姿が想像できるのであった。
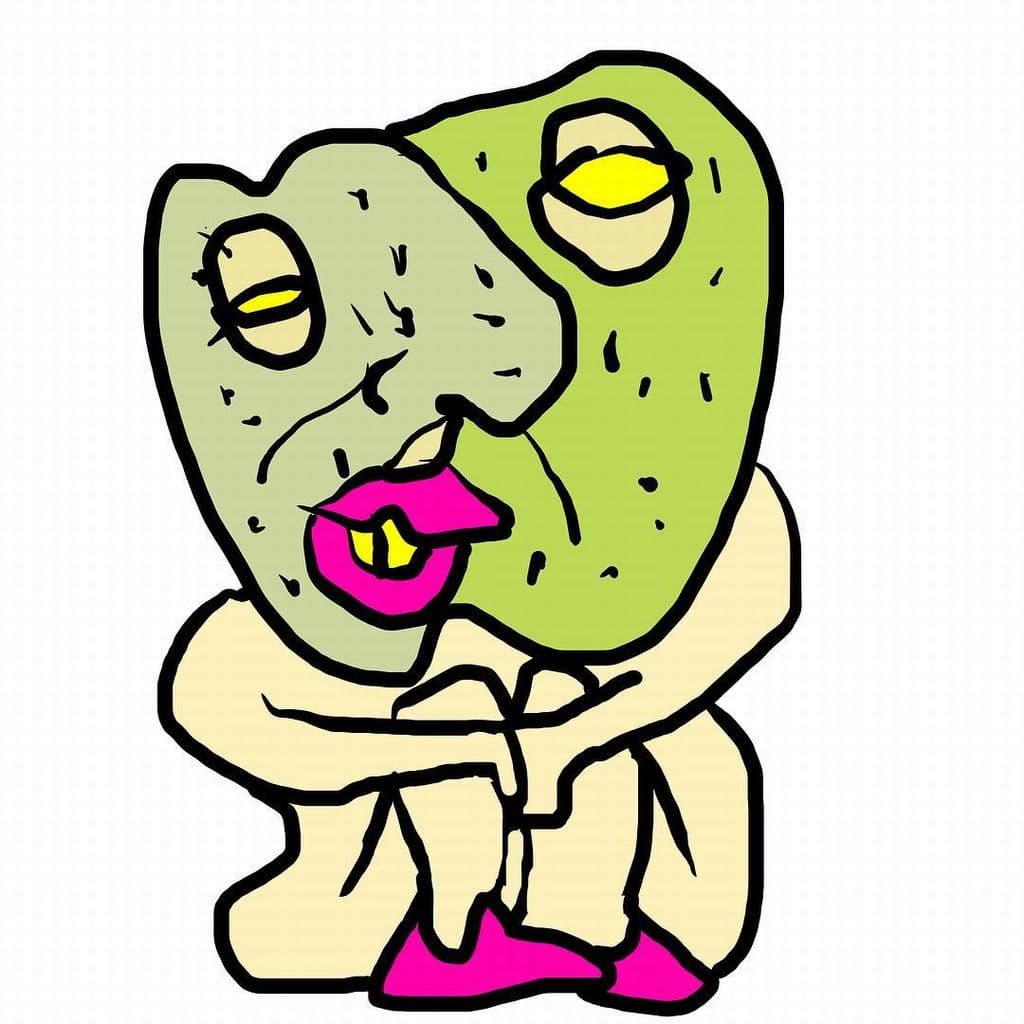




















コメントを残す