マジか、なにも変わってなかったんだ——ー。
Netflixで世界中に独占配信されている「THE DAYS」というドラマを見て(この件は、作品内には出てこないが)、思わずこぼれた感想だった。これは、12年前に日本を襲った東日本大震災で、未曽有の大事故となった「福島第一原発内の数日間」を描いたドラマである。
ちなみに、なにが「なにも変わってなかった」のかというと、燃料デブリと呼ばれるメルトダウンによって溶け落ちて固まった核燃料の処理が、12年たっても未だに何一つ行われていなかったことだ。
無論、燃料デブリを取り出して保管するまでに、解決しなければならない問題は山積みだった。よって、それらを一つずつクリアしての「今」であることは承知している。だが、およそ880トンもの燃料デブリがまったくの手つかず状態である上に、早ければ年内に「数グラム程度」を試験的に採取すると聞いて、かなりのショックと驚きを隠せなかった。
——なぜ、このような重要なことが報道されないのだろうか。まるで過去の出来事であるかのように、福島原発は何事もなかったかのように触れられない存在となっている。もうすでに安全は確保できており、なんの問題もないかのように。
*
ちなみに、この作品は記録動画やノンフィクションではないので、脚本家が書いたシナリオを俳優が演じているのだが、どれだけの聞き取り調査やインタビューを重ねたのかが分かるくらいに、役者の言葉や表情から伝わる「恐怖」と「覚悟」が圧倒的に違うと感じた。これは紛れもなく、事実だろう——。
特にどのあたりが刺さったのかというと、「現場の闇(暗さ)のリアル」だった。
よくよく考えてみると、福島第一原発が津波に襲われすべての電源を喪失したのは、夕方から夜にかけての出来事だった。ということは外は真っ暗のはず。加えて「全電源喪失」しているのだから、原子炉も中央制御室も当然、真っ暗なのだ。
よく、専門家を名乗る人々が
「1号機の水素爆発は、もっと早くベント(格納容器内の圧力を下げる操作)を行っていれば防げたはずだ!」
との考えを述べるが、それは確かにその通りかもしれない。だが、電源喪失により計器類は作動しておらず、手持ちの線量計のビープ音が高濃度の放射線を知らせる暗闇で、誰が普段通りに作業へ取り掛かれるだろうか。
加えて、状況把握が不十分な状態で指示を出すことなどできないわけで、想像以上に対応が遅れる、あるいは判断を間違える可能性があったのだ。
真っ暗闇のなか懐中電灯を頼りに進む所員を、何回も地震が襲う。いつ原子炉が暴走するのかも分からない状況で、仮にそうなったら命などないわけで、それでも自分たちがやらなければ福島が、いや、日本が危ないとなれば、もはややるしかないわけで。
この心境はどこか「戦地へ赴く兵士」に似ている気がする。お国のために、命を賭けて戦うことは素晴らしいことだ。残された家族たちもきっと、喜んでくれるだろう——。
彼らは「誰かがやらなければならない、ならば自分が」と、恐怖を振り切って前へ進んだのだろう。現実的にも、引き返すことなどできない状況に追いやられたら、人間誰しもが観念するのかもしれない。
福島第一の所員たちも、自動車通勤者の車からバッテリーをかき集めて、原子炉の圧力容器内の水蒸気を逃す「弁」を解放するための手段に使ってしまったため、逃げ出したくても車はもう動かなかったのだ。人間の足で全力疾走したところで(とはいえ、地面は瓦礫まみれで走ることなど到底できない)、爆発の威力に勝るはずもない。となれば、今ここでどうにかする以外に、生きる道は残されていないのだ。
これほど明確に「死」を突きつけられることが、現代を生きていてあるのだろうか。しかも相手は敵国の人間ではない。言葉も意思も通じない、原子炉という巨大なバケモノ。
福島第一の敷地内は、津波の影響で瓦礫やガラス、金属片がいたるところに散在していた。つまり、自衛隊や消防が近づくことのできない空間となっていたのだ。瓦礫をどかさなければ先へは進めない。作業途中でタイヤがパンクしたり燃料がなくなったりと、予想をはるかに超える苦難が隊員の行く手を阻む。
そして、しつこいようだがこれらの作業を暗闇で行ったのだ。電源喪失した屋内も夜の闇に包まれた屋外も、いずれも真っ暗闇なのだ。さらに、右も左も分からないほど滅茶苦茶になった現場で、高線量下の被ばくリスクを抱えながら、誰がテンポよく作業に取り組むことができようか。
*
福島第一原発事故について、教訓とすべき反省点は多々あるだろう。だが、あの時あの瞬間の一つ一つの判断について、あーだこーだ言える人間などいるはずがない。
明るい照明と暖かい(当時は3月)室内、かつ、被ばくの恐れもない安全な場所で、「安全性」について議論をしている人間に、現場の覚悟など知る由もない。そう、絶対に分からない。
内部被ばくを防ぐために、身体の表面に着いた放射性物質をシャワーで洗い流すのだが、電源喪失によりお湯が出ない。まだ冬の寒さが残る3月の福島で、冷たい水を全身に浴びながら必死に除染する所員のことを、わたしたちは考えたことがあるだろうか。
いつだって、直接的な犠牲を被るのは現場の人間である。命を賭ける覚悟は、お偉いさんなんかよりも下っ端のほうがよっぽど強く持っている。
偉い人は逃げる、あるいは逃がされるが、下っ端は現実から逃げることを許されない。だからこそ、どんなに理不尽であったとしても、記憶に残る充実した人生が送れるのは現場の人間だと、わたしは信じている。
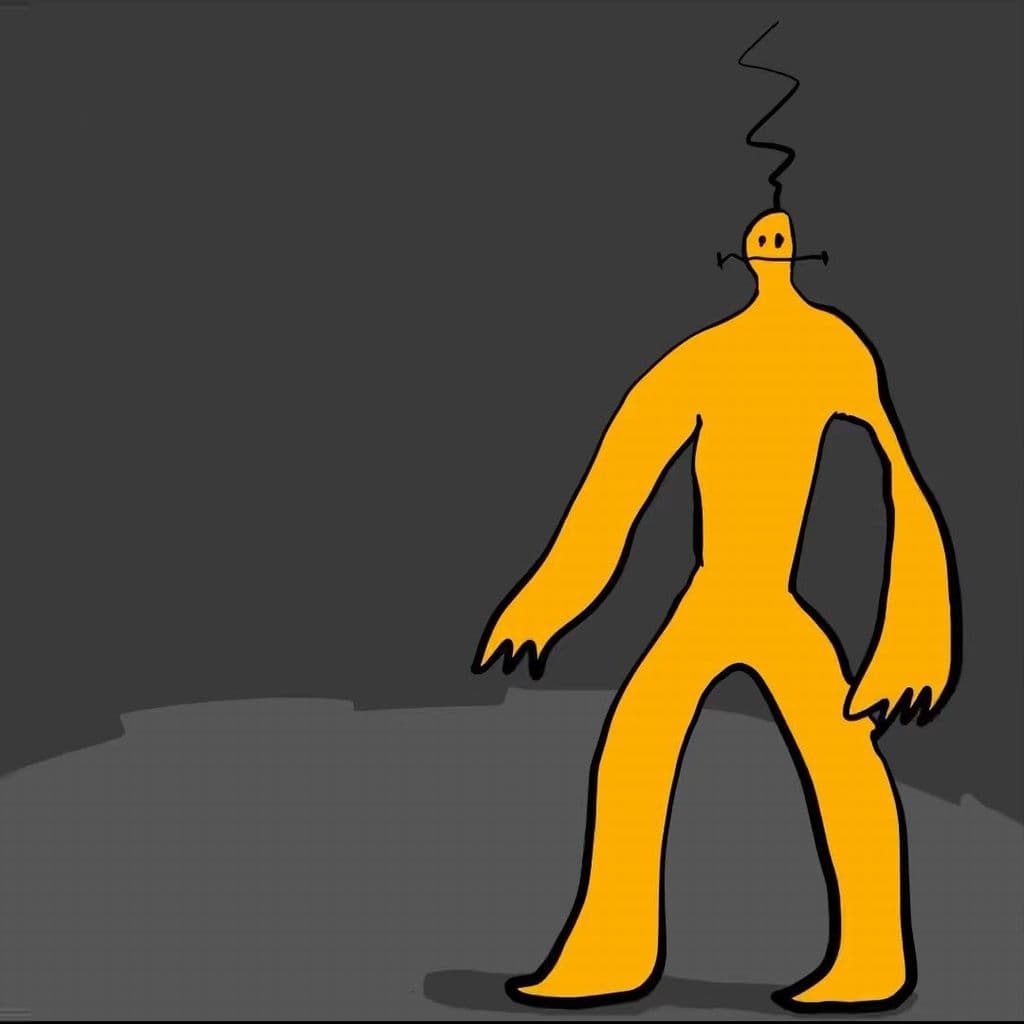









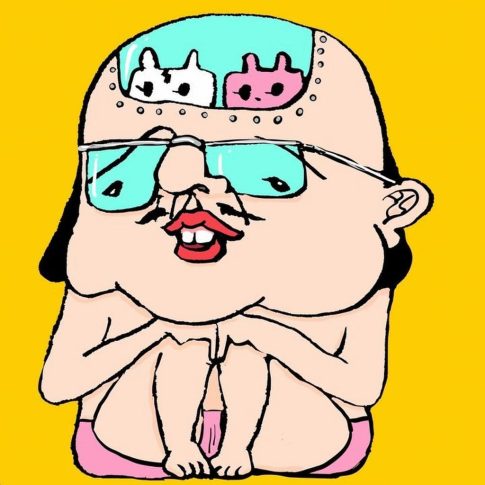










コメントを残す