わたしは今日、自分ではコントロールできないほどの憎悪と怒りがこみ上げるのを感じた。そして発狂寸前で、なんとかその禍々しい感情を捨て去ることに成功した。
というか、実際に着ていた服を脱ぎ捨てるのと同時に、感情も体外へ放出した・・・というのが正確な状況だが。
*
わたしには、体重をコントロールするために続けている運動がある。その名は「ブラジリアン柔術」だ。柔道とレスリングを足して2で割ったような動きの競技で、キッズからシニアまで何歳からでも、そして何歳まででも楽しむことができる、まさに生涯スポーツの代表格といえる。
ちなみに柔術は、「道衣」というユニフォーム、というか、柔道の道着に似た衣服を着用して競技を行う。そして試合に出る際には、道衣に関する細かなルールをクリアしなければならないので、わたしは試合用と普段の練習着は分けている。
しかし、「たまには試合用の道衣を着るのも悪くないだろう」ということで、今日は久しぶりに一張羅で練習に臨んだのだ。
事件はそこで起きた。
前からそうだったのか、もしくはわたしの脚が太くなったのかは分からないが、道衣のパンツがパツパツで、しゃがむことすら困難だった。例えるならば、全体重を乗せて太ももを押さえつける「正座」はできる。だが、「体育座り」をすると後ろへコロンと転がってしまうのだ。
脚を自力で曲げようとすると、どう頑張っても90度が精一杯。自分の手で脚をつかんで引き寄せようとしても、道衣に一ミリも余りがないため、ツルツル滑って埒が明かない。
その結果、わたしの下半身の自由は奪われた。というか、ウエスト部分がケツの途中で止まっているじゃないか!
なぜこのようなことになっているのかというと、太もものあたりでパンツが詰まっているのが原因。どんなに引き上げようが、どれだけジャンプしようが、股上が定位置に収まることはない。いうなれば「サルエルパンツ」のような形になっているのだ。オシャレのオの字もかすらない、パツパツのサルエルパンツだ。
そのため、パンツの股の部分とわたしのリアルな股との間に、決して近づくことのない「空間」が存在しており、その空間がなんとも不快で仕方がないのだ。
それにしても、どうしてこの空間に気を取られているのか、自分でも分からない。でもなぜか、気にしないようにしても無意識にその空間へと気持ち向いてしまうのだ。
(バ、バミューダトライアングル・・・)
そんな感じの、恐ろしい三角形がわたしの股には存在する——。
動くたびに太ももの肉が道衣のパンツに食い込んで、破れんばかりにテンションがかかっている。それと同時に、生地が四方八方に伸びているのが目視で確認できる。これでは、ケツの割れ目(パンツの)が裂けるのも時間の問題だろう。
パンツのせいで動きを制限されていることが、わたしのメンタルをも締め付ける。苦しい、過呼吸になりそうだ——。太ももやケツ周りがキツイだけなのに、なぜか心肺機能にまで影響が出ている。
(なんなんだ、このモヤモヤした不穏な気持ちは?おまけにイライラが収まらない・・)
必死に現実逃避を試みるが、現実的に固く拘束されている下半身のせいで気持ちのコントロールができない。気を紛らわそうとすればするほど、ギュッと締め付けるパンツにばかり意識が向いてしまい、そうこうするうちに、心の奥底からどす黒い禍々しい感情が込み上げてきた。
まるで貧血で倒れる直前のようだ。いや、貧血で倒れるときは意識が薄くなりパタッといくが、これはその逆だ。脳から血が引くのと正反対で、脳へ血が上る感覚だ。血かどうかも分からない、黒くて硬くて細かくてドロドロした泡のようなものが、うじゃうじゃとわき上がってくるのだ。
(もう駄目だ、我慢の限界だ・・・)
更衣室へ飛び込むと同時に、わたしは道衣を脱ぎ捨てた。どうやってパンツを脱いだのか記憶にないが、無我夢中で腰ひもをほどくと、そのまま足首までズザッと下ろして蹴り飛ばした。
冗談ではなく、もうあと数秒遅ければ、わたしは気が狂っていただろう。
*
今まさにリュックを閉じようとしているマルちゃんを見つけると、わたしは滑り込むようにそれを阻止した。
「この道衣、あげるから持って帰りなよ!」
まだ新しい道衣ゆえに、着られるヒトに譲るのが筋。彼女のリュックからきれいに畳まれた道衣を勝手に取り出すと、クルクルと丸め直して強引に詰め込んだ。そして少しだけできたスペースに、わたしの汗でぐっしょり湿ったA0サイズの道衣を、無理やり押し込んでやった。
迷惑そうな、いや、嬉しそうな表情で、パンパンに膨らんだリュックを背負ってマルちゃんは道場を去った。そしてわたしは、ほぼ空っぽのリュックを背負って駅へと向かった。
こうして、リュックも心も軽くなったわたしは、いい気分で帰宅したのである。









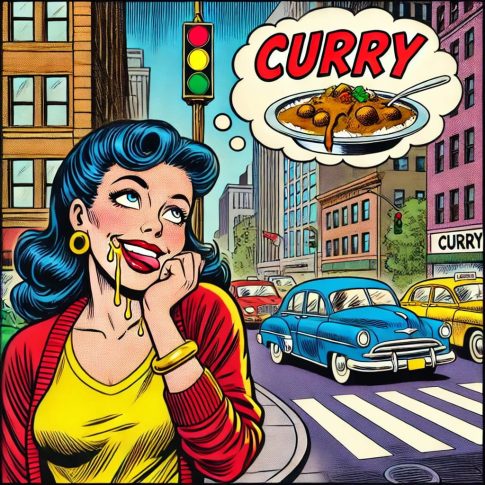











コメントを残す