「僕がこんなこと言うのもあれですが、3年前より上手くなりましたよ」
衝撃的なセリフが飛んできた。発言者は小学生の男子である。
こんな子どもから、上から目線で「上手くなった」などと言われ、プライドが傷ついた!…という話ではない。その男の子が、3年前のわたしを覚えていてくれたことに、感動を超えて衝撃を受けたのだ。
男子の名前はタクヤ君(仮名)。彼はブラジリアン柔術を習っており、たまに一緒に練習をする程度の仲だ。
しかし、年も離れていれば同じジムのメンバーでもないので、仲がいいわけではない。さらに相手は子どもゆえに、こちらから挨拶をしたり適当な会話を投げてみたりと、当たり障りのない距離感で接してきた。そしてもちろん、わたしは彼の名前を知らない。
柔道着や運動着のように、自分の名前がデカデカと記されたウェアでも着ていれば別だが、柔術衣には名前を縫い付ける習慣はないため、相手の名前を覚えるのに苦労する。
とくにわたしは、脳に障害があるため他人の名前を覚えることが苦手なのだ。自分のなかでは、相手に勝手にニックネームをつけることで、辛うじて相手を認知することができる。だが、興味の持てない相手のことはニックネームすらもつけないため、二度目の対面で「初めまして」などと口を滑らせた結果、微妙な空気になることも多い。
だからこそ、他人とはあまり親しくなりたくない。なぜなら、声をかけ合う仲になれば必然的に、相手の名前を覚えなければならないからだ。
たとえば「先生」「先輩」「社長」など、名前を呼ばなくとも相手を特定できる代名詞があればまだいい。しかし、同列の人間ばかりの場合、確実に相手の名前を憶えておかなければ、コミュニケーションに支障が出る。
しかも、この世の人々は比較的頭がいいのだろう。わたしは相手を忘れているにもかかわらず、相手がわたしを憶えている確率が非常に高いのだ。
そのため、向こうから名指しで声を掛けられた時、「あ、あぁ!ひさしぶり!」などと会話に便乗するのはいいが、相手の名前を呼ばなければならない時に困ってしまう――。そんな場合、会話をしながらさりげなくSNSを検索する、という緊急対処法が役に立つ。
だが迷惑なことに、インスタグラムではアカウントをニックネームで登録していたり、ローマ字、ひらがな、名前だけなど中途半端な登録だったりで、本名にたどり着けないことがある。そのため、最後まで相手の名前が分からないまま会話が終わる経験も数知れず。
「あー、アタシのこと覚えてないかな、●●だよ!」
勘の鋭い相手ならば、わたしがアワアワしているのを見破り、率先して自己紹介をしてくれたりもする。そんな時は、
「そ、そんなことわかってるよー!名前を忘れるわけないじゃーん」
と、白々しくも堂々と嘘をつくわけだが。
――話をタクヤ君に戻そう。タクヤ君いわく、3年ほど前に参加した柔術のセミナーで、わたしと一緒になったのだそう。しかもどうやらペアを組んで受講していたようで、集合写真でも隣に写っているとのこと。
そんなタクヤ君は、当時のわたしの存在を覚えているだけでなく、名前までしっかりと呼んでくれたのだ。まだ小学生の子どもだというのに、なんと殊勝なことだろうか。
さらに、わたしの柔術が下手くそだったことまで鮮明に記憶しているようで、恥ずかしいやら嬉しいやら、言葉にし難い感情が込み上げてくる。かつ、「あの頃より、今のほうが上手くなったよ」と褒めてもらうだなんて、身に余る光栄である。
にもかかわらず、わたしはタクヤ君の存在を忘れていただけでなく、今の今まで名前すら知らなかったのだ。オトナであるわたしが、小学生のタクヤ君に劣る記憶力とコミュニケーション力だったという恥ずかしさは、筆舌に尽くしがたい。
よし、これからはタクヤ君のことを「タクヤ先輩」と呼ぶことにしよう。少なくとも、相手の名前を把握し、3年前の行動を正確に記憶している時点で、わたしは完全に負けている。むしろわたしは、使い物にならないオトナのクズである。
人間の優劣に年齢は関係ない。年上を敬わなければならない理由は、老いていく人間の尊厳を保つために、せめて敬うことで手を打とうじゃないか、という若者の気遣いだからだ。
タクヤ先輩は、きっと立派なオトナになるだろう。なんせ、小学生の時点で反面教師となるオトナと出会えたのだから。
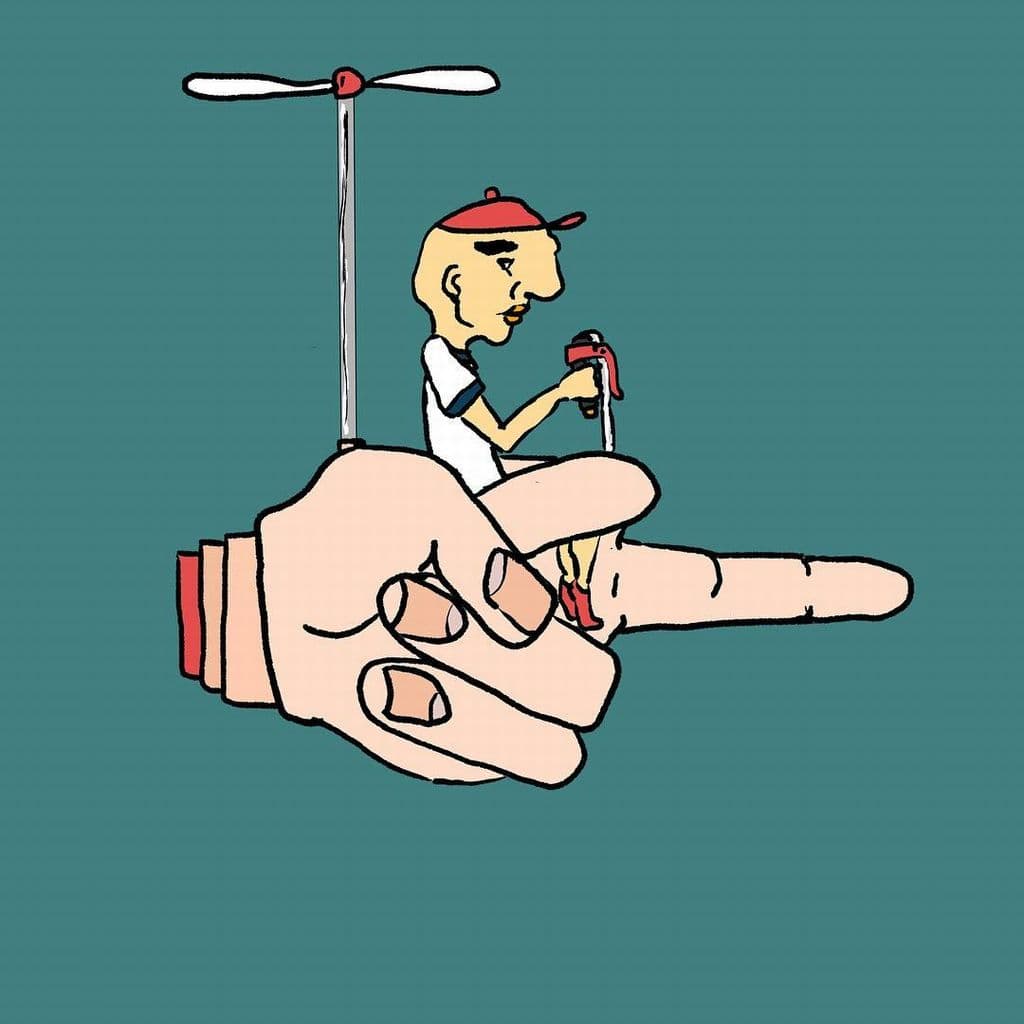




















コメントを残す