人間は自分の死期を前もって知ることはできない。よって、一分後には死んでいる可能性も十分ある。天変地異など予測できたところで防ぎようもなく、そうなったら運を天に任せるしかない。
そのくらい、人の命など短くて儚いものなのだ。
そして私は今、自分の死期が近いことを感じている。これは第六感とでもいうのだろうか。もはや、そうなるしかない状況に追い込まれたというのが、正しい表現かもしれない。
だからこそこうして、遺書というか死ぬ間際の出来事を克明に綴っているのだ。
昨日は「たまたまかな」という程度で過ごしたが、今日になって「これはたまたまなんかじゃない!」と強く感じるようになった。
そんな私のここ二日間を振り返ってみよう。
*
まずは昨日の朝、友人が美味しいパンをたくさん買ってきてくれたことに始まる。そのパンは、過去に私から頼んでおいたものなので、突然の出来事ではない。
だが、まさか日曜の朝に手渡されるとは思っておらず、突然の嬉しい収穫となった。
そして大量のパンに小躍りする私は、なんと別の友人から手作りのおにぎりをもらったのだ。それは鯖缶と細かいニンジンが入った炊き込みご飯で、鯖の脂が米のパサつきをおさえ、まろやかな口当たりを演出している。
鯖缶などあえて好んで食べない私だが、このおにぎりなら20個くらいは平らげる自信がある、といえるほど美味かった。
偶然とはいえ、美味い食べ物を二人の友人から前触れなくもらったことで、とても幸せな気分になった。あぁ、いい日曜日だったな――。
そして月曜日。どんよりとした雲に覆われた空の下、私は待ち合わせに遅刻した。
そもそも初めて降り立つ土地は、かなり気を付けなければならない。なにせ「都立大学駅まであと一駅!」というところで到着したのは、「九品仏駅」という、読み方も分からない初めましての駅だった。
そこから再び自由が丘駅まで戻り、別の路線に乗り換えると、たしかに一駅で都立大学駅に着いた。
(この乗り換えミスさえなければ、遅刻じゃなかったのに)
そんな言い訳をブツブツ呟きながら、待たせていた友人と会う。今回、私の用事で呼び出したにもかかわらず、こちらは手ぶらかつ大遅刻。
なのに友人は、どこかのお土産としてマドレーヌを持ってきてくれたのだ。
(これは絶対に私のために買った土産ではない。誰かのため、もしくは自宅用に買ったマドレーヌだろう。それをわざわざ私に与えてくれるとは・・・)
そんな友人の優しさに心打たれながら、帰りのバスでマドレーヌを食べ尽くしてやった。
そして夜になり、また別の友人と会うことに。すると開口一番、
「忘れる前にコレ・・・」
と言いながら、ジップロックに入ったチャーシューを手渡された。それは、過去に私があげた「生食パンのお礼」だった。
少し前のこと。諸事情から、買ったばかりの高級生食パン2斤を手放すこととなり、たまたまその場にいた友人に押し付けたのである。別に欲しかったわけではないだろうが、友人は喜んで食べてくれた。
あの時のお礼として、得意の手作りチャーシューを作ってきてくれたのだ。
元料理人だけあり、タコ糸の巻き方といい、チャーシューの渦巻きといい、見事なフォルムを形成している。さらに自家製のタレがキラキラと輝き、食欲をそそる。
(早くかぶりつきたいな・・・)
とその時、お嬢様の友人から呼び出された。
「アレ、持ってきてくれた?」
「アレ」とはワンピースのこと。昨年の夏にH&Mで買ったVネックワンピースがあり、それを諸事情から着用する羽目になった私。
そこで、夏服の衣装ケースからワンピースを引っ張り出したところ、見事シワシワになっていたのだ。
何日かハンガーに掛けてぶら下げておいたのだが、シワは一向に消えない。そのため、お嬢様の友人に愚痴をこぼしたところ、
「じゃあ持ってきなよ。私がアイロンかけてきてあげるから」
と、素晴らしいアイディアを提案してくれたのだ。こんなめんどくさい手間を笑顔で自ら引き受けるなんて、育ちの良さ以外に何があろうか。
申し訳ないなと思いながらも、図々しい私はちゃっかりワンピースを持参していた。そしてそれを渡すと彼女は、
「じゃあ、ちょっと時間つぶしてて。アタシもトイレ行きたいし」
と、なぜか私を邪険に扱った。とりあえず、言われるがままに時間をつぶし、30分ほど経った頃にお嬢様の元へと戻ると、なんとそこにはハンガーに掛けられたツルツルのワンピースが吊るされていた。
「・・・え?これって、どういうこと?」
状況が把握できない私はお嬢様に尋ねる。すると彼女は、置いてあった小さなアイロンを指さしながら、
「これ、古いんだけどね。試してみようと思って使ってみた」
と微笑んだ。そう、私のためにわざわざ旅行用の小さなアイロンを持ってきてくれたのだ。さらに、アイロンなど使ったことがないであろう私を見越して、私をどこかへ追いやった隙にアイロンをかけておいてくれたのだ。
「でもまたシワになるかもしれないから、着る直前にアイロンかけてもいいかもね。これ持って帰っていいからさ」
そう言いながら、小さなアイロンの使い方を説明してくれるお嬢様。どうやら水を入れてスチームアイロンとして使うのだそう。そうすることでハンガーに吊るしたままでもアイロンがかけられるらしい。
(段ボール箱ならあるが、アイロン台などあるはずもない我が家。だが吊るしたままならなんとかなりそうだ)
こうして私は、また一つ家電製品の扱い方を覚えたのであった。
*
私はきっと、帰宅途中に事故に遭って死ぬだろう。無事に帰宅できたとしても、大地震が発生して津波に飲まれて命を落とすだろう。
なぜなら、こんなにも食べ物に恵まれたり、アイロンをかけてもらったりすることなど過去にはなかったわけで、こんな幸せが続くはずもないからだ。
ということは、これこそが最期の晩餐になるのだ――。
そう思いながら、手作りチャーシューをナイフとフォークで切り分けながら、これまた手作りのタレにチョンチョンしながら噛みしめる。
(・・・うん、美味い)
ガツンと手ごたえのあるタレは、まさに男料理といった印象。しっかりと巻かれた分厚いチャーシューは、脂身の美味さよりもタフな豚肉の噛み応えに感動を覚える。
(これが最期の晩餐だ。よく味わって食べよう)
覚悟はできている。こんな美味いものばかりを与えられて、のうのうと生きていられるはずがない。
いつ私がこの世を去ってもいいように、こうして現状を綴っているのだが、今のところはまだ生きている。
サムネイル by 希鳳
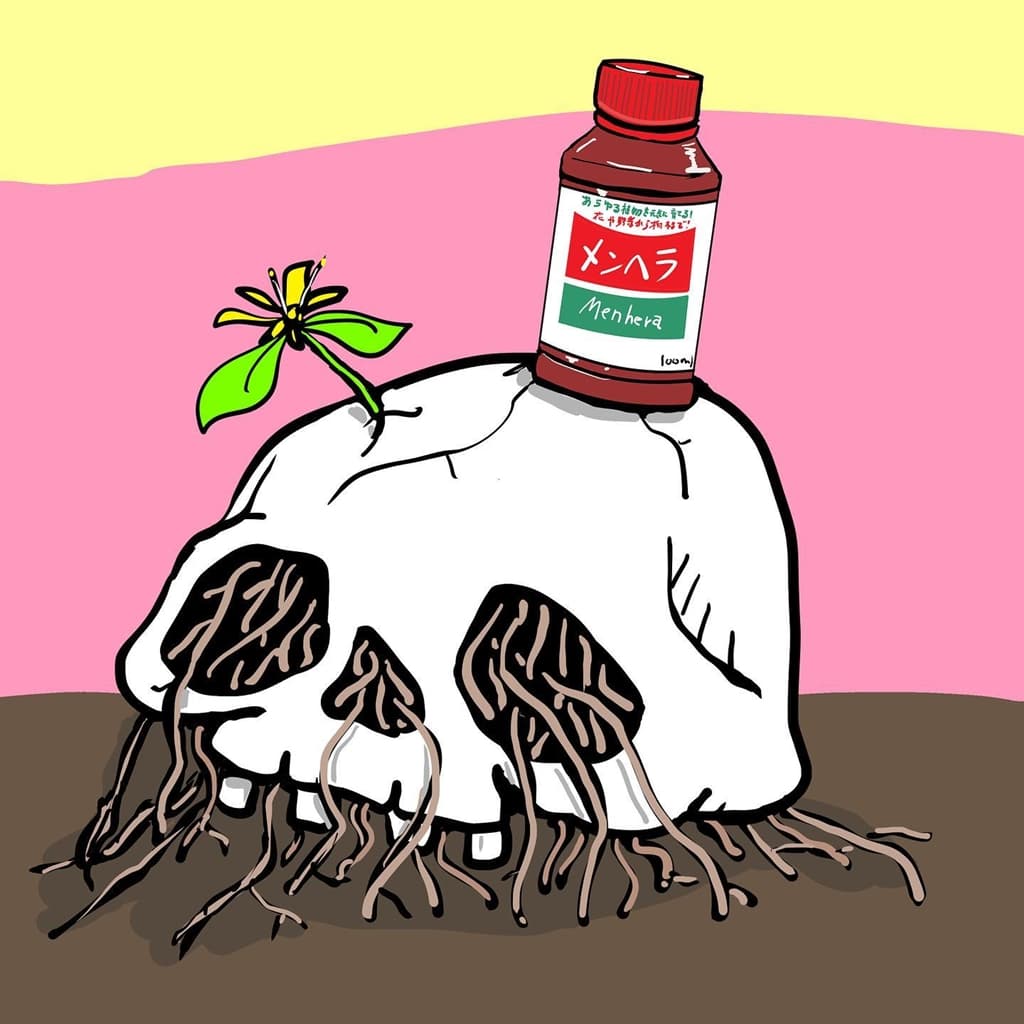






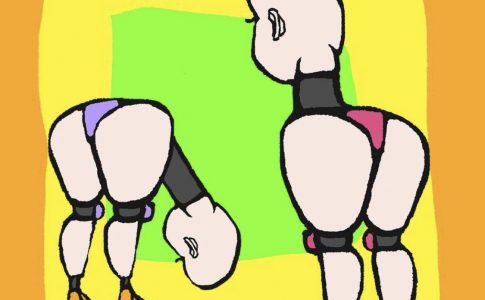













コメントを残す