築47年、木造平屋の一戸建てで暮らしている僕。この家は元はというと死んだばあちゃんの住まいだった。だけどこんなボロ家じゃ買い手もつかないだろうから、家賃を浮かすためにも今は僕が住んでいる。
しかし昭和の家屋というやつは、快適さがまるでない。今どき、バランス釜の正方形の風呂なんて存在するんだろうか?
さらにタイル張りの狭い風呂場は、冬のこの時期は地獄。窓はペアガラスじゃないどころか、木製の枠が腐って歪んでいるせいで常に風が吹き込んでくる。
とはいえ、ばあちゃんの最期がこの風呂場だと思うと、いまだにやるせない気持ちになるんだけど。
関東大震災でもくれば一発でつぶれるであろうこの家だが、唯一の自慢といえば、壁に掛かっているウズボン打の古時計だ。僕がまだ小さかった頃、夏休みにここへ来ると鳴り響く「ボーンボーン」という音が、ばあちゃんちの唯一の思い出だった。
今じゃ30分に一度はボーンを聞くわけで、うるさいと思う反面、時間が過ぎるのは本当に早いもんだと思い知らされる。
コロナで仕事がなくなり、生活保護をもらいながら悠々自適に生きているんだけど、最近、体の一部に気になる変化が起きた。
毎日の食事といえば、スーパーで大量に安売りされていたジャガイモをそのまま茹でて、塩を振りかけて食べている僕。そんな中、少し前に食べたジャガイモが苦いことがあったんだ。皮の色はどす黒いモスグリーンで、表面には傷がたくさんついていた。ジャガイモ自体もやや緑がかっていたけど、まだ若いのかな?と思っただけで、いつもより長く茹でて食べたんだ。
一口食べてすぐに「苦い」と感じたけど、野菜の皮が苦いことはよくある。イモの断面に大きな変色も見られないため、気のせいだと言い聞かせて食べ続けた。そしてその苦いジャガイモを飲みこむと、次のジャガイモにフォークを突き刺した。
なのに次のジャガイモもなんだか苦い気がする。さっきのジャガイモの苦みが口に残っているのかもしれないけど、とにかく苦い味しか感じられない。
ジャガイモの芽や皮には、天然毒素であるソラニンやチャコニンが含まれている、と聞いたことがある。あとは、家庭菜園で作られた小っちゃくて未熟なジャガイモにも、それらの毒素が多く含まれていると。
たしかに今回買ってきた大量のジャガイモは、小ぶりでお手玉みたいな大きさだけど、スーパーで売られていた鹿児島県産のものだし、出所も明らか。それが2個も続けて毒イモのはずがない。
とりあえず僕は、15個ほど茹でてしまったジャガイモを急いで食べきった。あれこれ考えると嫌なイメージしか湧いてこないので、「そんなことより、空腹を満たすほうが先だ」と言い聞かせ、いつまでたっても苦味しか感じられないジャガイモを完食した。
――そこから、僕に明らかな変化が訪れたんだ。
舌の左半分が痺れている。そしてジャガイモは残っていないのに、ずっと渋い感じが続いている。むしろ、痺れている舌から苦味が漏れてくるようになったんだ。
麻痺する舌を奥歯で挟むと、ジュワッと液体が垂れる。はじめは気にしていなかったけど、そのうち苦味の正体を不審に思い、搾り取った苦味をペッと吐き出してみた。
(なんだこの緑色の液体は・・・)
緑色の唾液を吐くなんて、ドラゴンボールのピッコロくらいだろう。恐ろしくなった僕は湯を沸かすと、痺れた舌を溶かす覚悟で熱湯を口に含んだ。めちゃくちゃ熱い、口の中の皮がめくれてくる。それでも舌の左半分だけはなぜか何も起きない。
熱くもなければ痛くもないなんて、こんなことあり得ない――。
半狂乱の僕は、来る日も来る日も麻痺した舌へ熱湯を注ぎ続けた。なのに一向に熱さを感じないんだ。さらに数日後、僕は舌の左側に硬い突起物があるのを発見した。でもこれは、もしかすると火傷の痕なんじゃないか?と思ったら、なんだか少しだけホッとした。
ところがそれもつかの間。さらに2,3日が過ぎると、その「火傷の痕」は恐ろしい姿に成長していった。なんとその塊は「芽」だった。ジャガイモの芽が生えてきたんだ!
奥歯で芽の周辺を噛んでみると、全体的に硬くなっているのが分かる。これはもう見るまでもなく、ジャガイモの根が張っているに違いない。舌の痺れも範囲を広げており、それは根が伸びるのに従って浸潤しているかのようだった。
(待てよ、むしろラッキーかもしれない)
僕は思った。このままうまくいけばジャガイモが育つかもしれない。そしたらスーパーで買う必要がなくなる。家庭菜園ならぬ自己栽培でジャガイモが収穫できるんだ。養分も必要ない、熱湯を注いでいれば勝手に育つんだから。
――人類が食糧難で餓死しようとも、僕は生き残れる。僕は僕自身でジャガイモを生み出すことができるんだから!!
ニュータイプに目覚めた僕の背後では、古ぼけた掛け時計がボーンボーンと時を刻んでいた。
(了)
サムネイル by 鳳希(おおとりのぞみ)
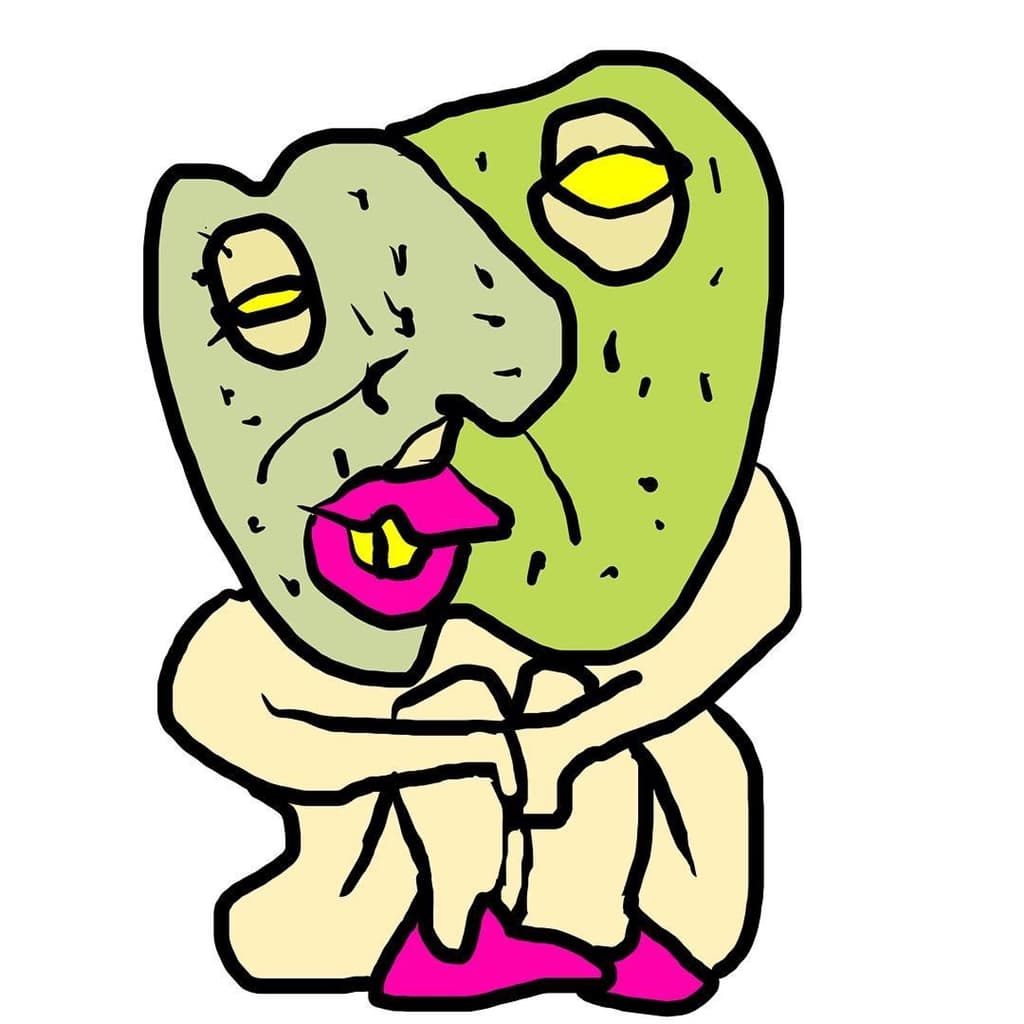




















コメントを残す