今年4月、埼玉県・草加市の粗大ごみ回収に従事する現場職員ら47名について、「業務開始前、作業服への着替え時間も労働時間に当たる」という指導を、春日部労働基準監督署が行っていたことがニュースになった。
草加市役所側は、制服(作業服)への着替えにかかる「3分間」を労働時間としてカウントしていなかったため、過去3年間に遡り時間外労働に対する割増賃金として約220万円を支払うこととなった。また、就業前の着替えのみならず運転手のアルコールチェックについても、黙示の指示があったとされている(労働新聞)。
他にも、三六協定の上限である「3時間」を超えて労働させた日が複数あったことが確認され、その部分についても割増賃金を支払うこととなったと報じられている(埼玉新聞)。
このニュースを知った接客サービス業・・とくに飲食業の経営者は、「そんなこと言ってたら、店が回らない!」と思っただろう。
いかんせん、ホールスタッフがユニフォームに着替えたり、キッチンスタッフがエプロンやコックコートを着用したりするのは、仕事に入るための当たり前の服装であり、身支度を整えてからタイムカードを打刻するのが当然の流れだと考えているからだ。
そしてその通り、エプロンやユニフォームは仕事の際に着用する作業服であるため、それらを着る=仕事に入るという合図でもある。ということは・・仕事のために作業服へ着替える時間というのも、「業務時間」ということになるわけだ。
かくいうわたしも、かつてカフェでアルバイトをしていた頃、エプロンを巻いて身支度を整えてからタイムカードのボタンを押していた——今思えば、あれは労基法違反だったことになる。
とはいえ、どこの飲食店でもほぼ当たり前に”身支度を整えてからシフトインする流れ”ができており、「たかが数分だし、そこまでこだわる必要はない」と思いがち。だが、今回の草加市役所の件からも、賃金の時効が3年(原則は5年だが、当分の間は3年)であることや、従業員の人数が多ければ多いほど未払い賃金の額は跳ね上がることから、”たかが数分”の積み重ねが、事業主にとって大きな痛手となるリスクは否定できないのである。
「ならば、10時からフロアに出てもらいたいときは、シフトは9時55分からにしなければならないのか?」
——そういうことになる。しかしながら実際には、エプロンをかぶる程度の着替えならばものの数秒で終わることからも、そこまでナーバスになる必要はないだろう。
ところが、明らかに着替えが必要な場合・・たとえば、料亭や旅館で接客・給仕を担当する”仲居”は、着物姿がユニフォームとなるため、着付けや髪型を整える時間として長ければ30分ほどかかる。
そのため、多くの仲居が始業30分前に職場へ到着し、身支度を整えるのが慣例となっているのだ(むしろ、ほとんどがそうかもしれない)。
そして当然ながら、この身支度の時間は「労働時間」となるわけだ。
本来ならば、着替えにかかる時間を逆算してシフトを作成する必要がある。もちろん、業務終了後の着替えについても労働時間としてカウントされるため、仲居業における勤務シフトは”前後1時間が着替えの時間”となる可能性も。
加えて、これもよくある話だが、店のオープン前に行われるミーティング・・いわゆる「朝礼」について、こちらも言うまでもなく労働時間となる。よって、当日の予約状況の確認や業務連絡を行う際は、そこも含めてシフトを検討しなければならない。
ちなみに、とある顧問先はオープンとクローズの前後に付随する作業時間について、そちらを優先するため営業時間を変更させた。これは驚きの英断だったが、労務管理の側面から考えると、×時00分から朝礼や準備時間として15分を確保し、×時15分に店をオープンさせる・・というほうが、明らかに管理しやすいのだ。
顧客側としても、そこへきて15分は大した差ではないため、売り上げも変わらずコンプライアンス遵守も徹底できるという、まさに一石二鳥の労務管理&店舗経営が実現したのである。
*
労働法は労働者を守るための法律であり、その判断基準は”労働時間”と”業務実態および慣例”にある。
よって、この期に及んで「お客様は神様だ!」などと、手放しでこびへつらっている場合ではない。まずは、自社の神様である従業員のコンプライアンスを徹底した上で、次なる神様・・お客様へのサービスを提供するのが、労働者を雇用する事業主の責務なのである。
むしろ、この順番なくして事業は成り立たないだろう——なんせ、労働者こそが会社を支える神様なのだから。



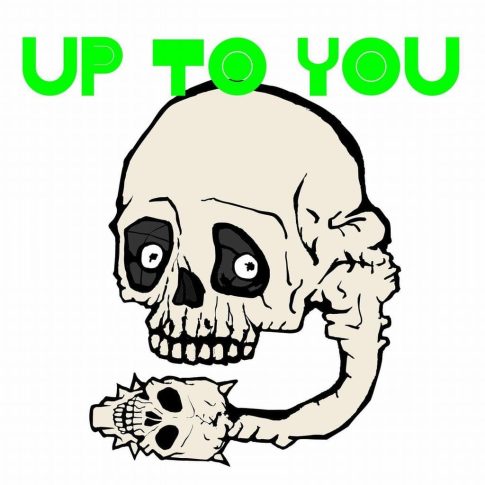
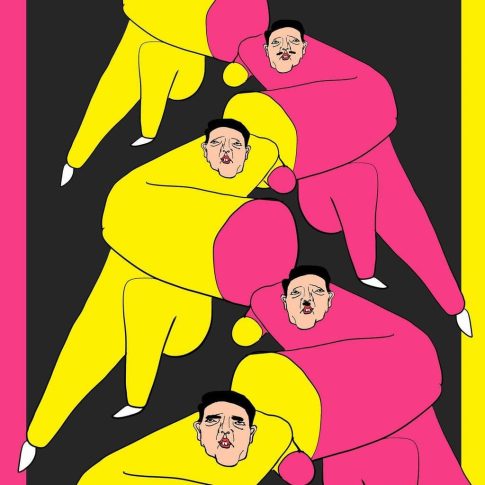
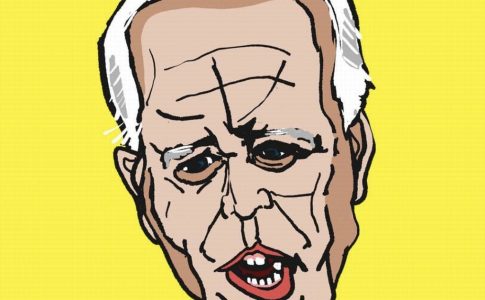

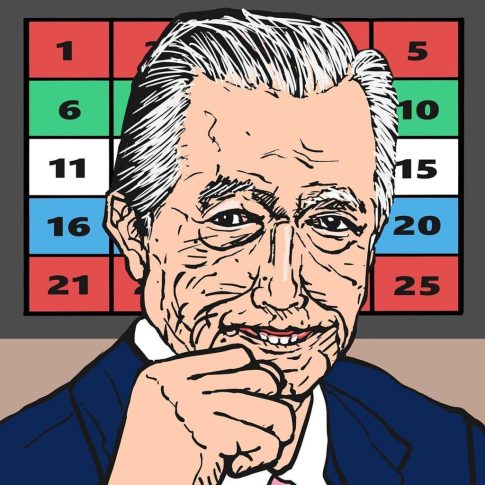













コメントを残す