今月に入ってから、日々せっせと社労士の仕事に勤しむわたしは、連日「時間が足りない」とボヤいている。今月・・すなわち7月は、労働保険料の年度更新(申告)と、社会保険の算定基礎届の申請を行わなければならないため、社労士にとっては一年で最も多忙な数週間となるからだ。
ちなみに年度更新は、昨年度に支払った賃金総額が分かればさほど大変な作業ではないが、年度途中で雇用保険に加入したまたは雇用保険を喪失した労働者がいる場合、その月を境に乗じる保険料率が変わるため注意が必要。
これが顧問先であれば、その都度メモを残すなどして年度更新の際に注意喚起ができるが、スポットで依頼を受けた場合、念のため12カ月の内容を確認しなければならないので結構な作業となる。
「でも、雇用保険加入は週20時間以上だから、およその賃金総額で判断できるのでは?」
たしかにその通りなのだが、今回引っかかったケースとして三つの「擬態」があった。
まず一つ目は、週20時間程度をウロウロしているアルバイトだ。入社当初は雇用保険未加入だったが、数カ月働くうちに週20時間をギリギリ超えることが多くなり、「ならば雇用保険に加入させよう」ということで、途中から被保険者となった者がいる場合は要注意。
そして二つ目は、ダブルワーク先で加入していた雇用保険を喪失した労働者だ。予てから労働時間は週20時間を超えており、本来ならば雇用保険への加入が必要だが「ダブルワーク先で入っているので」という理由で、こちらの会社では未加入となっていたケース。労働時間や支給額に変動はないものの、雇用保険料だけがシレっと控除されているので、こちらも見落としがちな罠といえる。
最後は、役員が労働者になったケースだ。役員報酬として、一般的なフルタイム労働者程度の報酬を得ていた者が、労働者へと身分が変更となった後も総支給額に変動は見られない。にもかかわらず、ある月から雇用保険料が控除されているじゃないか——。
・・このように、「何月から雇用保険料の控除が始まったのか」をチェックし、念のため資格取得確認通知を確認したうえで、その月から雇用保険料率を乗じた金額を算出しなければならないため、ざっと総支給額に目を通すだけでは見落としてしまう場合もあるのだ。
「アルバイトから正社員へ変更」というように、誰が見ても明らかな変化があればまだしも、先に挙げた「擬態」はなかなかのくせ者であり、スポットで受任する際の落とし穴ともいえるのである。
いっぽうの「算定基礎届」でも、内訳を確認しないとうっかり見過ごしてしまう「擬態」がある。
算定基礎届は、4・5・6月に支給された賃金総額をもとに、その年の9月から翌年8月までの社会保険料等級を決定するもの。この時期は年度初めということもあり、比較的残業代が増えてしまったり昇給と重なったりで、保険料を決定するには不利な条件が揃いがちな季節ではあるが——。
それよりなにより、注意すべきは「遡及調整」の罠である。過去の昇給について遡って4月に支給していたり、給与計算ミスで過払いしていた分を5月で調整していたり、それだけでも等級が一つ変わるくらいの額だと、絶対に見過ごせない処理となる。
ましてや、毎月インセンティブが発生するような会社では、そもそもの総支給額が安定しないため、それが遡及支給なのかそうじゃないのかを確認しなければならず、結局は全員の賃金に目を通す必要があるのだ。
被保険者にとっても会社にとっても、保険料を納付する側からすれば正しく算定してもらいたいのは言うまでもないが、仮に年金事務所の調査が入った際に「遡及調整があったのに処理ができていない」となれば、その時点で遡って算定の訂正が必要となり、会社に対して多大な迷惑をかけることとなる。
そんな未来の不安を払拭するべく、せっせと全員の給与に目を通しながら算定基礎届の画面を埋めていくのが、われわれ社労士の仕事なのである。
この「擬態」について、労務管理システムや給与計算ソフトで正しく入力できていれば、年度更新や算定の処理も一発で済むわけだが、なかなかそうもいかないのが現実。中には、手計算かつ手書きで管理している会社もあるため、そんなところはどうしたってすべてに目を通さなければ、恐ろしくて申請などできるはずもない。
とはいえ、システム任せで自動計算された年度更新や算定基礎届について、あとから指摘が入った場合に「ソフトが勝手にやったんで、知りません」では通らない。無論、それらを販売する会社のほうでもあらゆるリスクを想定してシステムを構築しているはずだが、現場側の技量で左右される部分——ソフトを扱う者の理解度や入力作業の正確さ——に影響されるので、やはり最終的には人間の目・・というか社労士の目でチェックする必要がある。
なんせ、必ずといっていいほどミスがあるわけで・・・。
*
年度更新も算定基礎届も、表面上は誰にでもできる単純な作業であるのは間違いない。だが、その真偽についての判断は、労働法を熟知し実務に精通している者にしかできない・・というのも、否定のしようがない事実なのである。
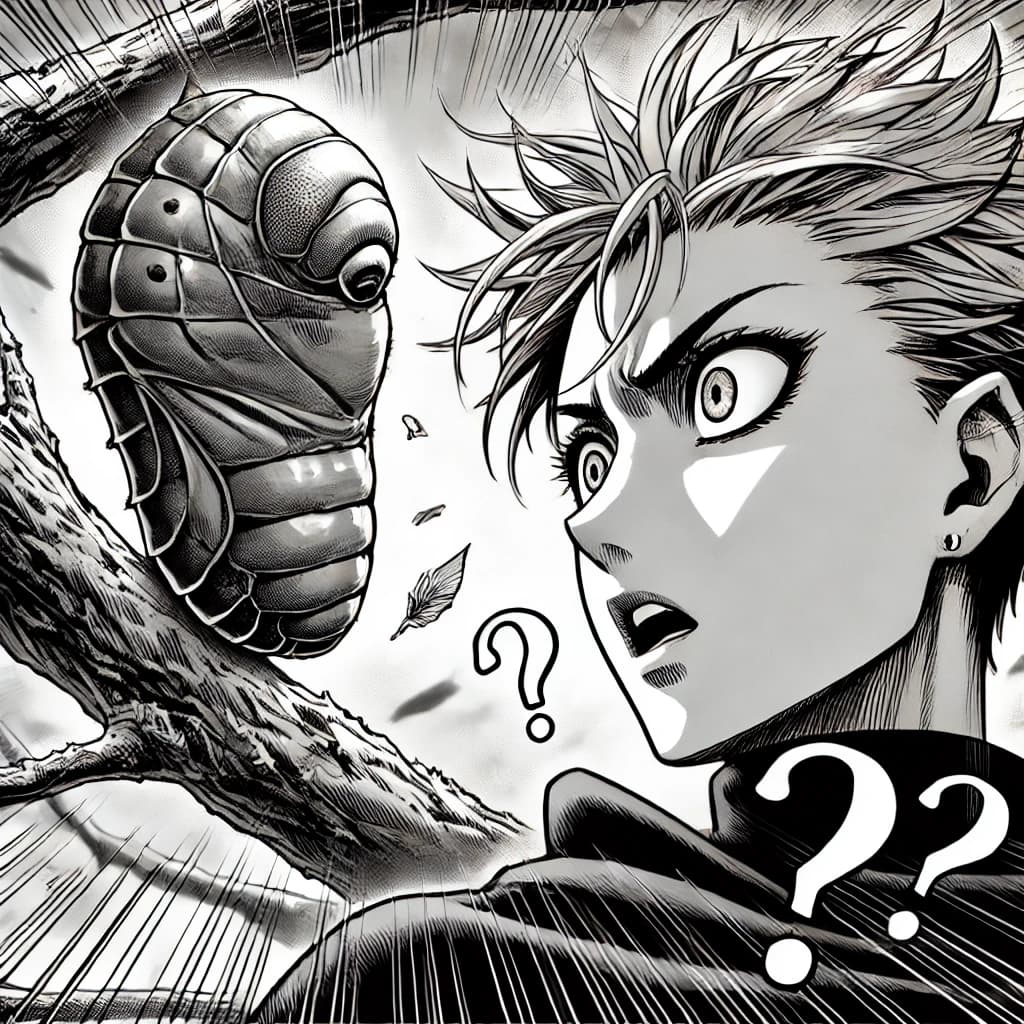


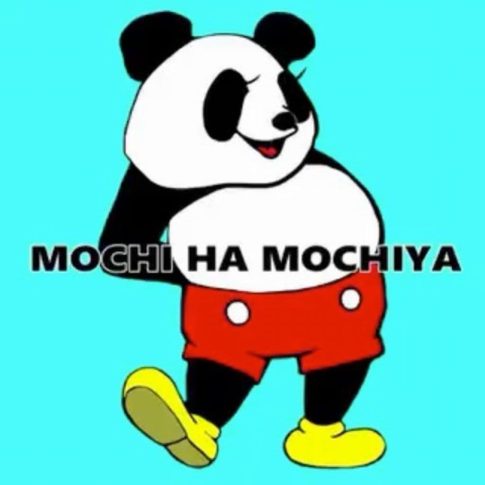
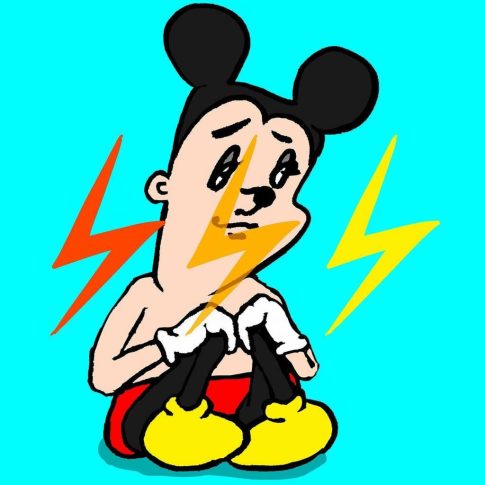
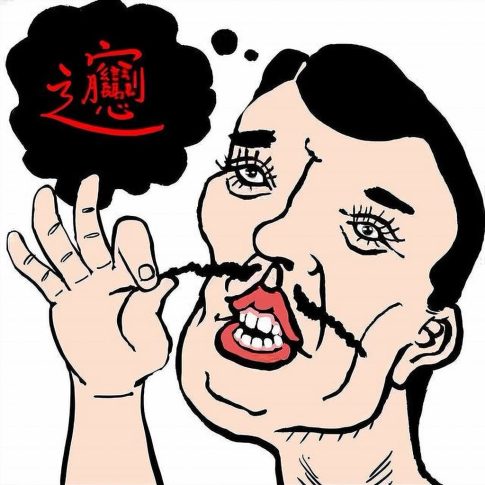


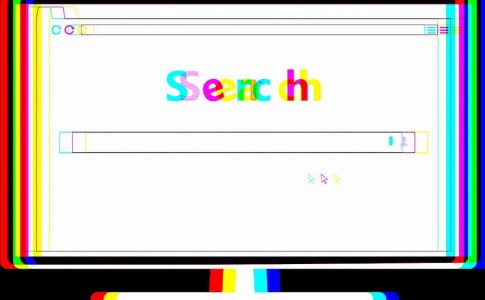
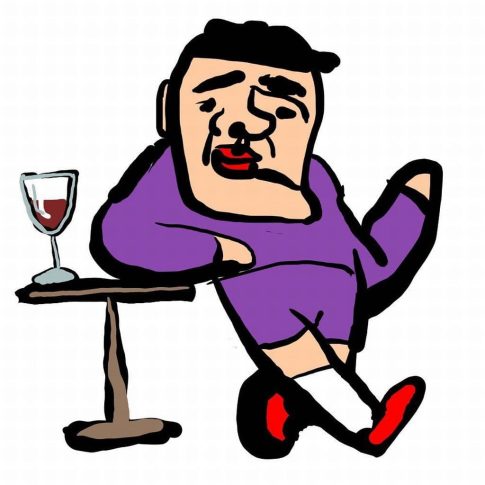
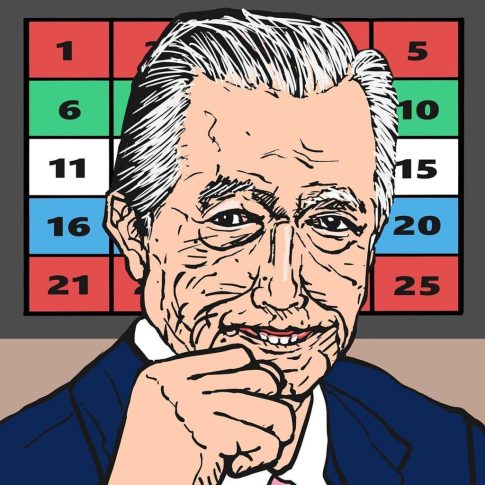










コメントを残す