どれほどイキがったところで、所詮わたしは温室育ちの港区民なんだ——。そう認めざるを得ないほど、足立区竹の塚は"修羅の街"としての威厳を放っていた。
深夜3時半、わたしは足立区の治安維持を任されたオトコ(以下、石井と呼ぶ)と共に、足立区のなかでも最も足立区っぽいエリアである「竹の塚」を訪れた。足立区竹の塚といえば、泣く子も黙る混沌とした土地。今でこそ駅周辺は整備されて、ファミリー向けの住宅地として人気を博しているが、竹の塚の本質はそんな生ぬるいものではない。
「そこのラーメン屋に行こう」
大通りに堂々と路駐をすると、石井はアゴで細い路地を示した。その先にあるのは——スナック??
一見、場末のスナックにしか見えないさびれた店舗へ近づくと、それは古びたラーメン屋だった。その名も「梁山泊」、腕に覚えのある豪傑らが集うラーメン屋なのだろう。なんせ、港区民ならばぐっすり眠っているであろうこの時間に、店内にはすでに三名の客がいるわけで、足立区の夜がどれだけ深いものなのかを物語っている。
さらに、石井を含む客らは全員ジャージ姿で地元民であるのが一目瞭然。対するわたしはデニムを履いており、いかにも"よそ者"風情を醸し出していることに、恥ずかしさを覚えた。
足立区のラーメン屋は、多くの店が4時半閉店なのだそう。白金のラーメン屋など・・いや、白金にはラーメン屋すら存在しないわけで、この時点で夜を生きる足立区民には太刀打ちできない。
そして、年季の入った店内にはBOØWY(ボウイ)の曲がエンドレスで鳴り響いている。「この店は、いつ来てもBOØWYしか流れてないんだ」と、石井が補足する。これもまた、足立区の・・いや、竹の塚のプライドなのかもしれない。
ふとカウンター席に目をやると、革のバッグとスマホが放置されている。だが客の姿は見当たらない——まさか忘れて行ったのか?いや、さすがにそれはないか・・。すると、店主がおもむろにトイレのドアを叩きながらこう吐き捨てた。
「もう20分ですよ、いい加減に出てきてください」
内側からコンコンとノックを返す音はするが、どうやら我々が入店する以前からトイレに籠っている様子。酔っ払いであることは間違いないが、果たして居眠りしているのか、それとも嘔吐しているのか——。
すると石井が、ごく当たり前の表情でこう言った。
「足立区では、トイレで寝るとか当たり前だから」
まぁ、港区でもトイレで寝る酔っ払いはいるだろうが、よりによってこんな狭いラーメン屋のトイレで寝ることはないだろうに。
注文を済ませてしばらくすると、すでに食べ終わった客らが店を去り、入れ替わりで新たな客が入ってきた。この時点での時刻は午前3時50分——、いったい足立区民は何時に寝るんだろうか。
「俺らの頃は、竹の塚警察署ってなかったんだよね」
思い出したかのように石井がつぶやく。若かりし頃の彼が世話になったのは綾瀬警察で、その当時、竹の塚警察は存在しなかったのだそう。そのため"ワルの巣窟"である竹の塚を綾瀬警察が一手に引き受けており、生活安全課はそれはそれは大賑わいだった模様。
おまけに足立区は、"大人の遊園地"こと東京拘置所を保有しているため、北舎、新北舎、南舎など入所した者にしか知り得ない貴重な情報まで聞かせてもらった。
さらに、道路の真ん中んに設置された中央分離帯について、
「あれ、俺らの暴走行為を阻止するためにできたんだ」
と、昔を懐かしみながら石井が当時を語ってくれた。あぁ、やはり石井は生きた足立区の伝説なんだ——。
そうこうするうちに、注文したラーメンが運ばれてきた。梁山泊の名に恥じない見事なボリュームと濃厚なスープ、そしてゴロゴロと横たわるチャーシューに散りばめられたネギを眺めながら、この殺伐とした店内ですするラーメンの意義あるいは重みに、果たしてわたしは耐えられるのか密かに不安を抱いた。
目の前では石井が平然とラーメンに食らいついている。それは足立区民にとってはごく自然な行為であり、当然ながら躊躇などするはずもない。対するわたしはしがないシロガネーゼ、どう虚勢を張ろうが足立区民の足元にも及ばないわけで——。
すると突如、トイレのドアが開いた。中から一人のオトコが現れ、何食わぬ顔でスマホとバッグを回収すると、店を後にした——マジで寝てたのか。
*
圧倒的にタフで肝が据わった区民・・それが足立区民であり、なかでも竹の塚の住民はある種の精鋭部隊といっていいだろう。
夜な夜なラーメンをすすり、アウトローの道を黙々と進む彼らを間近で観察したわたしは、港区民ならではの高貴な貧弱さを痛感し、完膚なきまでに打ちのめされた気分で帰還したのである。
(シロガネーゼにとって、足立区の関門突破はまだ早かったようだ・・・)

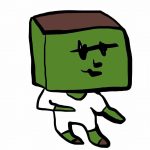



















コメントを残す