谷崎潤一郎の「春琴抄」を読んだ。
2時間もあれば読了できる薄い文庫本なので、ぜひ一度読んでもらいたい。なにせ帯には「人間の欲望の深淵を覗いてみたいと思うなら、谷崎の作品こそうってつけです」などと書かれており、奇しくもこのブログのタイトルである「URABEを覗く時」とかぶるではないか。
スタバの一角を陣取り、早速読み始めた。一ページ目でつっかえる。
「それならあれにありますのがそれかも分かりませぬ」
一文字ずつゆっくりと読まなければ、意味不明な呪文と間違う。まぁ数ページも読み進めるとなんとなく慣れるので、しばし我慢。
その後も「蓋(けだ)し」「行年五拾八歳」「俤(おもかげ)」などの言葉に悩まされつつ、ラスト10ページあたりまで進んだ。
この話、簡単にまとめるとこうだ。
主人公は金持ちの家に生まれた美女で、幼くして盲目となる。当時、お稽古事として琴や三味線を習っていたが、その才もあり、20歳で自身の教室を構え師匠となった。その師匠の目となり手足となり、甲斐甲斐しく世話をし続けた男がいる。師匠への忠誠心と愛情の深さが常軌を逸しており、男も独学で琴や三味線を学び彼女の弟子となり、師匠亡き後、自らが師匠を継いだ。その男、40歳過ぎに失明の道を選ぶのだが、それには発端となる事件があった。ある日の夜中、何者かが侵入し師匠の顔に大やけどを負わせた。元来美人であることを認識していた師匠は、顔がやけどでひどい状態となったであろうことを憂い、誰にも見られたくないと泣いた。それを見た男は、自らの両目を針で突いて失明させた。
この、縫い針で目を突いて失明させたくだりで涙が溢れた。
「アンタも女やのぉ」
元議員で脳科学者の友人が言う。しかし、残念ながら男が示す愛情の深さに涙したわけではない。眼球、しかも黒眼を何度も突くという恐怖と痛みと絶望を想像すると、わたしはもはや瀕死状態となったのだ。
くどいようだが、わたしにとって目は命と同じ重さがある。生まれた時から目の見えない父と、右目だけ見える母の子として育ったわたしは、毎朝毎夕「いずれおまえも失明する」と耳にタコができるほど聞かされた。だからこそ、今見えるこの景色を忘れるなと、自由奔放に生きてきたのだ。
その結果、未だに両目とも見えており、自由奔放さだけが定着する結果となった。
・・・話を戻そう。目が見えなくなる=死の覚悟を持つわたしにとって、この作中の男が自らの黒眼を縫い針で突いて失明させる行為は、自殺と同じだ。
ましてや
「白眼の所は堅くて針が這入らないが黒眼は柔かい」
などというリアルすぎる描写に、全身鳥肌が立った。
平々凡々なわたしには、想像しただけで痛く、苦しく、絶望しか感じられない。
だがこの男、そうして得た「盲目」という状況こそが、結果として、師匠すなわち愛する女にリアルに近づくことができたと喜んだ。
他人に対してそこまでの想いを抱けること、愛を注ぎ続けられることが奇跡だし、その我慢強さには脱帽する。
当然ながら、わたしには無理だ。
失明する=自殺をしてまで、誰かのために生き続けることなど。
*
この恐ろしい余韻に浸りながらスタバを出ると、カラフルにライトアップされたタイ料理屋の看板が目に入った。早速、テイクアウトの注文をするも現金が足りないことに気付く。さらにスマホ決済もクレカも使えない。
仕方ない、少し先のATMで金を引き出してくるから待っててくれ、と店を後にする。
信号を渡るとパン屋が目に留まる。パン屋というのは不思議なもので、どんな状態(満腹、イライラ、多忙、雨降り)でも美味そうに見えるし、必然的に立ち寄らせる魔力がある。
店に入り、クロワッサンやらブリオッシュやらハード系のパンやらを買い漁る。ここはモバイルスイカで済んだ。
そして今、気づくとわたしは電車の中にいる。何か忘れているような、忘れていないような気がしていたのだが、タイ料理を注文したまま、支払いも受け取りも忘れていることに今気が付いた。
これも全て、谷崎潤一郎がわたしに与えた恐怖と、荒んだ心を包み込んでくれたパンの匂いのせいだーー。
最寄り駅の改札を目の前にして、わたしは再び乗車駅へと踵をかえす。
Illustrated by 希鳳









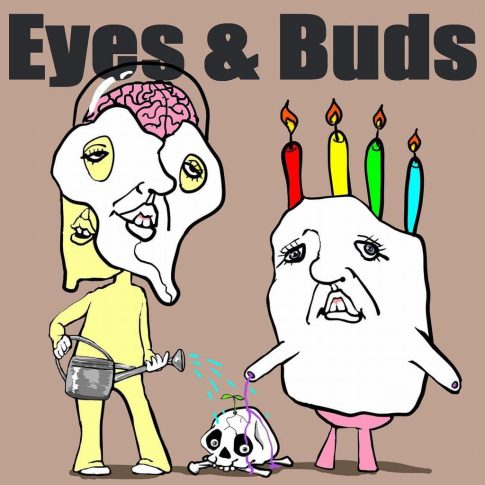











コメントを残す