身内の法要にすら参列したことのないわたしだが、愛犬・乙の一周忌には姿を現したわけで、これが人生初の”節目の供養”への関与となった。よって、すべてが珍しく新鮮に感じられたのは、法要の素人だから・・という可能性もあり、一般的には常識として認知されていることであれば申し訳ない。
その上でわたしは、「住職のタイムマネジメント能力」に釘付けとなったのである。
*
”法要素人”のわたしにとって、一周忌は初めての経験だが葬儀には何度か参列したことがあるので、およその流れは理解している(つもり)。ちなみに、儀式の意義は「故人を悼み感謝を伝え、残された者の心を整理する場」だと弁(わきま)えているが、そういった場に慣れていないわたしは毎回、お焼香のタイミングがくるとドギマギしてしまうのだ。
(お焼香って、どうやるんだっけ・・)
これだけで頭の中はパニックになり、故人を偲ぶどころの話ではなくなる。なんせ、前の人の真似をしようにも背中が邪魔で手元が視認できない。おまけに、遺族らの目の前でミスなく焼香を済ませなければならない——こういう場で、マナー違反や失礼があってはならないという、常識人的な認識は持ち合わせている——というプレッシャーというかプライドがあるため、「お焼香をお願いします」というアナウンスと同時にスマホで「焼香の仕方」を検索し、動画を見ながらイメトレを繰り返すのであった。
そして今回も「お焼香をお願いします」という声掛けはあったが、参列者が父と母とわたしの三名のみなので、あらかじめ手順について動画で確認しておいたわたしは、余裕をもって自分の出番を待っていた。
とその時、ふと思ったことがある——読経は滞りなく続いているのに、進行係はなぜ「お焼香のタイミング」を告げることができたのだろうか。
大した事ではないが、なんとなく不思議に思いながらも焼香を済ませ、元の席へ戻って一息ついた頃、まるで図ったかのように読経が終わったのだ。
配置的にいうと、祭壇の前に住職、その背中を拝むように参列者、さらにその背後に進行係・・というフォーメーションのため、住職が目くばせなどで進行係へ合図を送ることは不可能。
——まぁこの辺りは、住職のアイテムである”仏具”のどれかで合図を送ったのだろう。木魚、鈴(りん)、鉦(しょう)のうち、もっとも使用頻度の低かった「鉦」を叩いた時が、「もうそろそろ、お焼香ね」という合図だったのでは・・と予想している。
では、住職はどうやって「ちょうどいいところで合図を送れたのか」というのが、さらなる謎である。無論、今回のように少人数であれば逆算も可能だろうが、参列者が大人数の場合など、どうやってペース配分を決めているのだろうか。
どうしても気になったわたしは、法要の後にスタッフへ尋ねてみた。すると、当たり前だが「なるほど」という回答を得られたのである。
「およその参列者数をこちら(葬儀社側)が把握しているので、それを事前にご住職へ伝えます。お経の長さは決まっているので、その人数でお焼香にかかるであろう時間を逆算して、合図があったらこちらからお焼香を促すアナウンスを入れるんです」
(まぁそうだよな・・)
「でも、あまりに参列者が多い場合などは、お経を繰り返しているようです。我々には分からないですが、いつもちょうどいいタイミングで終わるので、きっと調整されているんでしょうね」
さらに、「全員の焼香が済んだかどうかについて、こちらへ背中を向けている住職はどうやって知るの?」という疑問について、
「あらかじめ人数を伝えているので、その数をカウントしていたり、横目で参列者を確認していたりと、ご住職によって違うみたいですよ」
と、これまた当たり前だが「なるほど」という回答をもらったのである。
たしかに、自分が住職の立場になってみれば、あらかじめ人数を把握したうえで視界の隅で動く人影をカウントするだろう。そして、たとえば10人ごとに鈴を鳴らすとかして、忘れないように目印(耳印?)を打つかもしれない——これが正解かどうかは分からないが。
*
というわけで、滅多に体験しない法要に出席したわたしは、社会常識に加えて現場の裏技まで知ることができたのだ——乙、ありがとう。




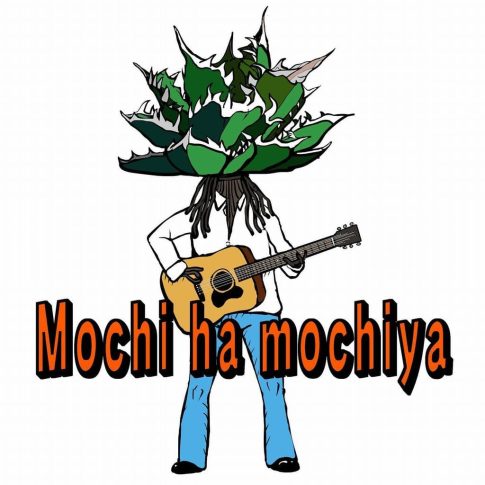
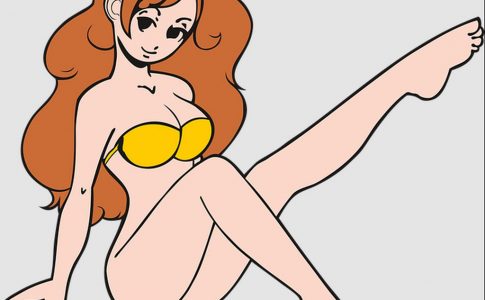















コメントを残す