もしかすると、わたしはニュータイプなのかもしれない——そう疑わざるを得ないほど、なんというか「身体がメカ化」している気がするのだ。なぜそう感じるのかというと、JR埼京線の車内で起きた"とある出来事"がきっかけだった。
本日の目的地である北赤羽駅は、進行方向前後に改札がある作りとなっている。そしてわたしは後方の改札を利用するため、ロスを減らすべく最後尾へと移動するのがいつものやり方。
無論、池袋駅から乗車する場合は、はじめから最後部の車両へ乗り込めばいいが、今日はたまたま赤羽駅から乗ることとなり、しかもホームへたどり着いた途端に埼京線が到着したため、とりあえず目の前の車両へ飛び乗ったのだ。
(北赤羽は次だけど、少しでも改札に近いほうがいいだろう・・)
どうせすぐに到着するわけだが、それでも乗車時間の無駄を省くべく、わたしは最後尾へと歩き始めた。5,6車両も歩けば最後尾であり、その頃には北赤羽に着いているだろう——。
こうして、走る電車に逆らうように後方へと歩き出したわたしは、車両を仕切るドアレバーへと手をかけた。その瞬間、ビリッ!と、まさかの静電気によって放電が発生したのだ。
(イテッ!!)
わたしは、骨折や捻挫の痛みには強いくせに、神経痛のような痛みにはめっぽう弱い。だからこそ冬場は帯電防止に尽力しているのだが、こんな真夏に静電気が溜まっているとは思ってもみなかった。いや、これは何かの間違いかもしれない。要するに、ビリッときた気がしただけで、実際はなにもおきていなかったとか——。
改めて考えると、樹脂製のレバーに触れて放電するのはおかしい。無論、ありえなくはないが、夏のこの時期にさすがにそれはないだろう。ということは、やはりわたしの気のせいだったのだ。
「なぁんだ!」と、拍子抜けした気分で次の車両へ向かい、おもむろにドアレバーに手を伸ばしたところ・・・
「イッテェ!!」
静電気による放電が再び起こったのだ。今度ばかりは気のせいではない、確実にビリッと痛みを感じた上に、心の声が口から漏れたわけで。その証拠に、ドア付近の優先席に座っていた老人が、ギョッとした表情でわたしを凝視していた。
(これは正真正銘、静電気の放電による感電だ。気のせいなんかじゃない!)
ただでさえ布面積の少ない衣服で身を包んでいるのに、どうやって静電気が発生するというのか。しかも、もしも最初の「バチッ」が放電だったとすると、車両一つ分を歩いただけで、もうすでに十分な帯電が完了したというのもおかしな話だ。これはきっと、なにかの勘違いだ——。
そう信じたい気持ちと、そうでなければ納得のいかない自分がいる反面、「次のドアでも、静電気の放電が起きたらどうしよう・・」という恐怖が拭えないまま、わたしは次のドアの前に立っていた。
(よし、念のため手のひらで逃がしてから、レバーを握るとしよう)
指先で触れるから放電時の痛みを一挙に受けてしまうのだ。ならば手のひらや手を握るなどして、広い部分で電流を分散させれば痛みは軽減するはす。静電気があろうがなかろうが、とりあえずお守がわりにやっておこう——。
わたしは手のひら全体でドアを叩くと、恐る恐るレバーを握った。すると・・・
「イッテ!!!」
先ほどよりも大きな痛みが指先を走った。いったいどういうことだ!?おまけに、手のひらでドアをバンッと叩いた音と、その後の「イテッ」という叫び声とで、またもや優先席に座っていた乗客らがこちらへ注目してしまったではないか。
若干の恥ずかしさを覚えたわたしはそそくさとその場を離れ、いざ次の車両のドアと対峙した。それにしても不思議なのは、ドアレバーはなんらかの樹脂でできているように見えるが、どこかに金属が使われているのだろうか——?
どうも腑に落ちないわたしは、レバーに触れると同時に裏側を覗き見たその瞬間・・・
バチッ!!
案の定、しっかりと感電したのである。そしてわたしは、この目で確認した事実があった。なんと、レバーの裏側は金属でできていたのだ!
レバーの裏側に潜むマイナスに帯電した金属から、プラスに帯電したわたしの指先へと電流が流れる・・これはすなわち"感電"であり、当然ながら痛みを感じる・・・とまぁ、静電気の放電の仕組みはこのような感じだが、そんなことよりも、たかが一つの車両を歩く程度で、これほどまでに見事な帯電ができるものなのだろうか。
これはもしや、わたし自身が蓄電マシーンに変化した・・ということなのではなかろうか。
*
結局、最後尾までのすべてのドアで感電したわたしは、あまりのトラウマから「ドアレバー・ドアノブ恐怖症」になったことは言うまでもない。加えてこれからは、わたし自身が"蓄電システム"として稼働せざるを得ないことも、不本意ながら受容するしかなくなった。
あぁ、まさに"ニュータイプの先駆け"となるべく、このわたしが選ばれたのだとしたら——はっきり言って、いい迷惑である。
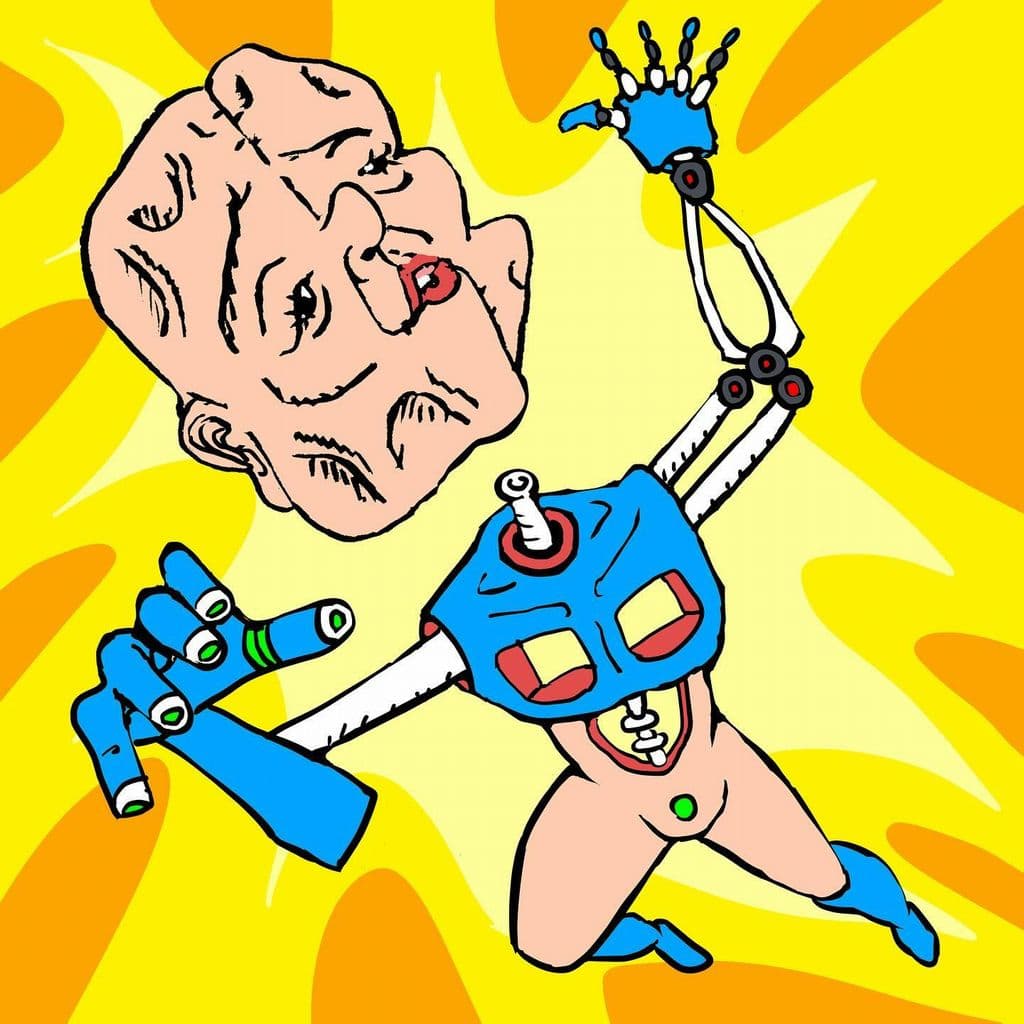



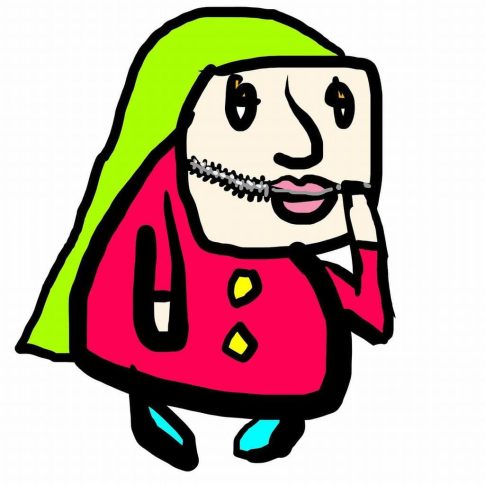
















コメントを残す