(おぉ、まるでボワッとなったカピバラの背中のようだ・・)
カピバラという生き物は、長い年月を野生で過ごしてきたにもかかわらず、背中や腹をゴシゴシなでると全身の毛を逆立てて「気持ちいい」を表す、不思議な動物である。
中には、あまりの気持ち良さに自立することを忘れ、地面にゴロンと横たわってしまう個体もいる。目を細め口元を緩めてしまう者もおり、まるで愛玩動物のような無防備さを持つ、世界最大のげっ歯類なのだ。
そんなカピバラを彷彿とさせたのは、採れたての枝豆だった。
埼玉・秩父市の友人宅を訪れたわたしは、レジ袋いっぱいに詰められた枝豆を発見した。どうやら、ついさっきお隣さんからもらったものらしい。
秩父は都心から近いが、自然豊かで四季折々のイベントに長けた素晴らしい地域である。春は色とりどりの花が目を養い、夏は深緑と川のせせらぎに心癒され、秋は新鮮な果物と野菜に舌鼓を打ち、冬は天然の巨大つららがお出迎え——。これほどの自然に恵まれた土地というのも、正直、珍しいのではなかろうか。
そんな秩父の肥沃な土壌で育った枝豆は、表面を立派な産毛で覆われていた。
濃い緑色の枝豆を手に取ってみると、なにやらチクチクするのを感じた。よく見ると、枝豆の表面を保護するかのように、茶色の短い毛がびっしりと生えているではないか。
さらに顔を近づけて観察すると、なにか見覚えのあるものに思えてきた。——そう、カピバラだ。
撫でられて気持ちよくなったカピバラの体毛は、まるでたわしのように丸く逆立つのだが、その姿とそっくりな枝豆の産毛に、わたしは思わず釘付けになった。
(すっげー!カピバラみたいだ)
枝豆を茹でる前に、スマホで調理方法を確認する友人。どうやら、さやの部分をキッチンばさみで切り落としてから茹でると、塩味が中まで染み込み美味しく茹であがるのだそう。
料理上手な友人は、わたしと会話をしながらもせっせとさやをカットした。しかし彼女の細い腕では、大量のさやをチョキチョキするには無理がある。なぜなら、キッチンばさみはサイズがデカい上に、採れたての枝豆は皮がしっかりしていて切りにくいからだ。
「指が攣りそう!」
とうとう悲鳴をあげた彼女からハサミを奪うと、わたしは「待ってました!」とばかりに枝豆の袋へ手を突っ込んだ。
そもそもわたしは、元来、こういった「リアルな作業」が得意なのである。いや、得意かどうかはさておき、パソコンをカチャカチャいじるような行為よりも、自分の手で形状を変えたりゼロから何かを構築したりすることに、喜びと憧れ、そして誇りを持っているのだ。
「頭を使う仕事のほうが、よっぽどすごいよ」
その昔、学校のお勉強が苦手なとある友人が、わたしに向かってそうぼやいたことがある。そんな彼は、重機の操縦がずば抜けて上手い。しかも、常人離れした上手さと速さ、そして正確さと効率の良さを同時に披露するという、並外れた能力を持っているのだ。
とはいえ今のご時世、土方のような現場仕事は低学歴の象徴とされ、オフィスワークこそが優秀な人材の宝庫という、大きな勘違いがまかり通っている。
人間の能力は、文部科学省が決めた暗記テストで測れるようなものではない。むしろ、不安定な環境下でいかに効率よく作業を進められるかという、段取り・調整能力そして咄嗟の判断こそが、仕事における最も重要な要素である。
そして今、わたしは試されようとしているのだ。堆(うずたか)く積まれた枝豆のさやを、いかに効率よくスムーズかつ丁寧に切り落とすことができるのか、己の実力のほどを示せと言われているのである。
キッチンばさみを握る手に力が入る。そして、枝豆を掴んだ指が微かに震える。なんせ、呑気にチョキチョキするのは誰にでもできるが、このわたしに求められているのはスピードであり正確さであり、誰もが圧倒されるようなハサミさばきなのだ。
(やれるのか? 果たしてわたしは、皆のお眼鏡にかなうパフォーマンスを披露できるのか?)
己への未知なる期待と、それが叶わなかった際の絶望との狭間で、わたしはゴクリと唾を飲み込んだ。——やるしかない。
こうしてわたしは、猛スピードでさやを分断し始めた。最初はテーブルに肘をつきながらカットしていたが、そのうち両肘を浮かせて手首のスナップを利かせながら、微妙な角度を維持しつつカットした枝豆をボウルへと放り投げた。
それは自らの目を疑うほどの、驚異的なスピードだった。わたしの前世は、さやを切り落とす職人だったのではないか?——そう思わずにはいられないほどの見事な手さばきを見せるわたしは、「転職」という文字が脳裏をよぎった。
そして、わりと早い段階で発見した「ジョキッ、ポンッ!」というリズムを繰り返すことで、無駄な間合いをとることなく淡々と枝豆カットが実行された。しかも、なんというか楽しいではないか。楽しいからこそ苦にならず、楽しいからこそもっと楽しめるように工夫をするのである。
(あぁ、とうとう天職と出会ってしまったのだ!)
だが、そんな幸せな時間も長くは続かなかった。あっという間にレジ袋は空になり、隣りに置かれたボウルには山盛りの枝豆が積まれていた。
——終わった。
枝豆の終了とともに、わたしの「天職の夢」も終わりを告げた。
(もしも生まれ変わったならば、今度こそ、枝豆職人になろう)
心の中で密かにそう誓うのであった。
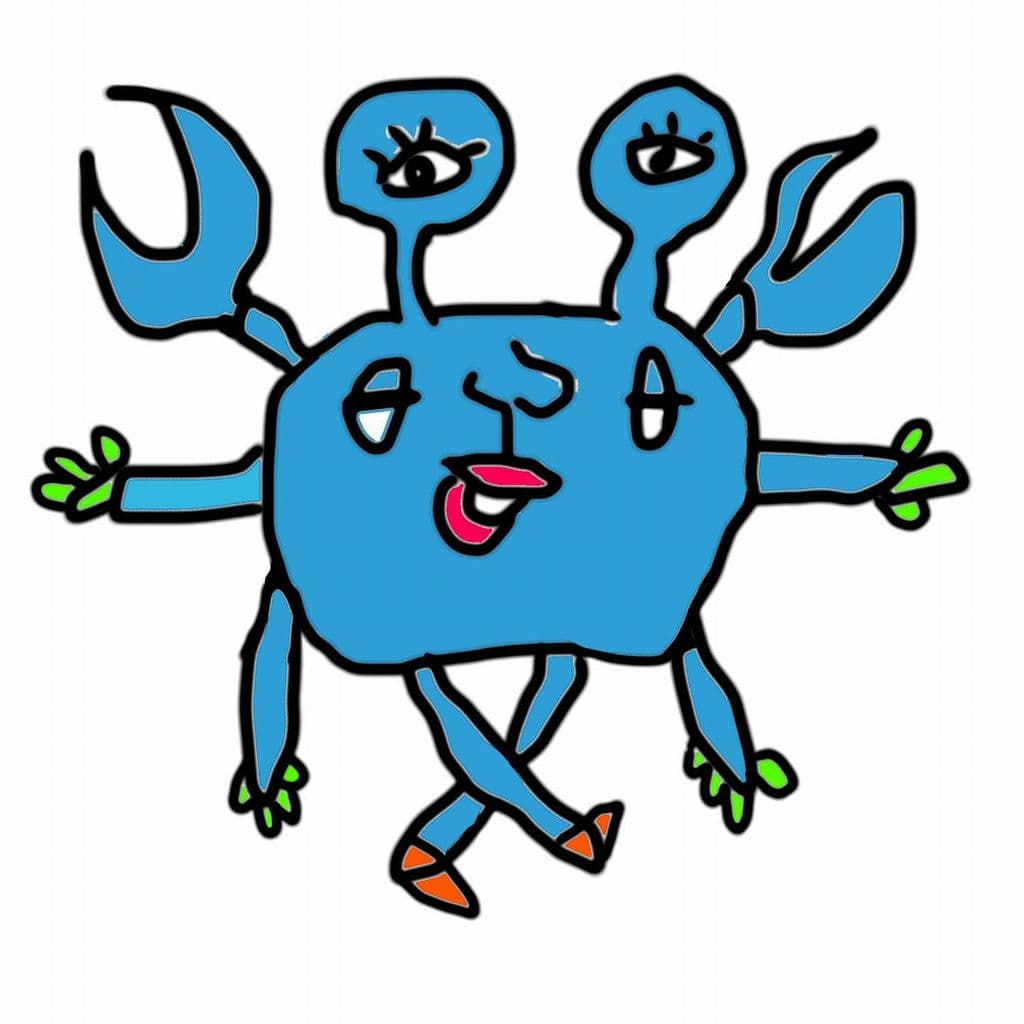


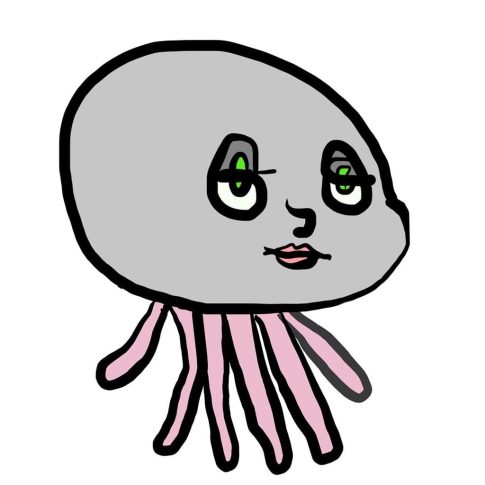

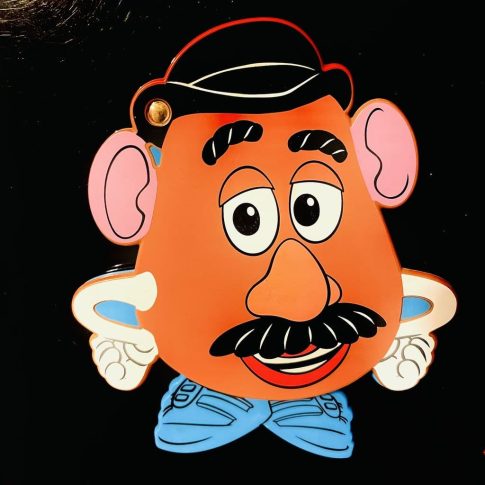















コメントを残す