社会人になってずいぶん経つが、仕事終わりに飲むビールが、こんなにも美味いものだとは知らなかった。しかも終わりの見えない絶望的な作業が、完結せずともある程度の形にできた頃、あるはずのないビールが目の前に現れた驚きと感動は、筆舌に尽くしがたいものがある。
そもそもアルコールなど好んで飲まないわたしが、時と場合によっては目を輝かせてビールをグビグビ飲み干すなど、自分を含む誰もが予想だにしなかったわけで、だからこそ余計に、この黒い缶ビールは美味かった。
*
自分のミスならば、こんな気持ちにはならなかっただろう。いや、そもそも小心者のわたしは、こんな雑で出鱈目な仕事はできない。
少なくともクライアントからカネをもらっている以上、完璧とはいえなくとも最低限の結果を出さなければならない。士業とはそういう性質の職業だからだ。
それでも、元からの能力が低かったり何らかの原因で精神的に病んでしまったりと、人間たるもの順風満帆にいくとは限らない。だからこそ、仕事仲間のような存在がいると心強いのだ。
わたしは社労士だが、弁護士や税理士の仕事を手伝うこともある。もちろん、専門的な業務は手伝いようもないが、たとえば、書面の校閲や証憑の整理ならばわたしにもできる。
猫の手も借りたいほど切羽詰まった状況ならば、たとえちょっとのことでも強力な助太刀となるのだ。
こうしてわたしは、夜の7時半から「他人の尻ぬぐい」を開始した。数百枚、いや、数千枚もの証憑の山を前にして、もはやゴールがどこにあるのかすら分からなかった。
この果てしなく高い山を、登りきることなどできるのだろうか――。
考えても仕方がない。とにかく一枚ずつ捌くしかないのだ。
段ボール箱に手を突っ込むと、当りなど入っていないくじを引くかのように、ガッサリと証憑を握りしめて持ち上げた。そして、それらに記載された宛名と支払年月日さらに但し書きを確認し、一つ一つ費目ごとに仕訳けていった。
やってみて分かったことは、数年分の証憑ゆえに期日の記載が西暦と令和とでごっちゃになることだった。「令和2年って、西暦何年だ??」何度聞いても忘れてしまうわたしは、付箋に大きく西暦と和暦を赤ペンで記して、怪しくなるたびにチラチラと盗み見した。
さらに進めていくと、証憑を手に取った時点でどこの店舗か、あるいはどこの取引先かが分かるようになった。なんというか、それぞれの独特なオーラを感じるようになるのだ。分かりやすい例えとして、タクシーや駐車場の領収書が挙げられる。タクシー会社の独特なフォントとサイズ感だったり、駐車場によくある紙質(裏面が磁気化されているなど)だったりと、手にした瞬間に「旅費交通費」の山へとパスすることができるのだ。
そんなこんなで冗談抜きに脇目も振らず、一瞬も休むことなく作業に没頭した。飲まず食わずでトイレにもいかず、無駄口を叩くこともスマホに目をやることもなく、ただひたすら膨大な紙の山を小さな塊に変えることだけに集中した。
あえて時計も見ずに全力で駆け抜けたわたしは、ようやく段ボール箱の底を見ることが叶った。そしてその時、心の底からこう思った。
(道は辿るものではない、自ら切り拓くものなのだ――)
*
下だけを見続けたせいで首が痛い。目を大きく見開き続けたせいで目が乾く。「卓上かるた大会」に出場したかのように、前かがみを続けたせいで腰は悲鳴をあげている。
やったことは軽作業だが、結果としてかなりの重労働と同等の疲労感が残った。そしてこれは、明らかに肉体労働だったといえる。加えて、精神的に追い込まれた状態での「かるた取り」は、必要以上に心身への負担が大きかった。
ふと時計を見ると、なんと深夜2時半を過ぎていた。わたしは実に7時間もの間、一心不乱に証憑の山と戦い続けたのだ。
さすがに、4時間くらいは経過しただろうと思っていたが、まさか一日の四分の一強を単純な軽作業かつ肉体労働に費やしていたとは、驚きを通り越して呆れてしまった。
「飲む?」
惚けたわたしの目の前へ、同じく作業を行っていた仲間が黒い缶を突きつけてきた。――エビスビールだ。
そんな「まさかの労い」にわたしは驚いた。なぜならここは弁護士事務所で、まさかビールの備蓄があるとは思わなかったからだ。ついでに、山盛りのお菓子やおつまみまで出てくるではないか。
ビールなど飲む習慣のないわたしだが、今日ばかりはグビグビと喉を鳴らして飲み干した。エビスビールだからか、それともいい具合に冷えていたからかは分からない。だが、仕事終わりの缶ビールがこんなにも美味いものだとは、これっぽちも知らなかった。
*
こうして、ようやく帰宅した頃には朝日が顔を覗かせていた。ブラインドの隙間からは白々とした爽やかな光が差し込んでくる。
今日の作業は単にスタートを切ったにすぎず、前途多難であることに変わりはない。それでも、さっきまで感じていたドロドロの疲労は消え、最後まで戦い抜くだけの気力が蓄えられたように思うのだ。



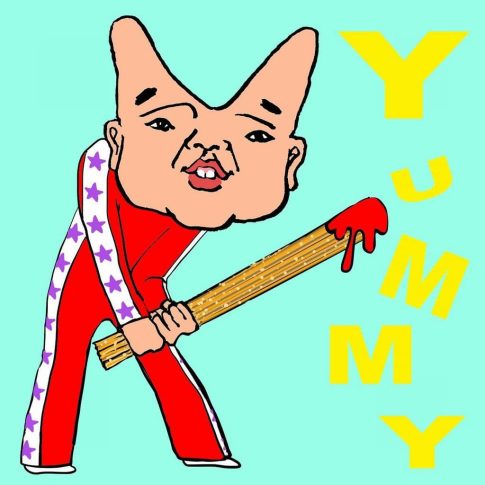

















コメントを残す