本日、所用で某専門学校を訪れた。
在籍中の後輩と行動を共にしたが、やはり学生が集まる場所というのは活気があっていい。しかもその活気は、社会人にありがちな表面上の薄っぺらい活気ではなく、若者から放たれるリアルな生気というか、本当に「今を楽しんでいる感」が伝わってくる。
卒業前の試験が目前に迫る中、多くの学生が居残りで試験勉強に取り組んでいる。しかしよくよく観察すると、参考書を開いて勉強をしている生徒はおらず、みんな思い思いの行動をとっていた。
3~5人ほどのグループでかたまり、スマホをいじりながら談笑をしたり、そうかと思えば連れだって食事に出かけたりと、勉強をすると見せかけて、友達との楽しい時間を過ごすためにここにいるのだ。
だがこれこそが、学生にとっては正しい時間の使い方といえる。どんなに勉強が嫌いでも、時が来れば渋々取り組むわけで、そこまでのバッファーはギリギリまで使い果たすのが、学生の本領発揮すべき分野だからだ。
*
思い返せば学生時代、全盲の父と片目が見えない母という家族構成で育ったわたしは、とにかく「視力最優先」の生活を余儀なくされた。「目が悪くなるから」と、テレビを見ることは許されず、勉強さえもあまり推奨されない徹底ぶりだった。
「テストの点数はどうでもいいから、勉強をしすぎて目が悪くなることは避けなければならない」
という教育方針の下で、思春期のわたしはつまらない毎日を送っていたのだ。
しかし学校では、まるで義務であるかのように多くの生徒が学習塾へ通っていた。
さらに、小・中学生が夜出歩くということは「望ましい行動ではない」とされる時代だったため、塾云々よりも「夜、外出できること」がカッコいいしうらやましかったのだ。そこでわたしも、なんとかして夜遊びに参加しようと頭をひねった。
テスト用紙を親に見せる習慣はなかったが、点数だけはおよそ報告していたため、ある日わたしは親に嘘の芝居をした。
「今回のテストでひどい点数を取ってしまい、このままでは授業についていけない。だからぜひとも塾へ通わせてほしい!」
わざわざ嘘をついたのには理由がある。少し前に塾へ通いたい旨を伝えたところ、
「塾へ通わなければならないほど、勉強はしなくていい」
とバッサリ斬られたことがあった。そのため、なにがなんでも塾通いを達成するべく、「授業にすらついていけないほど、勉強ができないアピール」を敢行したのだ。
・・・案の定、両親は塾通いを許可した。
こうしてわたしは、学校から帰ってくると少し離れた場所にある塾まで、週に3回ほど自転車をこいで通うようになった。
塾での楽しみといえば、案の定「おしゃべり」だ。授業が始まるまでの時間や、授業と授業の間の休み時間など、他校の生徒たちと談笑するのが何よりも楽しみだった。
いつまでもダラダラとしゃべれる環境ではないからこそ貴重な時間であり、くだらない内容でも面白く感じるのだろう。そして先生が教室に入ってくると、ガタガタと座席に戻り参考書を開くわけだが、そこまでのわずかな自由時間を満喫するために、わたしは塾へ通っていたのだ。
夜9時ころ、塾が終わると各々が帰路に就くため自転車に乗って散っていく。
しかし数名の友人とあらかじめ申し合わせて、近所のコンビニで落ち合う約束をしていた。そこでまた、アイスを食べながらしょうもない話で盛り上がるのであった。
無論、親には
「先生に質問してから帰るので、30分くらい遅くなる」
と、もっともらしい嘘をついているので問題はない。
授業の合間も塾後のコンビニも、生きる上で利益となる話をするわけでも、人生を左右するほど重大な相談をするわけでもない。昨日見たテレビの内容や気になる男子の話、先生や親の悪口からの晩ごはんのメニューといった、どうでもいい話題ばかりが延々と続くだけなのだ。
それでも、わたしにとってはその「しょうもない会話」が楽しくてしかたなかった。兄弟がいないからだろうか、少しでも長く同年代の友達と話をしていたかったのだ。
*
しばらくすると、食事に出かけていた学生の集団が戻って来た。後輩のクラスメイトらしく、こちらへ寄ってくると卒業式について話していた。そこから話題がそれて、これまたどうでもいい会話が始まった。
――ま、これこそが青春ってやつだろう。









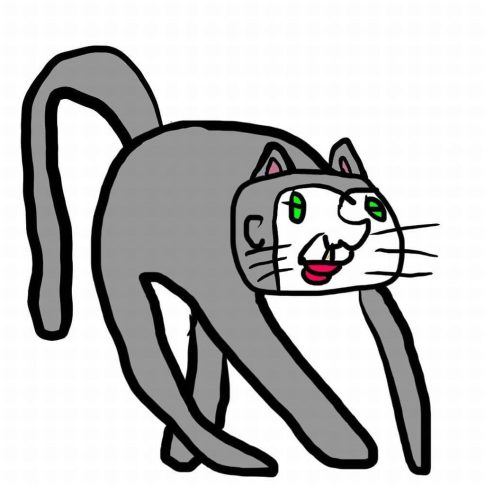











コメントを残す