力強くも美しい嬰へ長調のサブドミナントが鳴り響いた瞬間、わたしは涙をこぼすとともに「あぁ、終わってしまった」とつぶやいた。
心を揺さぶられるほどの感動を与える演奏だったのだから、当たり前にファイナル進出となるだろう。にもかかわらず「牛田くんの演奏はこれが最後だ」と、どこか胸が締め付けられる思いに駆られたのであった。
*
ピアノを聴くことに関して、素人に毛の生えた程度の感性しか持ち合わせていないわたしだが、5年に一度のショパンコンクールだけは睡眠不足の代償を払ってでも視聴することにしている。
そもそも、コンクールの様子をオンライン配信する仕組み自体、かなりレアで柔軟な対応といえる。皮肉にも、コロナ禍が生んだ”価値ある変革”がコレなのだから、手放しに喜べないのも事実。とはいえ、これまではワルシャワ国立フィルハーモニーへ足を運ばなければ、リアルタイムで聴くことのできなかった演奏を、オンラインとはいえ同時に鑑賞できるのだから画期的である。
そんなわけで、第19回ショパン国際ピアノコンクールの三次予選(セミファイナル)の演奏を、スマホ越しに視聴していたわたしは、日本代表の一人である牛田智大くんのソナタ3番のフィナーレに胸を打たれた。
およそ1時間にわたる長い物語の終焉を、ショパンの晩年の大作ともいえるこの曲で締めくくる・・という豪華なプログラム構成も見事だが、なによりも演奏そのものが圧巻だった。
牛田くんといえば、幼少期から「天才少年」ともてはやされ、メディアからステージから引っ張りだこの人気ぶり。無論、実力が伴っているからこそだが、そんな彼が満を持して挑んだ前回のショパンコンクールでは、まさかの二次予選止まりに終わった。
その敗因について、本人がXにてこう分析している。
「今回はなかなかホールの音響がつかめず、最大音量を見極められないままラウンドを終えてしまい、ダイナミクスの構成や音色の調整が狂ってしまいました。ホールの音響上自分の音量が足りていないのではと錯覚してしまい、不自然な力で芸術的でない飽和した響きを引き出してしまった瞬間がありました。」
「また、響かないホールで無理やり音量を出すために、バスや最も重要な音を少し遅らせることで倍音の効果でピアノが鳴っているように聞こえさせることができるのですが、これをホールの音響を探るうちに無意識に多用してしまっていたようです。」
「計算違いが重なり想定していたものとはかなり違った音楽を提示する形になってしまいましたが、自分にとっては準備の過程のなかで作品についての勉強をたくさんさせていただけたことが、かけがえのない経験と財産となりました。」
あれから4年——。26歳を迎えた牛田くんは、ショパンをより深く学ぶべく、ワルシャワにある「フレデリック・ショパン音楽大学」に入学した。そして、ショパンの祖国にて音楽を学び、日常生活や文化に触れ、身も心もショパンを染みこませた彼の演奏は、まさにショパン本人のものであるかのように聞こえた。
そんな非の打ち所がないセミファイナルの演奏で、たった一つ不安があるとしたら——演奏時間だった。コンクールの規定によると、「45〜55分のリサイタルを行うこと」とされており、この時間内で収まるプログラムでなければならないが、ラストとなるソナタの第4楽章を弾き始めた頃、演奏時間は54分を超えていた。
言うまでもなく55分で終わるはずがない。どう頑張っても、時間内に最後まで弾ききることなど不可能なのだ。
それでも牛田くんは、魂をこめた渾身の演奏を続けた。ダイナミックでありながらも丁寧で緻密な音色——決して雑味や粗っぽさを感じない、それどころか繊細かつ上品なピアノフォルテを途切れることなく放ち続けた。
それにしても、これほどまでに感情をむき出しにした彼を、少なくともわたしは今までに見たことがない。ピアノを弾くということは、内面にある想いを音にして表すことなのだ・・という理屈が、彼を見ているとよくわかる。
そして、この壮大なショパンの物語を終わらせるためには、演奏時間というルールを破ってでも繋げなければならない使命がある。そもそも、ギリギリの時間配分となるとうな構成にしなければよかったのに、なぜあえてそこへ挑戦したのか——どうしても表現したいショパンが、そこにあったからだろう。
そんな彼のショパンに対するリスペクトと愛情が、55分という時間を過ぎても刻々と続いたのである。
ちなみに、ショパンコンクールには年齢制限がある。予備予選の時点で16歳から30歳までという、限られた年代のピアニストだけが参加できるコンテストなのだ。そして牛田くんは今年26歳・・というか、セミファイナル当日に26歳を迎えた。まるでショパンに祝福されているかのような偶然のスケジュールだが、だからこそ彼にとっても特別な一日となったのではなかろうか。
そしてこれは、今回が最後のチャンスであることを意味する。彼はもう二度と、ショパンコンクールに参加することはできないのだ。
サッカーのワールドカップは2年に一度、オリンピックは4年に一度開催される。毎年ではないからこそ、「また来年頑張ろう!」などと軽々しく言えない重圧があるわけだが、対するショパンコンクールはそれらよりもさらに長い5年に一度しか開催されない。加えて年齢制限もあることから、コンテスタントたちはまさに20代という貴重な時間を懸けて、この大会に挑むのである。
そんな、「また次回」が存在しない牛田くんのラストの演奏は、なおさら涙を誘うのであった。願わくば、ファイナルでピアノコンチェルトが聴きたい——。
そんな祈りも虚しく、わたしが「終わってしまった」と感じた一番の理由は、彼の演奏に心の底から感動してしまったことだ。
これは個人のリサイタルではなく、審査員が目を光らせているコンクールである。そして、歴代の優勝者の演奏を思い返すと、圧巻の演奏ではあるが涙を誘うような感動の仕方はしなかった。今回も、ファイナルへ進出したコンテスタントの演奏はどれも素晴らしかったが、どちらかというと「なるほど」「さすがだ」という印象——すなわち、安定した完璧さがファイナリストたる演奏であるように感じたのだ。
だがわたしは、奇しくも牛田くんの演奏に心を打たれ涙をこぼしてしまった。ショパンではなく、牛田くんに感動してしまったのだ。
*
ヒトには誰でも今日まで紡いできた人生があり、その背景を知れば知るほど情が湧き人間味を増すもの。そして、それらを度外視して審査員に音楽を示せた者が、コンテストで優勝できるのだろう。
だがそれは、必ずしも上手い下手の範疇に留まらないのも確か。セミファイナルにて人生最後のショパンコンクールを終えた牛田くんの60分に、どのピアニストよりも深い信念と尊敬、そして誠実さを覚えたのは事実。
ファイナル進出からの優勝・・という完成形は幻となったが、永遠に未完成というのは、ある意味完成したのと同じである。例えるならば、壮大な満月よりもちょっと欠けた三日月に風情を感じるような——。
なんとも切ない、にもかかわらず圧倒的な演奏が、未だに耳から離れないわたしなのである。





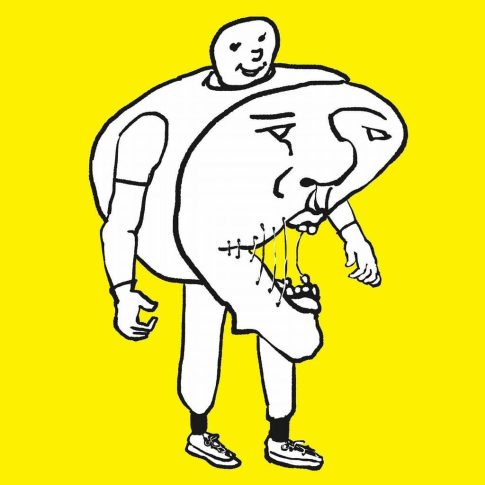



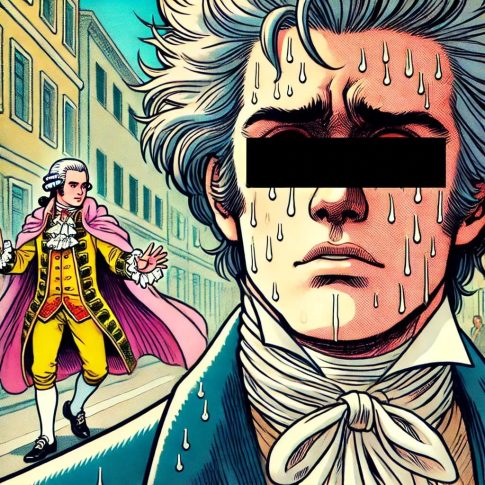











コメントを残す