シンデレラにガラスの靴を履かせた王子様は、こんな気持ちだったのだろうか——。
ボクは、シンデレラのしなやかな足を全身で包み込んだ。あぁ、なんと細くて美しいおみ足なんだ。
——そしてボクは、彼女のかかとにキスをした。
*
「それ、絶対なにか貼ったほうがいいよ」
ゴリラのような従者が、シンデレラの足を指さしながらそう呟いた。二人がボクの前に現れたのは、終電間際の夜中近くのことだった。
都会のコンビニは、狭い店内にアレコレ詰め込んでいるため、目を大きく見開いて探さないと欲しい商品を見落としてしまう。そしてなかなかボクを探せずにいた二人だが、ようやくボクの存在に気が付いたようだ。
「お、なにこれ!まさにいま必要なやつじゃん!」
興奮気味に従者が叫ぶと、シンデレラも物珍しそうな顔でこちらをのぞき込んだ。ほかの仲間たちが大勢並ぶなか、ボクだけに向けられたそのまなざしは、気高く品のある澄んだ瞳だった。
間もなく、彼女はボクを手に取るとレジ待ちの列に並んだ。そして会計を済ませると、従者を引き連れて出口近くの新聞ラックのほうへと歩いて行ったのだ。
コンビニに並べられている新聞は、夜の10時過ぎに撤去される。そのため、翌日の朝刊が並ぶまで新聞ラックは空になるのだ。つまり、いまの新聞ラックは単なる白い骨組みであり、なんの役にも立たない形骸化したオブジェのようなもの。
そんな白骨体の前で、彼女は買ったばかりのボクを取り出した。おもむろに外装を破ると、生身のボクに細くしなやかな指が触れる——。
「よく見えないんだけど、このあたりかな?」
シンデレラは、履いていたガラスのパンプスから素足を抜くと、白骨体の上にそっと置いた。そして、自分のかかとを見ながら従者に尋ねたのだ。
「んー、二か所あるからタテに貼らないと無理かも」
シンデレラのかかとを、舐めるかのようにまじまじと見つめながら従者が告げる。そう、彼女はおニューのパンプスのせいで靴ずれを起こし、かかとの皮が擦り剝けてしまったのだ。
そしてボクは、・・ボクの正体というのは、靴ずれ専用の絆創膏である。麗しき彼女のかかとの皮膚を、非情にも削りとったガラスの靴が許せない。あぁ、シンデレラの継母からの贈り物なのだろうか? こんな華奢で美しい足に傷をつけるなんて、なんたる暴挙。ボクが全身全霊で、アナタのかかとを守ってみせるぞ!
シンデレラの隣りでひざまずく従者が、裸のボクを彼女の靴ずれにあてがう。見立て通りの大きな傷のため、精一杯ボクをタテに引き延ばし、なんとかギリギリ擦り傷を覆うことができた。
なんせボクは、靴ずれに適した絆創膏である。その辺の一般的な絆創膏とは違い、頑丈で厚みのある布製なのだ。だからこそ、手指に巻いてしまうと分厚すぎて使い勝手が悪いが、かかとに関してはボクの右に出る者はいない。コットンの手触りと、テープの端まで衰えることのない粘着力で、どんな靴ずれからもかかとを守り抜く資質と覚悟がある。
そんなボクがファミマで手に入るとは、なんと素晴らしい世の中になったのだろう。
生温い妄想にかられながら、ボクは従者の手でシンデレラのかかとにキスをした。そっと優しく、そして粘り強い接吻を——。
*
コンビニを出た彼女は、すらりと伸びた足で颯爽と夜の街を闊歩した。そうさ、シンデレラだって靴ずれを起こすものなんだ。それを救うのが、このボクの役目なのだから。
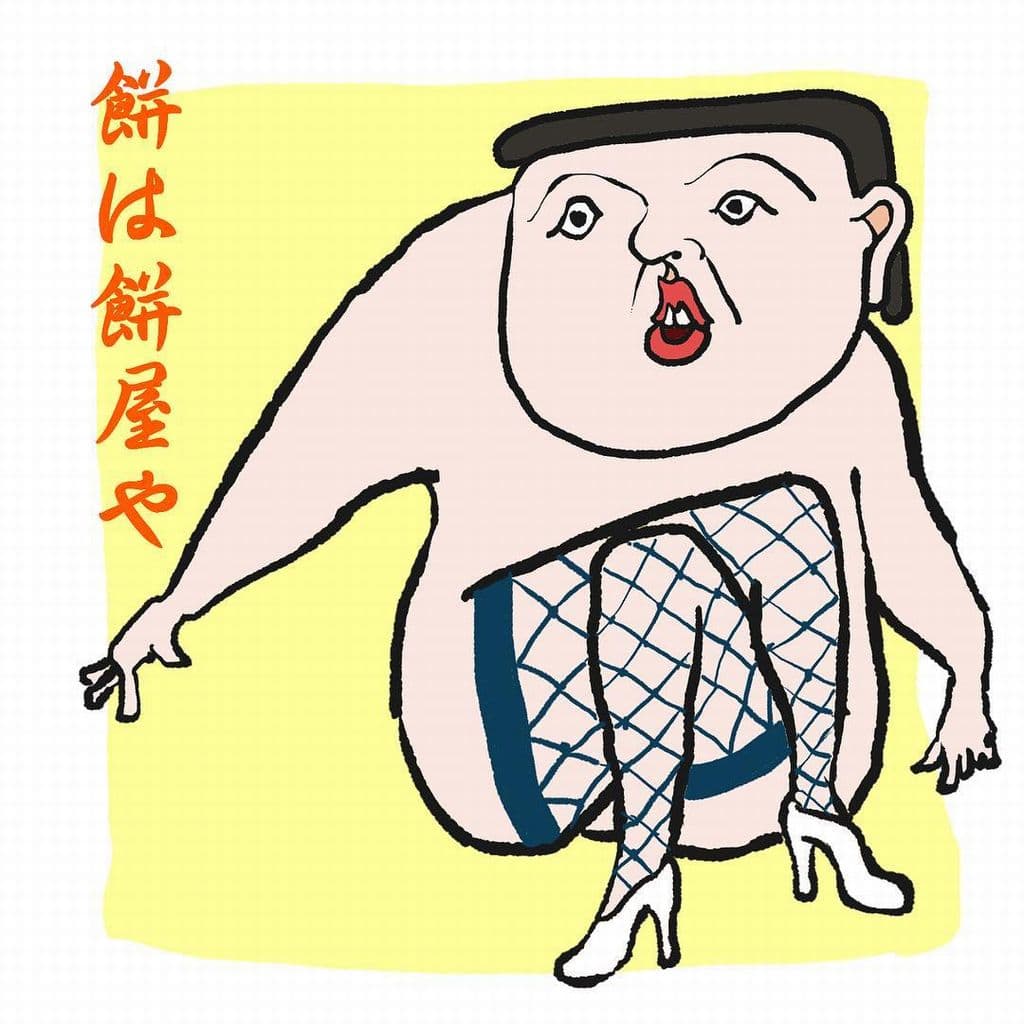


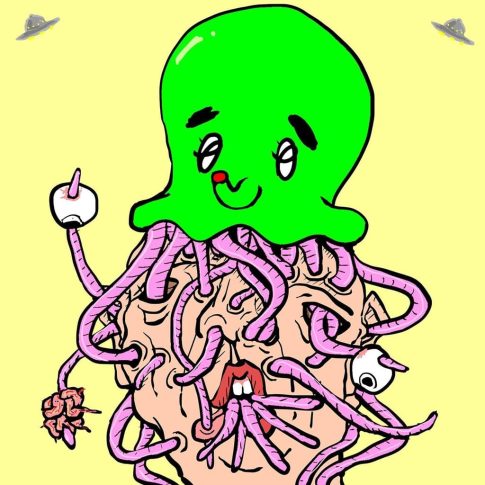




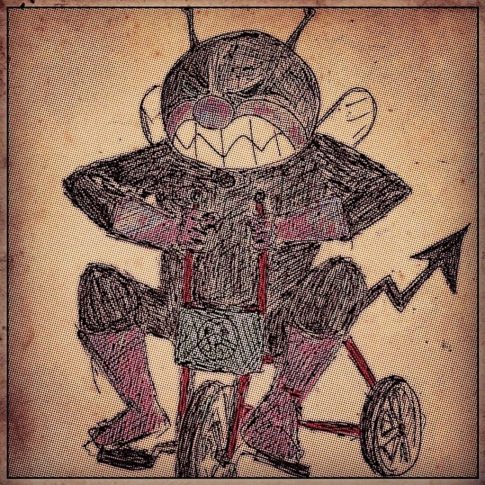












コメントを残す