裏原宿をぶらぶらと歩いた。久しぶりというか、久しぶりでもないというか、レインボーパンケーキを目指してここを訪れたことはあるが、ただぶらぶらと歩いたのは学生以来だろう。
*
それにしても表参道沿いは、表参道ヒルズを筆頭に華々しいエリアに生まれ変わった。
「あぁ腹が減った。中華料理でも食べたいな」と思いながら、外苑前から表参道まで歩いてみたが、そこからさらに裏原宿まで強制的に歩かされたほど、下町の中華料理店的な飲食店は一つも見当たらなかった。
不思議なことに、表参道沿いをどれほど見回してもわたし好みの小汚い料理店はない。それどころか飲食店が圧倒的に少ないのだ。
ルイヴィトン、プラダ、シャネル、アルマーニ、ハリーウィンストン、マックイーン、ウブロ。透け透けのガラス越しに中をのぞくと、細くてスラっとしたイマドキ男子が立っている。しかも店員全員が全員とも、スラっとしているから驚きだ。
(これは間違いなく、フォルムで採用を決めているな。雇用機会均等法に抵触する恐れがある!)
いやいや、それでいい。言っちゃあなんだが、ハイブランドの店員がずんぐりむっくりでは、ブランドイメージを損ねるだけでなく顧客の足も遠のくだろう。有名ブランドのフロアに立ちたければ、細長い手足と9頭身の体を手に入れなければ、その夢は叶わないのである。
それにしても、どこもかしこもオシャレでハイセンスな建物で埋め尽くされている。道を歩く若者でさえ、別の人種であるかのような自信と輝きを放っているわけで。
(わたしにも、こんな時代があったんだよな)
お上りさんのようにキョロキョロしながら、わたしは旧渋谷川遊歩道路、いわゆるキャットストリートを右折した。
*
「オネエサン、ちょっといいですかぁ?」
その昔、芸能事務所を名乗る胡散臭いオッサンやファッション雑誌の取材班などが、スタイルのいい女性や奇抜なファッションの若者に声をかけては、名刺を渡したり写真撮影をしたりしていた。
そこでわたしも、今か今かと声を掛けられる瞬間を待っていた。モデル事務所は無理だが、ファッション雑誌ならば望みもあるだろう――。
しかし待てど暮らせど、あいつらは声を掛けてこない。わざわざ目の前をウロウロしてやってるにもかかわらず、タイミングを逃しているじゃないか。どんくさいな。
そんなことの繰り返しで、これまでにスカウト的な人間から声を掛けられたことは一度もない。いや、正確には一度だけあった。しかし場所は裏原宿ではなく、水道橋だった。
「ちょっといいですか?」
明らかにスカウトマンではない。幸薄げなオバハンだった。これでAVのスカウトだったら面白いが、死んだ目をしているから違うだろう。
わたしの魅力、いやセンスに気付くのがこんなオバハンというのはいささか悲しいが、それでも誰一人として見つけられなかったのだから、その点だけは褒めてやろう。
信号待ちをしていたわたしは、横から声をかけてきたオバハンをチラ見した。
「あの、じつは・・・」
なんだかもったいぶった言い方で、もじもじしている。なんだよ、早く言えよ気持ちわりぃな。
「て、手相を見せてもらえませんか?」
*
裏原宿をぶらぶらしていると、いまだにスカウトマンがうろついている。もはや、こんな太々しい中年に声を掛けてくる人間などいない。たとえ手相占いであっても、今のわたしには見向きもしないだろう。
関係ないが、香港の繁華街を歩いていたときに、ビラかティッシュを配る男性がいた。誰彼構わずというより、ある程度選別しているように見えるが、どういう区別をしているのかは分からない。
それでも、なんとなく若くてイケてる女性に配っているように見えたので、わたしもそれなりに覚悟を持って通り過ぎようと決めた。そしていよいよ、その瞬間がきた。
――が、言うまでもなく素通りさせられた。
込み上げる気持ちを抑えながら、わたしは二、三歩進んだところで踵を返した。そしてその男の前に立つと、胸ぐらをつかみそうな勢いで問い詰めた。
「なぜわたしの時だけ、手を引っ込めた?」
無論、男はあたふたしながら去って行った。
・・・道というのは、ただぶらぶらと歩くのが精神衛生上ちょうどいい。
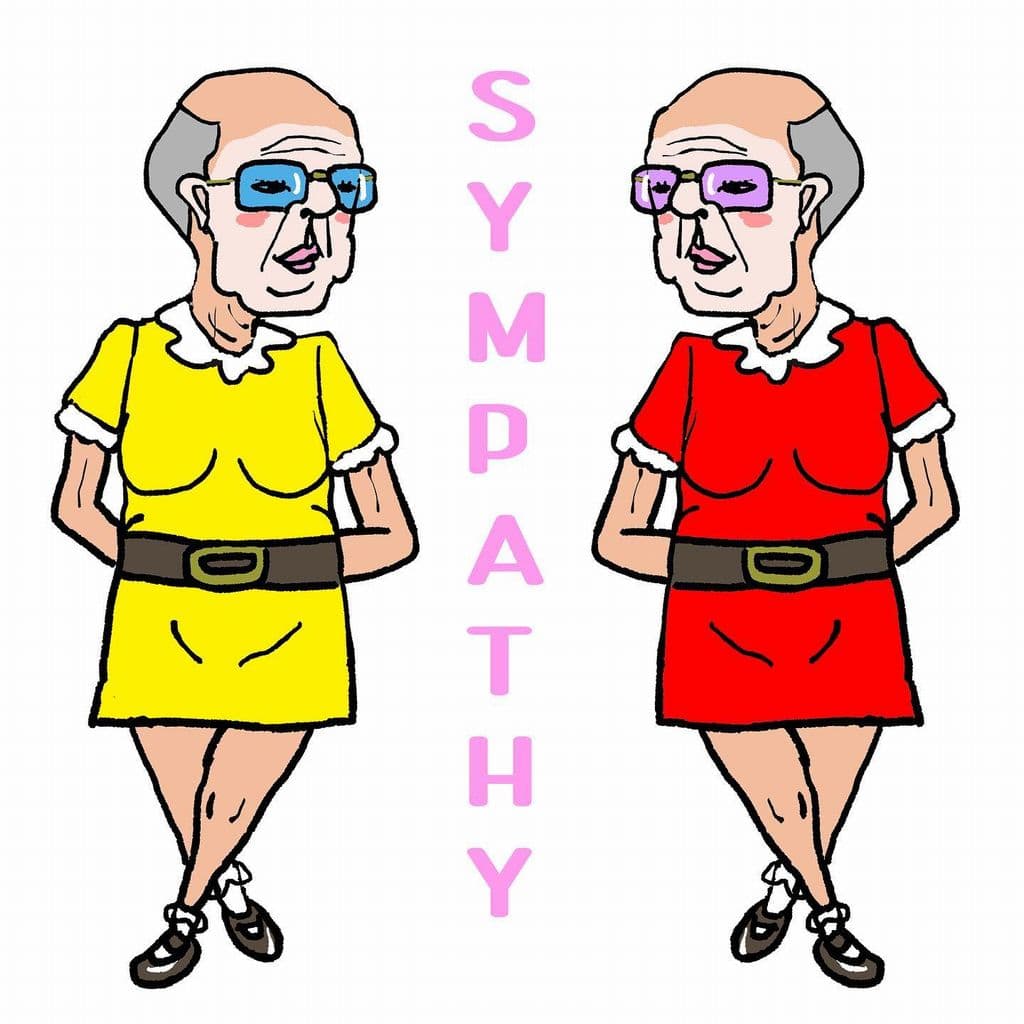


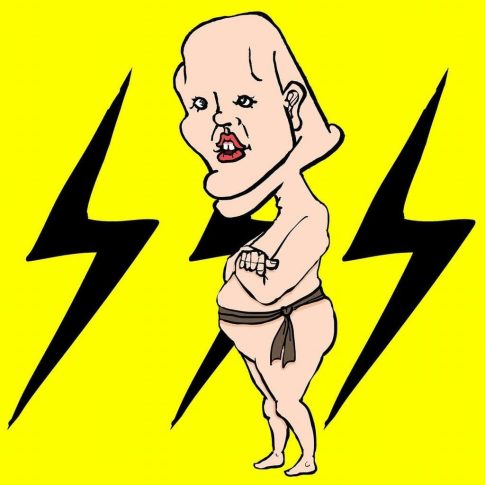

















コメントを残す