「この感じだと、いったん除去してからでないと入れられないですね」
わたしの眉毛を凝視しながら、美容外科のナースがしみじみとつぶやく。
そう、わたしの眉毛は15年前にアートメイクを施してあるのだ。そして15年経った今でも、きちんと眉毛として存在感を放っているのである。
「アートメイクって、数年で薄くなるんじゃないの?」
その通りだ。日本が誇る繊細で美しいアートメイクならば、2年もすればリタッチが必要となるだろう。
だがわたしの眉毛は、何を隠そうメイドインコリア。美容大国・韓国のクオリティーでできているため、15年経ってもびくともしないのだ。
(・・・いや、これはアートメイクではなくタトゥーだろう)
*
あの当時、格安でアートメイクや脱毛、二重まぶた、豊胸、脂肪吸引などができるとあり、日本人はこぞって韓国へと押し寄せた。
そして友人に誘われたわたしは、さほど興味はなかったが断る理由もないため、友人とともにソウルを訪れた。
ビルが丸ごと美容クリニックで、すべての施術が即日可能という、驚異のスケジュールがウリの韓国美容業界の実態。
中には会社の昼休みに、二重まぶたの施術に訪れる女子もいるらしい。
午前中は一重まぶたで、昼休みが終わったら急に二重になっている――。
そんな光景も、韓国では日常茶飯事なのだろう。さらに、顔面にガーゼや包帯を巻いた状態で、平然と闊歩する女性がチラホラ見受けられるなど、美容整形に対する民度と文化の違いを見せつけられるのである。
友人の脂肪吸引を待つ間、わたしは眉毛とアイラインのアートメイクで時間つぶしをすることにした。
日本円で2万円程度の格安価格でできるとあり、これは多少失敗してでもやる価値がある!と思ったわけだ。
施術担当者は「オモニ」の理想像のような、かっぷくの良いオバチャン。決してセンスのいい雰囲気は感じないが、韓国の美容レベルは世界一である。よって、見た目で決めつけてはならない。
こうして、オモニに顔面を委ねたわたしは、静かに表面麻酔が塗られる瞬間を待った。
「チョトゴメンナサイ、マスイキレテル。ドウスル?ガマンデキル?」
突然、オモニが話しかけてきた。どうやら、本来塗るべき表面麻酔の軟膏が切れているらしい。アートメイクを諦めるか、麻酔なしで傷みを堪えながら施術を受けるか、究極の選択を迫られているのだ。
(ソウルまでやってきて、麻酔ごときで格安アートメイクを断念できるはずがない!)
痛みなど一瞬の出来事である。女は度胸、針で突かれる痛みごときで弱音は吐くまい。わたしは笑顔で、麻酔なしで施術を行う決意を告げた。
するとオモニはニッコリ微笑みながら、
「ゴセンエンニマケトクネ」
と、値引きを約束してくれたのだ。眉毛とアイラインが五千円とは、これは何が何でも耐えなければなるまい。
そしてオモニはマシンの電源を入れた。
静かに目を閉じ、痛みに備えるわたし。痛いといったって、ちょっと皮膚の表面を削る程度のことだ。擦り傷などしょっちゅう経験しているわけで、騒ぎ立てるほどのものではない。
そう自分自身に言い聞かせているうちに、いざ、マシンの先端に取り付けられた針が、わたしの眉骨に触れた。
ブィィィン
予想通りの痛みが走る。痛すぎるわけでもなければ、痛くないわけでもない。ただただ、想像していた痛みと同じくらいの痛みが、眉骨辺りで発生しているのだ。
そもそも、痛いのは当たり前のことである。眉毛を描く手間を減らそうと、いわば「ラクをするため」にこうして施術を受けているのだから、痛かろうがなんだろうが文句をいう立場ではない。
ましてや、針で傷つけた皮膚にインクを流し込んで色素を定着させるのだから、小さな擦り傷やささくれ程度でも「痛い!」と騒ぐ輩が、この状態で痛くないはずがない。
つまり、痛いのは当たり前なのだ。むしろ痛くなければおかしいだろう。そうだ、痛くていいのだ。痛みを感じることこそが、正しい反応なのだ!
こうして、気を失いかけては魂を奮い立たせ、なんとか眉毛の施術が終了した。
「ダイジョブ?」
さほど心配していない表情のオモニが問いかける。わたしは黙ってうなずいた。
――とにかく早く終わらせてくれ。次のアイラインは、まつ毛の間を埋める作業になる。軽く粘膜にも触れるだろう。それが痛くないはずもなく、明らかに眉毛よりも痛いことが確定している。だからこそさっさと終わらせてくれ。時間との勝負なんだ。
半分涙目のわたしは、決死の覚悟でギュッと目をつむった。
ブィィィィン
(熱っ!!!!!!)
まつ毛の間にロウを垂らされたかのような、ものすごい熱を感じた。そうか、電動の針でつついているから、痛みが熱さのように感じるのか。
ブインブインと細かく刻まれるマシン音。まつ毛の際をキレイに埋めてくれているのだろう。
口を開けたら魂が飛んでいきそうなくらい、痛みを超えた「なにか」がわたしを襲う。
目尻からは涙がこぼれる。こんなもの、我慢しようとして止められるものじゃない。じわっと滲み出る涙が、断続的に地面へと落ちていくのだ。
そしていつしか、意識がほとんど遠のいた。
あぁ、わたしは今いったい何をしているのだろうか?なぜこのような痛みに耐えなければならないのだろうか?
普通ならばこの痛みは味わわなくてもいいはず。なのに、たまたま麻酔が切れていたからという理由で、わざわざ日本からやってきたわたしは、例えようのない激痛、いや、鋭痛を正面から受け止めなければならないのか――。
もはや正気を保つことができそうにない。わたしは発狂寸前のところで、理性を総動員させて当たり前の理屈を反復するのだった。
きっと中世の拷問は、こういう感じだったのだろう。あぁ、わたしが犯してきた数々の悪事を、どうかお許しください――。
「コレデヒヤシテ」
施術を終えたオモニが、ビニール袋にいっぱいのロックアイスを持ってきた。そしてひどく腫れあがったまぶたの上に、そっとのせてくれたのだ。
うなずくことすらできないわたしは、静かに涙を流しながらロックアイスを受け入れた。
神様、ありがとう――。
*
こんな経緯で、わたしは無事に(?)アートメイクの施術を終えたわけだが、今思えば、あれはいわゆる「タトゥー」だったのではなかろうか。
なぜなら、アートメイクであそこまで深くは彫らないからだ。
だからこそわたしのアートメイクは、未だにしっかりと皮膚に刻み込まれているのである。
おかげで、いま流行りの「3Dアートメイク」をやろうにも、この韓国仕込みの眉毛をレーザーで除去しなければ、施術できないというわけだ。
あの痛みが忘れられないわたしは、「レーザー除去」という響きに、心底ビビっているのである。



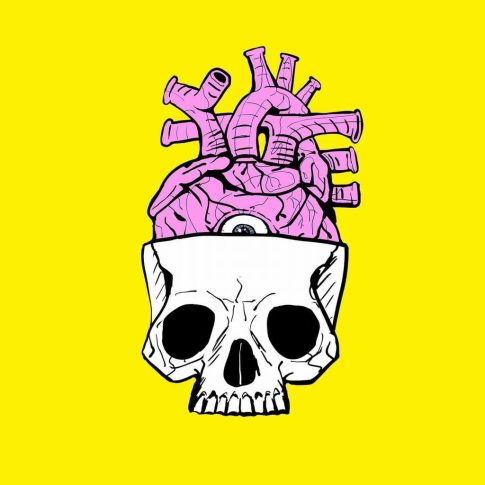

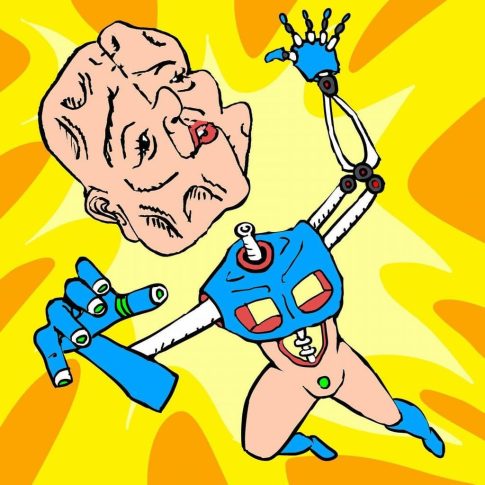




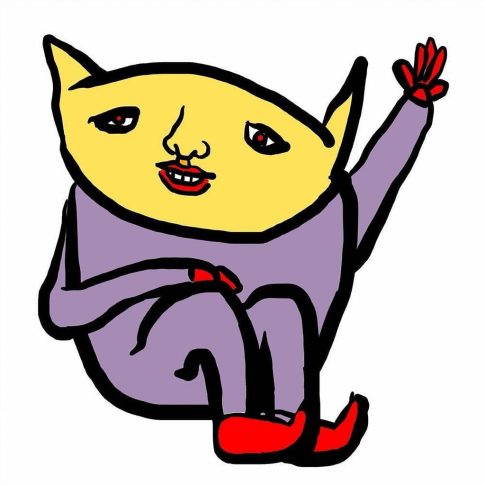










コメントを残す