とあるカフェのテラス席での出来事。
爽やかな青空だが日差しは強すぎず、外でコーヒーブレイクがちょうどいい季節である。紫外線を嫌う女性も多いが、太古から降り注ぐ電磁波は適度に浴びるのが自然といえる。
実際のところ、店内の席が一杯であるため、ここしか空いていなかったというのが本音なのだが。
目の前には、コンクリートでできた大きな円柱状のオブジェが建っている。その周囲をぐるりと、ベンチ代わりのコンクリートが囲っている。
腰掛けるにはちょうどいい高さであるため、子ども連れの母親や犬の散歩途中の飼い主らが、一休みする場所となっている感じだ。
高さ2メートルほどのオブジェの上部には、中学生と思しき女子が2人、胡坐をかいておしゃべりをしている。たまに下界に向かって声をかけており、視線の先には同い年くらいの男子2人が座っていた。
椅子に腰かけたわたしの視線の先に彼ら彼女らがいるため、そのやり取りの一部始終を観察しながら、熱々のドリップコーヒーと焼き芋ブリュレフラペチーノを交互に味うことにした。
男子のほうは学校の課題だろうか、なにやら本を開きながら頭を悩ませている。対する女子のほうは、相変わらずお立ち台の上でおしゃべりをしながら、ケータイをいじっている。
いずれのペアも目の前に人間を置きながら、目線は手元に落としたまま会話を続けており、「相手の目を見て話しなさい!」などというセリフは、もはや化石となりつつあるようだ。
そんなわたしもケータイ越しに彼ら彼女らを眺めているわけで、この世はケータイとセットで成り立っているのかもしれない。
タカトゥッタットゥッタッタ♪
突如、隣りのテーブルからiPhoneでおなじみの着信音が鳴り響いた。音量の大きさに一瞬驚いたが、まぁ普通に誰かからの電話だろう。
・・と思ったが、なぜかその音は鳴りやまない。隣りを見ると、90歳近いおばちゃんらが談笑を続けている。
(オイオイ、電話鳴ってまっせ!)
心の中でツッコみつつ、なぜ電話に出ないのかしばらく見守ってみた。すると30秒ほど経ってから、
「誰かから電話だわね、ちょっと失礼」
と言って、ケータイを左手に、杖を右手に立ち上がり、少し離れたところまで歩いて行った。
なぜしばらく放置したのかは謎だが、着信音は聞こえていたらしい。ということは、きっと、今この瞬間を逃したくないおしゃべりをしていたのだと、結論づけることにした。
5メートルほど離れたところで、我々に背を向ける形で誰かと会話をするおばあちゃん。内容から推測するに、ここで待ち合わせをしていたお友達らしい。
あら、来ないの?そのまま行くのね?・・などという発言からも、きっとそういうことだろう。
中学生らは相変わらず、それぞれが違うことをしながらも、同じ場所で同じ時間を過ごすという青春を謳歌していた。画面越しではなく、手を伸ばせば触れられる距離に誰かがいるということは、とても貴重な時間なのだ。
バシャン!!
またもや隣りのテーブルから物音がした。しかし今度は振り向きたくないような嫌な音だった。なぜなら、わたしの足に液体らしきものが飛び散った感触があったからだ。
咄嗟に「テーブルに残されたおばあちゃんの身に、何かがあったのだ」と感じたわたし。そして、何があろうと狼狽えることなく対処することを誓い、思い切って音のする方向を見た。
するとそこには、呆気にとられるおばあちゃんと、まだ口をつけていないアイスラテの紙コップが倒れていた。テーブルからポタポタと垂れるアイスラテ。隣りの椅子に置かれた買い物バッグにもこぼれている。
「あらあら、どうしましょうねぇ」
そう言いながらわたしと目が合ったおばあちゃんには、動じる様子は一切見られない。たまたま出入口付近にいたわたしは、店内に入ると店員に声を掛けて事情を伝えた。
とりあえず紙ナプキンを10枚ほど引き抜いておばあちゃんへ手渡したところで、電話が終わったもう一人のおばあちゃんが戻って来た。
テーブルやら地面やらにぶちまかれたアイスラテに気づくと、「あらあら、どうしたの」と言いながらも、大して驚きはしない。なるほど、お二人ともさすがである。
「長い人生、いちいちこんなことで狼狽えていては、体が持たないわよ」
そう教えてくれているかのようだった。
ふと中学生らを見ると、この小惨事には気づいていない様子。仮に気づいていたとしても興味も感心もないわけで、引き続き若者の時間を楽しむことだろう。
こうして、若くもなければ年寄りでもないわたしは、とくに何をするわけでもなく、ただ目の前で起こるそれぞれの瞬間を観察するのであった。
(了)








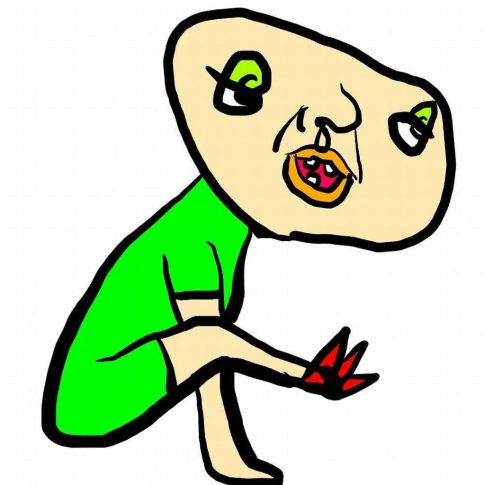












コメントを残す