(——なぜこんなところで攻撃を受けるんだ)
溜池山王駅構内にあるローソンで、キウイフルーツ味の飲むヨーグルトへ手を伸ばした瞬間、脳内に金属の針金を突き刺すかのような鋭い刺激が走った。この感覚は、ビルや店舗の入り口に設置されている虫よけ・・いや、野良猫やカラスの侵入を防ぐための超音波である。
先日も、目黒駅前の"はなまるうどん"に入ろうとしたところ、天井から放出される強力な超音波により入店を拒まれた。まぁ、はなまるうどんが・・というよりビル側が設置したものなので、はなまるうどんに罪はない。だが、せっかくの優良顧客(一般人よりも確実にたくさん食べてくれるわたし)を逃したのは、店としては痛いことだろう。・・などと適当な嫌味を言いながら、近くのタイ料理店へと矛先を変えたわけだ。
このように、都内を歩いているとちょくちょく超音波に妨害されるわたしだが、まさかコンビニのドリンクの棚に近づいただけで攻撃を受けるとは、予想だにしない出来事だった。
そもそも地下鉄構内のコンビニには、小動物はおろか虫だって入ってこない。むしろそれらの侵入を許すときは、日本、延いては世界の終焉を意味するわけで、入店者にどんどん商品を購入してもらいたい店側が、あえて超音波を発射して財布を遠ざけるようなことをするはずもない。
それなのになぜ、見えない壁に跳ね返されたかのように、わたしは咄嗟に身をひるがえしたのか——やはりなんらかの超音波をキャッチしたからだ。
コンビニの入り口で二人の友人が待っていたので、振り向きざまに「出てる、なにか出てる!」と叫んだところ、わたしの生態を熟知している友人は「超音波みたいなのが出てるの?」と、事態を正確に把握してくれた。
いったん彼女らの元へ戻ると、われわれは作戦会議を開いた。まずは"気のせいかもしれない"という選択肢だ。たまたま何かの振動音が例の超音波と似ていたため、思わず錯覚を起こした・・という可能性がある。たしかに一瞬の出来事だったため、この説は一理ある。
あとは、"さっきは超音波が発生していたかもしれないが、もう止んでいる"という可能性だ。あの時たまたま出ていたがもうすでに止まっている場合、今ならば飲むヨーグルトに近づいても大丈夫・・ということになる。
いずれにせよ、ヨーグルトを欲して止まないわたしは、改めてドリンクの棚へと向かったのである。
この感覚は静電気がパチッとくるのに似ている。二度と味わいたくない感覚ゆえに、一瞬のこととはいえ恐る恐る手を伸ばす——静電気が発生するまでは、どんなスピードで近づこうが結果は変わらないのに、それでも恐怖のあまりに縮こまってしまうのだ。
(飲むヨーグルトまであと1メートル・・70センチ・・50センチ)
ドリンクが陳列されているオープンショーケースに向かって、すり足で慎重に近づくわたし。その光景はもはや不審者以外の何者でもない。そしていよいよ飲むヨーグルトへ手を伸ばした。あと30センチ・・20センチ・・10センチ——大丈夫だ、さっきのは気のせいだったんだ!
「ギャァッッッ!!!」
あと少しで飲むヨーグルトに手が届く・・というところで、やはりなんらかの超音波に購入を阻止されたのである。大慌てで逃げるわたしの姿に驚く店員や客を尻目に、笑顔で待ち受ける友人らのところへと帰還したわたしは、改めて「なにかが出ている」事実を告げた。
「ほんとにぃ?あたしたちに聞こえるかなぁ」
呆れ顔の友人が店内へと足を踏み入れ、いざ飲むヨーグルトの前に立った。そしてチラチラと左右を見たり、何度か頭を傾げたりしながらも、お目当ての商品を掴むとわたしの元へと戻ってきた。
「とくになにもなかったよ」
そういって、キウイ味の飲むヨーグルトを手渡してくれたのだ。
なんせわたし以外の人間はあの場で異常を感知していないのだから、わたし自身に問題があるのは間違いない。だが、そんなことはどうでもいい。今後も飲むヨーグルトに近づけなくなる・・というのが困るだけで。あぁ、いったい何が出ていたんだ——。
とその時、わたしは一人のオトコと目が合った。洒落たベージュのスーツに身を包み、イマドキな塩顔にスレンダーなボディの男性は、さっきからわたしの動向を注視していた。当初からその熱視線に気づいていたわたしは、「まさかの恋の予感」を抱きながらも、飲むヨーグルトに必死だったため「とんだ醜態を晒したもんだ・・」と、切ない恋の終わりを感じていた。
だが、疑うべきはこのオトコなのではなかろうか。ややもすると彼が超音波を発していたのかもしれない。そして、誰がそれに気づくのかを観察していたのかもしれない——。
「ねぇ、あの男のヒト怪しくない?」
まるでわたしの心の声を聞いたかのように、友人がそう呟いた。——やはり彼女もそう思ったんだ!
店を後にする彼は、最後までわたしを訝しい目で見ていたが、あれはもしかすると「チッ、バレたか・・」という表情だったのかもしれない。他国のスパイが日本のコンビニにて超音波装置を仕掛け、それに反応する人間をあぶり出していたとすれば——。
わたしは身の安全を確保するべく、ブラジリアン柔術の練習に精を出そうと誓うのであった。
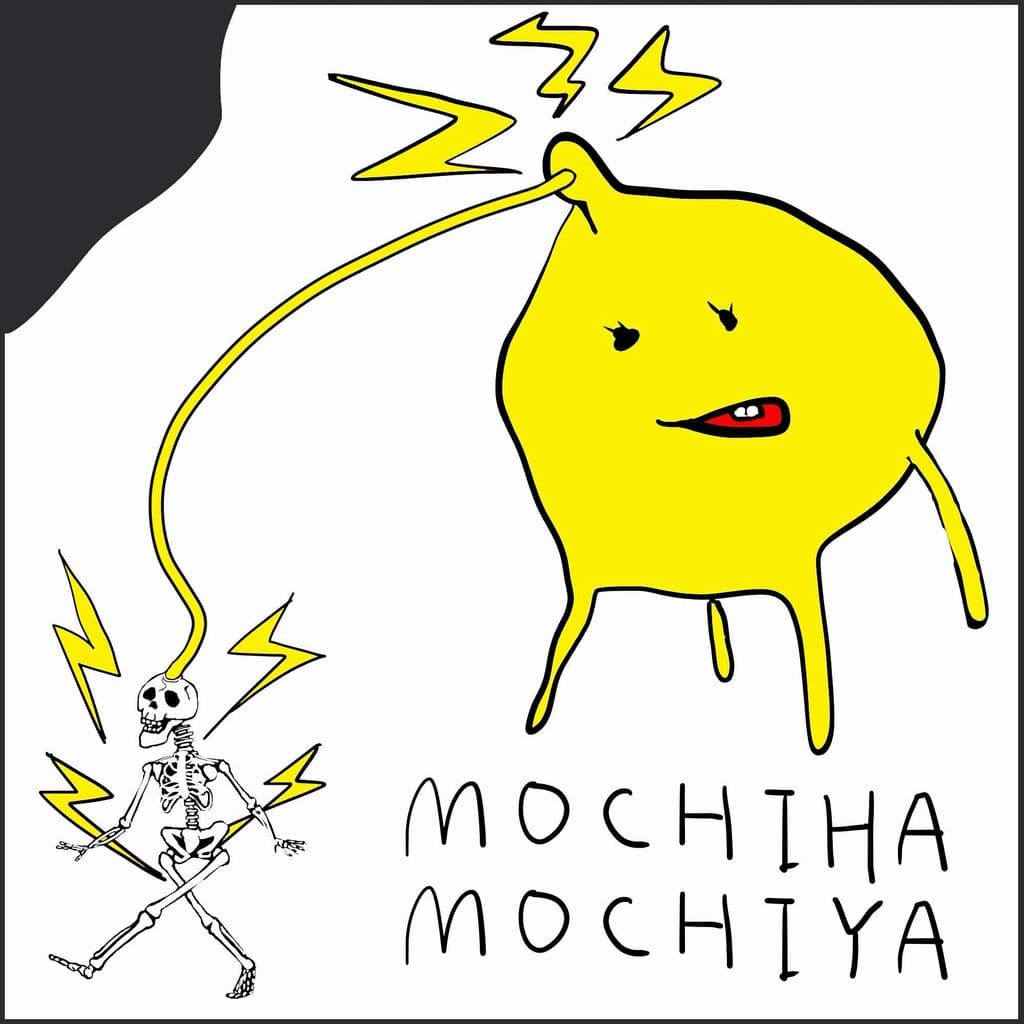


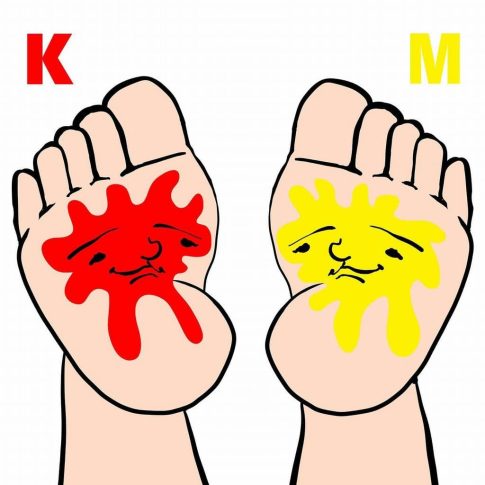

















コメントを残す